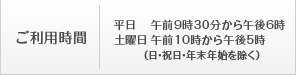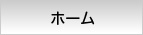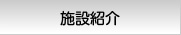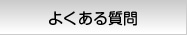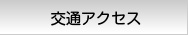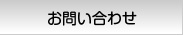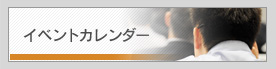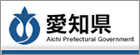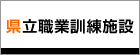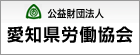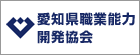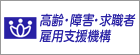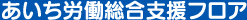ホーム > 就労支援・情報発信 > 最新の労働情報ダイジェスト
最新の労働情報ダイジェスト
情報スペースで収集するパンフレットや資料の情報を基にして最近の労働情勢や労働行政案内を行っています。
【令和6年3月29日更新】
「専門労働相談」(2024年4月~9月分)を実施 愛知県 令和6年3月27日
愛知県では、事業主や労働者等が抱える高度化・複雑化する労働問題について、県内の中小企業事業主、労働者等を対象として、社会保険労務士による「専門労働相談」を2022年度から実施している。この度、2024年度の4月から9月までの実施日時等を決定し、公表した。労務管理や就業規則の見直し、職場のトラブルなど、様々な労働問題について専門の相談員が解決に向けて助言を行う。相談料は無料、秘密厳守、オンライン相談も可能。
<利用方法>
「申込み・問合せ先」へ電話で事前予約が必要。
※同じ内容の相談は、1回までの利用。
<申込み・問合せ先>
愛知県労働局労働福祉課労働相談グループ
電話:052-589-1405
月曜日~金曜日 午前9時30分から午後6時まで
土曜日 午前10時から午後5時まで
※日曜日・祝日、年末年始を除く。
ホームページ
出展:愛知県 労働局 労働福祉課
テレワーク実施率調査結果 2月の調査結果 東京都 令和6年3月19日
東京都は、2月の都内企業のテレワーク実施状況について調査し、結果を公表した。
調査結果のポイント
(1)都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は43.4%。1月の前回調査(41.6%)に比べて、1.8ポイント増加。
(2)テレワークを実施した社員の割合は35.2%と、前回(28.9%)に比べて、6.3ポイント増加。
(3)テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が40.1%と、前回(43.0%)に比べて、2.9ポイント減少。
ホームページ
出展:東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課
令和6年における労働災害発生状況について(3月速報値) 厚生労働省 令和6年3月19日
死亡災害の発生状況
(1)全体
・死亡者数 87人(前年同期比+2人、2.4%増加)
(2)業種別発生状況
・製造業 20人(前年同期比+4人、25.0%増加)
・建設業 27人(前年同期比+2人、8.0%増加)
・林業 3人(前年同期比▲2人、40.0%減少)
・陸上貨物運送事業 13人(前年同期比▲4人、23.5%減少)
・第三次産業 19人(前年同期比+3人、18.8%増加)
(3)事故の型別発生状況
・墜落・転落 26人(前年同期比+2人、8.3%増加)
・はさまれ・巻き込まれ 16人(前年同期比▲4人、20.0%減少)
・交通事故(道路) 10人(前年同期比▲2人、16.7%減少)
※以下、「激突され」、「転倒」、「崩壊・倒壊」の順
ホームページ
出典:厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 業務係
令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在)を公表 厚生労働省 令和6年3月15日
厚生労働省と文部科学省は、令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和6年2月1日現在の状況を取りまとめ、公表した。
<就職内定率の概要>
・大学(学部)は 91.6%(前年同期差+0.7 ポイント)
・短期大学は 85.7%(同▲1.1 ポイント)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 91.4%(同+0.6 ポイント)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると 90.8%(同+0.9 ポイント)
厚生労働省と文部科学省では、新卒応援ハローワークの就職支援ナビゲーターと大学等の就職相談員との連携による新卒者等の就職支援を行っている。
ホームページ
出典:厚生労働省 人材開発統括官付 若年者・キャリア形成支援担当参事官室
一般職業紹介状況(令和6年1月分)について 厚生労働省 令和6年3月1日
厚生労働省では、令和6年1月分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
令和6年1月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.27倍となり、前月と同水準となった。
新規求人倍率(季節調整値)は2.28倍となり、前月を0.03ポイント上回った。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月と同水準となった。
1月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.2%増となり、有効求職者(同)は0.1%減となった。
1月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると3.0%減となった。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.91倍、最低は大阪府の1.06倍、受理地別では、最高は東京都と福井県の1.74倍、最低は神奈川県の0.89倍となった。
ホームページ
出展:厚生労働省 職業安定局 雇用政策課
「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金 計画届受理状況の取りまとめ(令和6年1月末時点) 厚生労働省 令和6年2月29日
厚生労働省では、「年収の壁・支援強化パッケージ」の対応として、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)を創設し、同コースを活用する予定の事業主から計画届を受け付けている。今般、計画届の受理状況を取りまとめるとともに、実際の企業の活用事例をまとめて公表した。今後も、こうした好事例を収集・周知するとともに、さらなる活用促進を図る。
【計画届受理件数及び取組予定労働者数(令和6年1月末時点)】
・計画届受理件数:3,749件
・取組予定労働者数:144,714人(令和5~7年度合計)※計画届提出時点の見込みとして記載された労働者数
【企業における実際の活用事例】
・活用事例1:パート従業員との丁寧な対話を重ね、各従業員のニーズに応じ、社会保険適用時処遇改善コースの複数のメニューを活用。
・活用事例2:新たに社会保険に加入するパート従業員に対し、社会保険適用時処遇改善コースを活用して社会保険適用促進手当を支給するとともに、既に社会保険に加入している一定の収入以下の従業員に対しても、企業独自で同手当を支給。
ホームページ
出展:厚生労働省 雇用環境・均等局 有期・短時間労働課
2023年労働条件・労働福祉実態調査について 愛知県 令和6年2月27日
愛知県では、県内の企業における労働時間などの労働条件等を把握し、労働関連施策の基礎資料とすることを目的として「労働条件・労働福祉実態調査」を毎年実施しており、2023 年の調査結果をとりまとめ公表した。
・ 年次有給休暇の取得日数は 11.8 日(前年 12.3 日)、取得率は 66.7%(同 69.1%)であった。中小企業における取得率は 62.9%(同 58.0%)であった。
※本調査では、中小企業の定義を「常用労働者 10 人~299 人を雇用する民営企業」としている。
・ 労働時間の短縮に向けた取組を実施している企業の割合は 63.4%で、前年より4.9 ポイント上昇。取組内容のうち最も高かったのは「年次有給休暇の半日単位取得制度の活用」(57.6%)、次いで「年次有給休暇の取得促進」(43.0%)であった。
・ 男性の育児休業取得率は 25.7%で、昨年より 14.9 ポイント上昇し、過去最高となった。また、男性従業員の育児休業期間は、「2週間~1か月未満」が 30.0%と最も高く、次いで「1か月~3か月未満」が 23.8%であった。男性従業員の育児休業の取得促進に取り組むに当たって困難なことや課題と感じることとして最も高かったのは「代替要員の確保が困難」(74.9%)、次いで「取得しやすい職場の雰囲気づくり」(34.3%)であった。
ホームページ
出展:愛知県 労働局 労働福祉課
毎月勤労統計調査 令和5年12月確報 厚生労働省 令和6年2月27日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年12月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は572,334円(0.8%増)となった。うち一般労働者が793,588円(1.4%増)、パートタイム労働者が117,678円(2.4%増)となり、パートタイム労働者比率が32.82%(0.59ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は326,465円(1.8%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,307円(3.8%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は2.0%増となった。
うち一般労働者が1.9%増、パートタイム労働者が4.0%増となった。
・就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(3.8%減)となった。
ホームページ
出展:厚生労働省 政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
令和6年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(令和5年12月末現在) 文部科学省 令和6年2月22日
<結果の概要>
1.就職希望者数・就職内定者数等
卒業予定者 928,080人(前年同月 971,396人)
就職希望者 129,233人(前年同月 137,685人)
うち就職内定者 117,713人(前年同月 125,171人)
うち未内定者 11,520人(前年同月 12,514人)
2.就職内定率(就職希望者に対する就職内定者の割合)
91.1%(前年同月比 0.2ポイント増)
○男女別
男子 91.8%(前年同月比0.1ポイント増) 女子 89.8%(前年同月比0.3ポイント増)
○学科別(就職内定率が高い順)
「工業」96.6%、「商業」94.5%、「農業」93.5%、「看護」93.4%、「水産」93.4%、「情報」91.7%、「福祉」90.8%、「家庭」89.6%、 「総合学科」89.0%、「普通」84.5%
○都道府県別
就職内定率の高い県:富山県 97.8%、三重県 96.6%、山口県 96.3%、 福島県 96.3%、福井県 96.1%、岩手県 95.8%
就職内定率の低い県:沖縄県 67.1%、神奈川県 81.7%、東京都 83.6%、 高知県 85.5%、千葉県 85.6%、北海道 58.7%
ホームページ
出典:文部科学省初等中等教育局児童生徒課
人口推計(令和5年9月確定値、令和6年2月概算値) 総務省 令和6年2月20日
【2024年(令和6年)2月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2399万人で、前年同月に比べ64万人減少
【2023年(令和5年)9月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2434万8千人で、前年同月に比べ62万3千人減少
・15歳未満人口は1420万3千人で、前年同月に比べ32万人減少
・15~64歳人口は7392万1千人で、前年同月に比べ28万3千人減少
・65歳以上人口は3622万5千人で、前年同月に比べ2万1千人減少
うち75歳以上人口は 2002万2千人で、前年同月に比べ72万5千人増加
<日本人人口> 1億2127万人で、前年同月に比べ83万4千人減少
ホームページ
出典:総務省統計局
令和6年における労働災害発生状況について(2月速報値) 厚生労働省 令和6年2月19日
死亡災害の発生状況
(1)全体
・死亡者数 37人(前年同期比+5人、15.6%増加)
(2)業種別発生状況
・製造業 11人(前年同期比+1人、10.0%増加)
・建設業 12人(前年同期比+4人、50.0%増加)
・林業 2人(前年同期比+2人)
・陸上貨物運送事業 4人(前年同期比▲2人、33.3%減少)
・第三次産業 7人(前年同期比+1人、16.7%増加)
(3)事故の型別発生状況
・墜落・転落 13人(前年同期比+7人、116.7%増加)
・はさまれ・巻き込まれ 9人(前年同期比▲4人、30.8%減少)
・交通事故(道路) 4人(前年同期比▲1人、20.0%減少)
※以下、「崩壊・倒壊」、「激突され」、「有害物との接触」、「交通事故(その他)」が2件ずつ
ホームページ
出典:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
テレワーク実施率1月の調査結果公表 東京都 令和6年2月15日
東京都は、1月の都内企業のテレワーク実施状況について調査を行い、公表した。
調査結果のポイント
(1)都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は41.6%。12月の前回調査(46.1%)に比べて4.5ポイント減少。
(2)テレワークを実施した社員の割合は28.9%と前回(35.0%)に比べて、6.1ポイント減少。
(3)テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が43.0%と、前回(46.4%)に比べて、3.4ポイント減少
ホームページ
出典:東京都産業労働局
令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定される 全国健康保険協会
令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)から適用となる。
愛知県は10.01%から10.02%に変更
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わる。
ホームページ
出典:全国健康保険協会
最近の雇用情勢(令和5年12月分及び令和5年分) 愛知労働局 令和6年1月30日
愛知労働局は、最近の雇用情勢(令和5年12月分及び令和5年分)を公表した。
令和5年12月分
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.33倍(対前月比0.01ポイント減)
有効求人数(季節調整値)132,533人(対前月比0.3%増)
有効求職者数(季節調整値)100,011人(対前月比1.6%増)
・有効求人倍率は2か月連続で低下
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値)2.23倍(対前月比0.11ポイント減)
新規求人数(季節調整値)44,560人(対前月比0.6%増)
新規求職者数(季節調整値)19,972人(対前月比5.5%増)
・新規求人倍率は2か月連続で低下
令和5年分
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(原数値・年平均)1.35倍(対前年比0.02ポイント減)
有効求人倍(原数値・年平均)132,659人(対前年比-2.1%減)
有効求職者数(原数値・年平均)98,086人(対前年比-0.6%減)
ホームページ
出典:愛知労働局職業安定部職業安定課
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について 厚生労働省 令和6年1月30日
労働政策審議会は令和6年1月30日に諮問された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」について、同日、厚生労働省案をおおむね妥当と答申した。
厚生労働省は、この答申を受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定。
答申分・報告分
https://www.mhlw.go.jp/content/001200555.pdf
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案要綱」(諮問文)
https://www.mhlw.go.jp/content/001200561.pdf
ホームページ
出典:厚生労働省雇用環境・均等部職業生活両立課
労働力調査(基本集計)2023年平均結果の要約 総務省 令和6年1月30日
総務省統計局は、労働力調査(基本集計)2023年平均結果の集計を公表した。
1.2023年平均の完全失業率は2.6%と前年と同率 完全失業者数は178万人と比べ1万人減少(2年連続の減少)
2.2023年平均の就業者数は6747万人と、前年に比べ24万人増加(3年連続の増加)
3.2023年平均の就業者のうち、前年に比べ最も増加した産業は「宿泊業,飲食サービス業」
4.2023年平均の正規の職員・従業員数は3615万人と、前年に比べ18万人増加(9年連続の 増加)非正規の職員・従業員数は2124万人と23万人増加(2年連続の増加)
5. 2023年平均の労働力人口は6925万人と、前年に比べ23万人増加(2年ぶりの増加)
6.2023年平均の非労働力人口は4084万人と、前年に比べ44万人減少(3年連続の減少)
ホームページ
出典:総務省統計局
県内大学・短期大学の2024年3月卒業予定者の就職内定率(12月末現在)は86.5% ~前年12月末と比べて0.9ポイント上昇~ 愛知県 令和6年1月29日
愛知県では、1994年度から県内の大学・短期大学における就職内定状況を調査・公表している。
この度、2023年度(2024年3月)に県内の大学等を卒業する予定者について、2023年12月末現在の就職内定状況を取りまとめ公表した。
大学・短期大学を合わせた全体の就職内定率は86.5%(前年12月末:85.6%、0.9ポイント上昇)となった。
ホームページ
出典:愛知県労働局就業促進課
中部圏初開催「外国人留学生等対象合同企業説明会」について~国際競争力の強化や国籍を問わず優秀な外国人留学生の採用を検討している企業を支援~ 愛知労働局 令和6年1月26日
令和3年度における日本の大学等の外国人留学生の 58%が日本国内での就職を希望しているにもかかわらず、国内就職率は 46.5%にとどまっているが、一方では、国際競争力の強化や国籍を問わず優秀な人材を確保する観点から、外国人留学生の採用を検討している企業が増加している。
そのため、愛知労働局では、大学等に在学中の留学生に対し、採用意欲のある企業及び団体から直接説明を受ける機会を提供し、外国人留学生等の就職促進を図るとともに、企業等の外国人確保に資することを目的として、「外国人留学生等対象合同企業説明会」を開催する。
詳細は下記URLから
ホームページ
出典:愛知労働局職業安定部職業対策課
労働法講座Ⅱ『複雑・多様化する「労働」を考える』開催 公益財団法人愛知県労働協会
全5日間の日程を通して、労働に関する法律や、様々な労働問題について体系的に学ぶことで、職場内における紛争の未然防止や職場における労働問題解決や、最新労働情報の入手、安定した労使関係の構築などに役立つ。
重要な判例や法改正について、専門家から詳しい解説を学べるので、企業の人事労務担当者や社会保険労務士、事業主・経営者、労働組合委員などにおすすめの講座。
申込方法
・WEBでお申込の方は専用フォームより申込
・FAXでお申込の方は申込用紙
(https://ailabor.or.jp/rodo/media-download/526/f2ee63abc5582cc2/)にご記入の上、052-583-0585まで
ホームページ
出典:公益財団法人愛知県労働協会
毎月勤労統計調査 令和5年11月確報 厚生労働省 令和6年1月23日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年11月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は289,905円(0.7%増)となった。うち一般労働者が379,900円(1.1%増)、パートタイム労働者が103,993円(2.3%増)となり、パートタイム労働者比率が32.68%(0.72ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は325,898円(1.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,301円(4.2%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は2.0%増となった。
うち一般労働者が1.8%増、パートタイム労働者が3.3%増となった。
・就業形態計の所定外労働時間は10.3時間(1.8%減)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
あいち人財強化プロジェクト 2025年3月大学等卒業予定者などを対象とした「大学生等会社合同説明会」の出典企業と開催内容決定 愛知県 令和6年1月19日
愛知県では、県内の経済団体等と連携して、2025年3月卒業予定の学生や卒業後おおむね3年以内の若年者の就職支援と、採用意欲のある県内企業の人材確保支援を目的に「大学生等会社合同説明会」を開催する。
当日は、来春採用を予定している様々な業種の企業(100社)が出展するとともに、就職に関するアドバイスが受けられる「職業適性検査」を始めとする各種支援コーナーを開設する。
入場無料、予約など事前手続き不要。入退場自由
参加に対する問合わせ先
大学生等会社合同説明会運営協議会事務局(公益財団法人愛知県労働協会)
名古屋市中村区名駅4丁目4-38愛知県産業労働センター(ウインクあいち)17階
電話:052-485-7156(受付時間 午前9時30分から午後6時まで、土日・祝日を除く)
ホームページ
出典:愛知県
「令和6年能登半島地震」で被災された方の就労相談窓口について 令和6年1月18日愛知県
愛知県では、令和6年能登半島地震によって被災された方々に対する支援の一環として、相談窓口において、愛知県内での就労を希望する方からの就労相談に対応する。
相談窓口利用方法(各窓口共有)
下記ホームページの「相談窓口」に記載された利用時間内に窓口に直接お越しいただくか、電話番号に連絡。
対面、電話相談ともに予約は不要。
ホームページ
出典:愛知県
令和5年における労働災害発生状況について(12月速報値) 厚生労働省 令和6年1月18日
厚生労働省は、令和5年における労働災害発生状況(12月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数677人 (前年同期比29人減少)
(2)業種別発生状況
製造業129人 (前年同期比3人減少)
建設業199人 (前年同期比65人減少)
林業27人 (前年同期比1人減少)
陸上貨物運送事業96人 (前年同期比18人増加)
第三次産業186人 (前年同期比 16人増加)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落182人 (前年同期比 30人減少)
交通事故(道路)132人 (前年同期比22人増加)
はさまれ・巻き込まれ104人 (前年同期比5人減少)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「崩壊・倒壊」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和5年10月確報 厚生労働省 令和5年12月22日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年10月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は279,232円(1.5%増)となった。うち一般労働者が363,772円(1.9%増)、パートタイム労働者が103,102円(3.2%増)となり、パートタイム労働者比率が32.50%(0.58ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は326,028円(1.7%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,293円(3.8%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は2.6%増となった。
うち一般労働者が2.5%増、パートタイム労働者が3.3%増となった。
・就業形態計の所定外労働時間は10.3時間(1.8%減)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
あいちの人口 愛知県人口動向調査結果 年報(2023年) 愛知県 令和5年12月21日
愛知県は、あいちの人口 愛知県人口動向調査結果を公表した。
この推計人口は、「令和2年国勢調査結果」(2020年10月1日現在)を基礎とし、住民基本台帳による月間異動数を加減して推計したもの。
愛知県の人口は、7,480,897人(男 3,725,279人、女3,755,618人)となり、1年間で16,624人減少し、四年連続の減少となった。
社会増減
転入数は390,967人、転出数は374,484人、その他の増減(職権記載や職権削除等)は3,034人の減少で、13,449人の増加となり、2年連続の社会増加となった。
また、愛知県外からの転入数は181,316人、県外への転出数は163,995人で、17,321人の転入超過となり、県外からの転入超過は2年連続となった。
ホームページ
出典:愛知県
人口推計(令和5年12月概算値、令和5年7月確定値) 総務省統計局 令和5年12月20日
総務省は、人口推計(令和5年12月概算値、令和5年7月確定値)を公表した。
【2023年(令和5年)12月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2424万人(前年同月比62万人減少)
【2023年(令和5年)7月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2451万7千人(前年同月比60万8千人減少)
・15歳未満人口は1428万1千人(前年同月比 30万8千人減少)
・15~64歳人口は 7401万5千人(前年同月比 26万9千人減少)
・65歳以上人口は3622万人(前年同月比3万1千人減少)
うち75歳以上人口は1991万5千人(前年同月比75万5千人増加)
<日本人人口> 1億2144万1千人(前年同月比 82万2千人 減少)
ホームページ
出典;総務省統計局
「第3回優良企業事業者育成セミナー」の参加者募集 愛知県 令和5年12月20日
愛知県では、事業者の皆様方に、「消費者志向経営」について考えていただくとともに、消費者関連法の基礎知識を身につけていただき、今後の事業活動に生かしていただくため、「第3回優良事業者育成セミナー」を開催する。
・申込方法
(1)Webページからの申込み
適格消費者団体「特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海」のWebページにアクセス又は二次元コードを読み取り、申込画面に必要事項を入力の上、申込み
Webページ:https://cnt.or.jp/topics/post-6997.html
(2)FAXでの申込み
ちらし裏面の参加申込欄に必要事項を入力の上、申込み
FAX 052-734-8108
セミナーのチラシ:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/487089.pdf
ホームページ
出典:愛知県
労働災害発生状況について(令和5年12月速報値) 厚生労働省 令和5年12月18日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年12月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数609人 (前年同期比39人減少)
(2)業種別発生状況
製造業113人 (前年同期比10人減少)
建設業175人 (前年同期比67人減少)
林業25人 (前年同期比3人減少)
陸上貨物運送事業90人 (前年同期比20人増加)
第三次産業169人 (前年同期比 16人増加)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落159人 (前年同期比 37人減少)
交通事故(道路)119人 (前年同期比24人増加)
はさまれ・巻き込まれ92人 (前年同期比10人減少)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「崩壊・転落」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
令和6年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(令和5年10月末現在)公表 文部科学省 令和5年12月15日
文部科学省では、高校生の就職問題に適切に対処するための参考資料を得るために、令和6年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況を調査し、このほど、令和5年10月末現在の状況を取りまとめ、公表した。
就職内定率 77.2%(前年同月比1.1ポイント増)
・男女別
男子77.8%(同0.8ポイント増)、女子76.0%(同1.4ポイント増)。
・学科別(就職内定率の高い順)
「工業」88.4%、「看護」88.1%、「商業」82.8%、「水産」80.7%、「農業」79.2%、「福祉」 78.6%、「情報」78.3%、「家庭」78.1%、「総合学科」75.0%、「普通」64.1%
ホームページ
出典:文部科学省ホームページ
愛知県特定最低賃金(2業種)改正―令和5年12月16日発効― 愛知労働局
愛知県では、12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正される。(参考:愛知県最低賃金は10月1日より時間額1,027円)
改定最低賃金(効力発生日 令和5年12月16日)
・鋼鉄業・製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,059円
・輸送用機械器具製造業 1,028円
(※ 令和5年10月1日から12月15日まで、愛知県最低賃金 1,027円が適用される。)
問合せは事業先を管轄する労働基準監督署まで。
ホームページ
出典:愛知労働局
労働力調査(基本集計)―2023年10月分― 総務省統計局 令和5年12月1日
【就業者】
・就業者数は6771万人。前年同月に比べ16万人の増加。15か月連続の増加
・雇用者数は6089万人。前年同月に比べ8万人の増加。20か月連続の増加
・正規の職員・従業員数は3611万人。前年同月に比べ3万人の減少。3か月ぶりの減少。
非正規の職員・従業員数は2140万人。前年同月に比べ24万人の増加。2か月連続の増加
・主な産業別就業者を前年同月と比べると、「宿泊業,飲食サービス業」、「情報通信業」、「学術研究,専門・技術サービス業」などが増加
【就業率】(就業者/15歳以上人口×100)
・就業率は61.5%。前年同月に比べ0.3ポイントの上昇
・15~64歳の就業率は79.1%。前年同月に比べ0.4ポイントの上昇
【完全失業者】
・完全失業者数は175万人。前年同月に比べ3万人の減少。2か月連続の減少
・求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が4万人の減少。
「自発的な離職(自己都合)」が11万人の増加。「新たに求職」が6万人の減少
【完全失業率】(完全失業者/労働力人口×100)
・完全失業率(季節調整値)は2.5%。前月に比べ0.1ポイントの低下
【非労働力人口】
・非労働力人口は4062万人。前年同月に比べ33万人の減少。20か月連続の減少
ホームページ
出典:総務省統計局
最近の雇用情勢(令和5年10月分) 愛知労働局 令和5年12月1日
愛知労働局は、最近の雇用情勢(令和5年10月分)を公表した。
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.35倍(対前月比0.01ポイント増)
有効求人数(季節調整値)132,764人(対前月比0.7%増)
有効求職者数(季節調整値)98,544人(対前月比0.2%増)
・有効求人倍率は3か月ぶりに上昇
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値)2.49倍(対前月比0.14ポイント増)
新規求人数(季節調整値)46,950人(対前月比8.7%増)
新規求職者数(季節調整値)18,844人(対前月比2.5%増)
・新規求人倍率は4か月ぶりに上昇
ホームページ
出典:愛知労働局
一般職業紹介状況(令和5年10月分) 厚生労働省 令和5年12月1日
厚生労働省では、令和5年10月分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
令和5年10月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.30倍となり、前月を0.01ポイント上回った。
新規求人倍率(季節調整値)は2.24倍となり、前月を0.02ポイント上回った。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.01倍となり、前月を0.01ポイント下回った。
10月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.0%増加となり、有効求職者(同)は0.3%減となった。
10月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.8%減少となった。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.95倍、最低は大阪府の1.10倍、受理地別では、最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.93倍となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
あいちの就業状況―労働力調査愛知県分集計結果(2023年7月~9月(平均))― 愛知県 令和5年11月30日
愛知県は、あいちの就業状況―労働力調査愛知県分集計結果(2023年7月~9月(平均))―を公表した。
・労働力人口は426万6千人となり、前年同期に比べ6千人の増加
・労働力人口比率は65.1%となり、前年同期に比べ0.1ポイント低下
・就業者数は418万2千人となり、前年同期に比べ8千人増加
・完全失業者数は8万4千人となり、前年同期に比べ2千人減少
・完全失業率は2.0%となり、前年同期と同率
・非労働力人口は227万2千人となり、前年同期に比べ4千人増加
ホームページ
出典:愛知県
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年9月分)― 愛知県 令和5年11月30日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年9月分)―を公表した。
2023年9月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は285,895円となり、前年同月に比べ2.1%の増加(21か月連続)。
所定外労働時間は11.9時間となり、前年同月と同水準。
常用雇用指数は98.2(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ0.1%の増加(28か月ぶり)。
ホームページ
出典:愛知県
毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果確報 厚生労働省 令和5年11月21日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年9月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は277,700円(0.6%増)となった。うち一般労働者が361,736円(1.2%増)、パートタイム労働者が101,854円(1.6%増)となり、パートタイム労働者比率が32.43%(0.75ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は324,753円(1.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,280円(3.3%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は1.8%増となった。
うち一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が3.0%増となった。
・就業形態計の所定外労働時間は9.9時間(3.0%減)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
人口推計(令和5年11月概算値、令和5年6月確定値) 総務省統計局 令和5年11月20日
総務省は、人口推計(令和5年月11概算値、令和5年6月確定値)を公表した。
【2023年(令和5年)11月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2431万人(前年同月比60万人減少)
【2023年(令和5年)6月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2451万1千人(前年同月比59万2千人減少)
・15歳未満人口は1429万(前年同月比 30万8千人減少)
・15~64歳人口は 7400万5千人(前年同月比 25万1千人減少)
・65歳以上人口は3621万6千人(前年同月比3万4千人減少)
うち75歳以上人口は1986万8千人(前年同月比76万3千人増加)
<日本人人口> 1億2144万8千人(前年同月比 82万4千人 減少)
ホームページ
出典;総務省統計局
令和5年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ(9月末現在)―高校生の内定率は63.0%― 厚生労働省 令和5年11月17日
厚生労働省は、令和6年3月に高校や中学を卒業する生徒について、令和5年9月末現在の公共職業安定所(ハローワーク)求人における求人・求職・就職内定状況を取りまとめた。対象は、学校やハローワークからの職業紹介を希望した生徒。
【高校新卒者】
○ 就職内定率 63.0%で、前年同期比 0.6 ポイントの増
○ 就職内定者数 約7万7千人で、同 4.0%の減
○ 求人数 約 46 万5千人で、同 9.4%の増
○ 求職者数 約 12 万3千人で、同 4.8%の減
○ 求人倍率 3.79 倍で、同 0.5 ポイントの上昇
【中学新卒者】
○ 求人数 784 人で、前年同期比 3.3%の増
○ 求職者数 666 人で、同 2.9%の減
○ 求人倍率 1.18 倍で、同 0.07 ポイントの上昇
※ 中学新卒者の選考・内定開始期日は、令和6年1月1日以降(積雪指定地域では令和5年 12 月1日以降)。
ホームページ
出典:厚生労働省
令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(10月1日状況)を公表―大学生の就職内定率は74.8%と、前年同期を0.7ポイント上回る― 厚生労働省 令和5年11月17日
厚生労働省と文部科学省は、令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和5年10月1日現在の状況を取りまとめ公表した。
【就職内定率の概要】
・大学(学部)は74.8%(前年同月比+0.7ポイント)
・短期大学は39.9%(前年同月比-6.0ポイント)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では72.3%(同増減なし)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると70.2%(前年同月比-0.3ポイント)
ホームページ
出典:厚生労働省
労働災害発生状況について(令和5年11月速報値) 厚生労働省 令和5年11月17日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年11月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数545人 (前年同期比39人減少)
(2)業種別発生状況
製造業101人 (前年同期比15人減少)
建設業161人 (前年同期比55人減少)
林業21人 (前年同期比3人減少)
陸上貨物運送事業80人 (前年同期比18人増加)
第三次産業148人 (前年同期比 7人増加)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落141人 (前年同期比 31人減少)
交通事故(道路)111人 (前年同期比26人増加)
はさまれ・巻き込まれ85人 (前年同期比8人減少)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「崩壊・転落」及び「高温・低温物との接触」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
愛知県毎月勤労統計調査地方調査結果 2023年夏季賞与の支給状況 愛知県 令和5年11月10日
愛知県は、愛知県毎月勤労統計調査地方調査結果 2023年夏季賞与の支給状況を公表した。
この調査結果は、毎月勤労統計調査の2023年6月分から2023年8月分までの「特別に支給された給与」のうち、賞与として支給された給与(夏季賞与)を抜き出して特別に集計したもの。
支給労働者1人平均支給額は、調査産業計で548,896円となり、前年に比べ2.0%増加した。
支給事業所数割合は、調査産業計で88.9%となった。
支給労働者数割合は、調査産業計で92.4%となった。
所定内給与に対する支給割合は、調査産業計で1.26か月分となった。
ホームページ
出典:愛知県
労働力調査(詳細集計)2023年7月~9月期平均公表 総務省統計局 令和5年11月10日
【正規、非正規の職員・従業員】
・役員を除く雇用者5750万人のうち、正規の職員・従業員は3617万人と、前年同期に比べ31万人の増加。2期連続の増加。
非正規の職員・従業員は2133万人と、13万人の増加。7期連続の増加
・非正規の職員・従業員について、現職の雇用形態についた主な理由別にみると、「自分の都合のよい時間に働きたいから」とした者が728万人と、前年同期に比べ33万人の増加。
「家計の補助・学費等を得たいから」とした者が379万人と、2万人の増加。
「正規の職員・従業員の仕事がないから」とした者が183万人と、28万人の減少
【失業者(失業期間別)】
・失業者は203万人と、前年同期に比べ3万人の増加。失業期間別にみると、失業期間が「3か月未満」の者は78万人と、1万人の増加、「1年以上」の者は61万人と、3万人の減少
【非労働力人口(就業希望の有無別)】
・非労働力人口は4031万人と、前年同期に比べ27万人の減少。このうち就業希望者は226万人と、2万人の減少
・就業希望者について、求職活動をしていない理由別にみると、「適当な仕事がありそうにない」とした者は77万人と、前年同期に比べ5万人の減少
【未活用労働】
・就業者6768万人のうち、追加就労希望就業者は193万人と、前年同期に比べ19万人の増加
・非労働力人口4031万人のうち、潜在労働力人口は39万人と、前年同期に比べ3万人の増加
・未活用労働指標の中で、最も包括的に未活用労働を捉えた未活用労働指標4(LU4)は6.2%と、前年同期に比べ0.3ポイントの上昇
ホームページ
出典:総務省統計局
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年8月分)― 愛知県 令和5年10月31日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年8月分)―を公表した。
2023年8月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は283,681円となり、前年同月に比べ2.6%の増加(20か月連続)。
所定外労働時間は10.9時間となり、前年同月に比べ3.9%の増加(4か月連続)。
常用雇用指数は98.2(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ0.3%の減少(22か月連続)。
ホームページ
出典:愛知県
最近の雇用情勢(令和5年9月分) 愛知労働局 令和5年10月31日
愛知労働局は、最近の雇用情勢(令和5年9月分)を公表した。
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.34倍(対前月比0.02ポイント減)
有効求人数(季節調整値)131,820人(対前月比1.4%減)
有効求職者数(季節調整値)98,368人(対前月比0.2%減)
・有効求人倍率は2か月連続で低下
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値)2.35倍(対前月比0.04ポイント減)
新規求人数(季節調整値)43,186人(対前月比4.9%減)
新規求職者数(季節調整値)18,382人(対前月比3.3%減)
・新規求人倍率は3か月連続で低下
ホームページ
出典:愛知労働局
労働力調査(基本集計)2023年9月分公表 総務省統計局 令和5年10月31日
【就業者】
・就業者数は6787万人。前年同月に比べ21万人の増加。14か月連続の増加
・雇用者数は6124万人。前年同月に比べ54万人の増加。19か月連続の増加
・正規の職員・従業員数は3633万人。前年同月に比べ44万人の増加。2か月連続の増加。
非正規の職員・従業員数は2141万人。前年同月に比べ8万人の増加。2か月ぶりの増加
・主な産業別就業者を前年同月と比べると、「宿泊業,飲食サービス業」、「建設業」、 「生活関連サービス業,娯楽業」などが増加
【就業率】(就業者/15歳以上人口×100)
・就業率は61.6%。前年同月に比べ0.3ポイント の上昇
・15~64歳の就業率は79.3%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇
【完全失業者】
・完全失業者数は182万人。前年同月に比べ 5万人の減少。3か月ぶりの減少
・求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が6万人の減少。 「自発的な離職(自己都合)」が4万人の増加。「新たに求職」が1万人の減少
【完全失業率】(完全失業者/労働力人口×100)
・完全失業率(季節調整値)は2.6%。前月に比べ0.1ポイントの低下
【非労働力人口】
・非労働力人口は4040万人。前年同月に比べ31万人の減少。19か月連続の減少
ホームページ
出典:総務省統計局
新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)公表 厚生労働省 令和5年10月20日
厚生労働省は、令和2年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況を取りまとめ公表した。
就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が 37.0%(前年度と比較して 1.1 ポイン
ト上昇)、新規大学卒就職者が 32.3%(同 0.8 ポイント上昇)となった。
厚生労働省では、新卒応援ハローワークなどで、引き続き、新規学卒就職者に対する
職場定着支援や離職者等に対するきめ細かな就職支援を行っていく。
ホームページ
出典:厚生労働省
労働災害発生状況について(令和5年10月速報値) 厚生労働省 令和5年10月19日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年10月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数506人 (前年同期比9人減少)
(2)業種別発生状況
製造業95人 (前年同期比 6人減少)
建設業152人 (前年同期比40人減少)
林業19人 (前年同期比 0人増減なし)
陸上貨物運送事業75人 (前年同期比24人増加)
第三次産業133人 (前年同期比 4人減少)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落130人 (前年同期比 21人減少)
交通事故(道路)102人 (前年同期比30人増加)
はさまれ・巻き込まれ86人 (前年同期比3人増加)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「転倒」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
愛知県の特定最低賃金(2業種)の改正について 愛知労働局 令和5年10月16日
愛知地方最低賃金審査会は、2023年8月4日、愛知労働局長から愛知県の特定最低賃金の改正決定に係る諮問を受け、慎重に協議を重ねた結果、10月16日、愛知労働局に対し、現行の愛知県特定最低賃金(2業種)の時間額を改正決定する旨の答申を行った。
この答申を受けて愛知労働局は、本年12月16日から効力が発生(予定)するよう異議申立などの所要の手続を行うこととしている。
「愛知県特定最低賃金」改正決定状況
・製造業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 引上額41円、答申金額(時間額)1,059円
・輸送用機械器具製造業最低賃金 引上額31円、答申金額(時間額)1,028円
ホームページ
出典:愛知労働局
2023年度第2回労働講座の受講者募集―労働者の健康確保と適正な労働時間管理― 愛知県 令和5年10月13日
愛知県では、安定した労使関係を形成するため、中小企業の事業主や人事労務担当者等を対象に、労働問題を解決する上で必要な基礎的知識などを提供する労働講座を開催している。この度、2023年度第2回労働講座の受講者募集を開始した。
本講座では、愛知労働局労働基準部健康課長の山本祥喜氏から、労働者の心身の健康確保について、社会保険労務士の有田知史氏からは、適正な労働時間管理のポイントについて講演する。
【申込方法】
受講申込書(ちらし裏面)に必要事項を記入の上、以下の【問合せ先】までFAX又は郵送で申込み。
受講申込書【https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/477619.pdf】
また、あいち電子申請・届出システムから申込みも可能。
【問合せ先】
愛知県労働局労働福祉課 調査・啓発グループ
〒460-8501名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
電話 052-954-6359(ダイヤルイン) FAX 052-954-6926
ホームページ
出典:愛知県
令和5年9月のテレワーク実施率調査結果 東京都 令和5年10月12日
東京都は、令和5年9月の都内企業のテレワーク実施状況について、調査を行い結果を公表した。
調査結果のポイント
都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は45.2%。8月の前回調査(45.3%)に比べて0.1ポイント減少。
テレワークを実施した社員の割合は33.3%と、前回(34.4%)に比べて、1.1ポイント減少。
テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が44.4%と、前回(44.2%)に比べて、0.2ポイント増加。
ホームページ
出典:東京都
11月は「過労死等防止啓発月間」~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~ 厚生労働省 令和5年10月10日
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行う。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施している。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行う。
【過労死等】とは
(1)業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
(2)業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
(3)死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
ホームページ
出典:厚生労働省
あいちの人口 愛知県人口動向調査結果 月報(2023年9月1日現在) 愛知県 令和5年10月10日
愛知県は、愛知県人口動向調査結果 月報(2023年9月1日現在)を公表した。
9月1日現在の愛知県の人口は、7,481,546人(男 3,725,753人、女3,755,793人)となり、前月に比べ104人減少(男214人増加、女318人減少)し、前年同月に比べ18,811人の減少(男10,529人減少、女8,282人減少)となった。
社会増減(転入と転出の差に、その他の増減を加えたもの)
8月1か月間の転入数は30,528人(男17,072人、女13,456人)、転出数は28,528人(男 15,625人、女12,903人)、その他の増(職権記載、転出取消等)は 443人、その他の減(職権消除等)は 588人で、1,855人の増加 (男1,352人増加、女 503人増加)となった。
ホームページ
出典:愛知県
「福祉・介護の就職総合フェア」を開催 愛知県 令和5年10月6日
愛知県では、福祉・介護業界に就職を希望される方や興味のある方を対象とした「福祉・介護の就職総合フェア」を開催する。なお、令和5年度「介護の仕事カムバック研修会」(第2回)を同日開催。
どなたでも参加でき、参加費は無料。
「介護の仕事カムバック研修会」を除き、事前申込みは必要なし。
【実施内容】
就職説明会、就職相談会(福祉の仕事総合相談コーナー)、福祉情報資料コーナー、令和5年度「介護の仕事カムバック研修会(第2回)」の開催(事前申込制)
【申込方法】(介護の仕事カムバック研修会のみ)
ちらし掲載の二次元コードもしくは申込フォームから直接申込みか、同じくちらし裏面の申込書を記入の上、FAXにて送付(FAX 052-212-5520)。
【問合せ先】
愛知県福祉人材センター(県事業委託先)
名古屋市東区白壁一丁目50番地 愛知県社会福祉会館5階
電話052-212-5519 FAX 052-212-5520
ホームページ
出典:愛知県
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年7月分)― 愛知県 令和5年9月29日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年7月分)―を公表した。
2023年7月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は287,621円となり、前年同月に比べ2.5%の増加(19か月連続)。
所定外労働時間は11.9時間となり、前年同月に比べ1.7%の増加(3か月連続)。
常用雇用指数は98.7(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ0.2%の減少(21か月連続)。
ホームページ
出典:愛知県
労働力調査(基本集計)2023年8月分公表 総務省統計局 令和5年9月29日
【就業者】
・就業者数は6773万人。前年同月に比べ22万人の増加。13か月連続の増加
・雇用者数は6088万人。前年同月に比べ44万人の増加。18か月連続の増加
・正規の職員・従業員数は3637万人。前年同月に比べ48万人の増加。2か月ぶりの増加。
非正規の職員・従業員数は2114万人。前年同月に比べ7万人の減少。3か月ぶりの減少
・主な産業別就業者を前年同月と比べると、 「卸売業,小売業」、「宿泊業,飲食サービス業」などが増加
【就業率】(就業者/15歳以上人口×100)
・就業率は61.4%。前年同月に比べ0.1ポイントの上昇
・15~64歳の就業率は79.2%。前年同月に比べ0.4ポイントの上昇
【完全失業者】
・完全失業者数は186万人。前年同月に比べ9万人の増加。2か月連続の増加
・求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が3万人の減少。
「自発的な離職(自己都合)」が11万人の増加。「新たに求職」が2万人の減少
【完全失業率】(完全失業者/労働力人口×100)
・完全失業率(季節調整値)は2.7%。前月と同率
【非労働力人口】
・非労働力人口は4056万人。前年同月に比べ30万人の減少。18か月連続の減少
ホームページ
出典:総務省統計局
一般職業紹介状況(令和5年8月分) 厚生労働省 令和5年9月29日
厚生労働省では、令和5年8月分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
令和5年8月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月と同水準となった。
新規求人倍率(季節調整値)は2.33倍となり、前月を0.06ポイント上回った。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.02倍となり、前月と同水準となった。
8月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%増加となり、有効求職者(同)は0.2%減となった。
8月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると1.0%増加となった。
これを産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業(9.8%増加)、教育,学習支援業(8.4%増加)、医療,福祉(4.8%増加)で増加となり、製造業(7.5%減少)、建設業(3.8%減少)、生活関連サービス業,娯楽業(3.1%減少)などで減少となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
最近の雇用情勢(令和5年8月分) 愛知労働局 令和5年9月29日
愛知労働局は、最近の雇用情勢(令和5年8月分)を公表した。
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.36倍(対前月比0.01ポイント減)
有効求人数(季節調整値)133,672人(対前月比1.0%減)
有効求職者数(季節調整値)98,575人(対前月比0.2%減)
・有効求人倍率は4か月ぶりに低下
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値)2.39倍(対前月比0.01ポイント減)
新規求人数(季節調整値)45,397人(対前月比0.4%増)
新規求職者数(季節調整値)19,019人(対前月比1.0%増)
・新規求人倍率は2か月連続で低下
ホームページ
出典:愛知労働局
毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果確報 厚生労働省 令和5年9月26日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年7月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は380,063円(1.1%増)となった。うち一般労働者が509,103円(1.8%増)、パートタイム労働者が107,354円(1.3%増)となり、パートタイム労働者比率が32.21%(0.69ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は324,967円(2.0%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,283円(4.0%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は2.3%増となった。
うち一般労働者が2.7%増、パートタイム労働者が2.1%増となった。
・就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(2.0%減)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
人口推計(令和5年4月確定値、令和5年9月概算値) 総務省統計局 令和5年9月20日
総務省は、人口推計(令和5年4月確定値、令和5年9月概算値)を公表した。
【2023年(令和5年)9月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2445万人(前年同月比52万人減少)
【2023年(令和5年)4月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2455万4千人(前年同月比 51万7千人減少)
・15歳未満人口は1436万6千人(前年同月比 30万3千人減少)
・15~64歳人口は 7401万(前年同月比 17万4千人減少)
・65歳以上人口は3619万8千人(前年同月比 4万減少)
うち75歳以上人口は1975万5千人(前年同月比75万4千人増加)
<日本人人口> 1億2157万6千人(前年同月比 81万1千人 減少)
ホームページ
出典;総務省統計局
労働災害発生状況について(令和5年9月速報値) 厚生労働省 令和5年9月19日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年9月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数428人 (前年同期比29人減少)
(2)業種別発生状況
製造業83人 (前年同期比 11人減少)
建設業128人 (前年同期比40人減少)
林業19人 (前年同期比 3人増加)
陸上貨物運送事業63人 (前年同期比 14人増加)
第三次産業107人 (前年同期比 3人減少)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落108人 (前年同期比 23人減少)
交通事故(道路)86人 (前年同期比 21人増加)
はさまれ・巻き込まれ78人 (前年同期比1人増加)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「崩壊・倒壊」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
第36回国際労働問題シンポジウム「循環型経済におけるディーセント・ワーク―公正な移行に向けて」開催 ILO駐日事務所 法政大学大原社会問題研究所 令和5年9月1日
ILO駐日事務所と法政大学大原社会問題研究所(東京都町田市)は10月24日午後2時から、東京・市ヶ谷の法政大学ボアソナード・タワーで国際労働問題シンポジウムを開催する。36回目の今年は「循環型経済におけるディーセント・ワーク ―公正な移行に向けて」と題し、気候変動と雇用との関連について議論する。
ILOは、炭素排出量を実質ゼロにする脱炭素社会への移行に際し、炭素集約的な産業や生産に依存する地域や都市、産業部門で働く人々を中心に、誰も置き去りにしないよう雇用を確保する必要性を訴える「公正な移行(Just Transition)」を推進している。
【参加申し込み方法】
専用URLから申し込み
会場参加(10月22日締め切り):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAHMt321g3Jefwdpp5Cly2ne5ej40cFY8OLVyoXqtSJPvwwg/viewform
オンライン参加:
https://ilo-org.zoom.us/webinar/register/WN_7Yox1LJvRR2wlrybhF3u9Q#/
ホームページ
出典;ILO駐日事務所
愛知県最低賃金 令和5年10月1日から時間額1,027円に改正(時間額986円から41円引き上げ) 愛知労働局
愛知県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用される。
使用者は適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならない。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,027円と比較する。
問合せは、事業所を管轄する監督署まで
ホームページ
出典:愛知労働局
統計からみた我が国の高齢者―「敬老の日」にちなんで― 総務省統計局 令和5年9月17日
総務省統計局では、「敬老の日」(9月18日)を迎えるに当たって、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者のすがたについて取りまとめた。
1.高齢者の人口
・高齢者人口は1950年以降初めての減少
一方、総人口に占める高齢者人口の割合は29.1%と過去最高
・75歳以上人口が初めて2000万人を超える
10人に1人が80歳以上となる
・日本の高齢者人口の割合は、世界で最高(200の国・地域中)
2.高齢者の就業
・高齢就業者数は、19年連続で増加し912万人と過去最多
・就業者総数に占める高齢就業者の割合は、13.6%と過去最高
・65~69 歳、70~74歳の就業率は過去最高に
・日本の高齢者の就業率は、主要国の中でも高い水準
・高齢雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は76.4%と前年に比べ0.5ポイント上昇、一方で65~69歳では3年連続低下
・「医療,福祉」の高齢就業者は10年前の約2.7倍に増加
・高齢の就業希望者のうち、希望する仕事の種類は、男性は「専門的・技術的職業」が最も多く、女性は「サービス職業」が最も多い
・高齢者の有業率は、男性は山梨県が最も高く、女性は福井県が最も高い
ホームページ
出典:総務省統計局
「デジタル化×セキュリティ事例紹介セミナー」の参加者を募集 愛知県 令和5年9月15日
デジタル化や情報セキュリティ対策を進める際には、他の企業等の事例を参考にすることが有効。
そこで、愛知県では、中小企業等におけるデジタル化の進め方、ツール及び効果に加え、サイバー攻撃の手口、情報セキュリティ対策及び国や自動車産業のガイドラインへの対応方法について、事例を交えて分かりやすく説明する「デジタル化×セキュリティ事例紹介セミナー」を開催する。
現場会場とオンラインにて開催。
【申込方法】
申込Webサイトから申込み:https://forms.office.com/e/UQEAJY1Vry
【問合せ先】
<本事業に関すること>
愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室
デジタル技術活用促進グループ
電話:052-954-7495 FAX:052-954-6943
E-mail:jisedai@pref.aichi.lg.jp
<申込み・セミナー内容に関すること>(県事業委託先)
有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所
住所:愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋37階
電話:052-565-5955
ホームページ
出典:愛知県
テレワーク・スクール(第3回・第4回)の参加者の募集開始 愛知県 令和5年9月12日
愛知県では、「あいちテレワークサポートセンター」を2021年4月に設置し、県内中小企業のテレワーク導入・定着に向けて、2023年度までの3年間で集中的な支援を行っている。
その一環として、中小企業の経営者や実務担当者を対象に、Z世代の採用・定着に繋がるDX化促進や、テレワーク環境を構築する上でのセキュリティ対策について学べる「テレワーク・スクール(第3回・第4回)」をオンライン併用で開催する。
【申込方法】
セミナー受付専用サイトから申込み。
受付専用サイト:https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/seminar/
※申込後、県業務委託先からメールで受付完了を通知。申込多数の場合は、1社あたりの参加人数を制限することもある。
【問合せ先】
あいちテレワークサポートセンター(県業務委託先:株式会社パソナ)
電話:052-581-0510(受付時間:午前9時から午後5時まで、土日祝日・年末年始を除く)
メール:aichi-telework@pasona.co.jp
ホームページ
出典:愛知県
あいちの人口 愛知県人口動向調査結果 月報(2023年8月1日現在) 愛知県 令和5年9月11日
愛知県は、愛知県人口動向調査結果 月報(2023年8月1日現在)を公表した。
7月1日現在の愛知県の人口は、7,481,650人(男 3,725,539人、女3,756,111人)となり、前月に比べ213人減少(男39人減少、女 174人減少)し、前年同月に比べ20,929人の減少(男11,972人減少、女 8,957人減少)となった。
社会増減(転入と転出の差に、その他の増減を加えたもの)
7月1か月間の転入数は 28,929人(男 16,243人、女 12,686人)、転出数は27,174人(男 15,125人、女12,049人)、その他の増(職権記載、転出取消等)は 399人、その他の減(職権消除等)は 532人で、1,622人の増加 (男1,002人増加、女 620人増加)となった.
ホームページ
出典:愛知県
「専門労働相談」(9月~3月分)を実施~社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士が職場でのお悩みの相談に応じる~ 愛知県 令和5年9月7日
愛知県では、事業主や労働者等が抱える高度化・複雑化する労働問題について、県内の中小企業事業主、労働者等の方を対象として、社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士による「専門労働相談」を2022年度から実施している。
この度、2023年9月の追加実施及び下半期の実施日時等が決定した。
労務管理や就業規則の見直し、職場のトラブル、メンタルヘルスなど、様々な労働問題について専門の相談員が相談を受け、解決に向けて助言をする。
ホームページ
出典:愛知県
県内の企業における2023年夏季一時金要求・妥結状況調査結果 愛知県 令和5年9月5日
県内企業の夏季一時金要求・妥結状況を県内労働情勢の一つとして調査し、その結果を取りまとめ、公表した。
・ 平均妥結額 :933,815円 【前年比】5,306円減 0.6%減
・ 平均妥結月数: 2.86か月 【前年比】0.04か月減
※前年と回答企業が一部異なるため、単純比較はできない。
(県内328社が回答:平均年齢39.4歳 基準内賃金326,061円)
○2023年の夏季一時金の平均妥結額は933,815円、平均妥結月数は2.86か月で、前年より額で5,306円、月数で0.04か月の減となった。
○「299人以下」の企業における平均妥結額は469,609円で、前年比25,946円の減。平均妥結月数は1.87か月で、前年比0.10か月の減となった。
注 )数値はいずれも加重平均(労働組合員1人当たりの平均)
ホームページ
出典:愛知県
愛知県最低賃金1,027円に引上げ 愛知労働局 令和5年9月1日
愛知労働局長(阿部 充)は、愛知県最低賃金を41円引上げ、時間額1,027円に改正することを決定し、令和5年9月1日、官報公示を行った。
愛知地方最低賃金審議会(会長 中山徳良)は、本年7月4日、愛知県最低賃金の改正決定に係る諮問を受け、同年8月4日、愛知労働局長に対し、現行の愛知県最低賃金時間額986円を41円引上げ、時間額1,027円に改正決定する旨の答申を行った。
この答申を受けて愛知労働局長は、異議申出などの所要の手続を行い、同年9月1日、官報公示を行った。
効力発生日は令和5年10月1日。
ホームページ
出典:愛知労働局
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年6月分)― 愛知県 令和5年8月31日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年6月分)―を公表した。
2023年6月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は288,134円となり、前年同月に比べ3.0%の増加(18か月連続)。
所定外労働時間は11.6時間となり、前年同月に比べ0.9%の増加(2か月連続)。
常用雇用指数は98.3(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ0.6%の減少(20か月連続)。
ホームページ
出典:愛知県
労働力調査(基本集計)2023年7月分公表 総務省統計局 令和5年8月29日
【就業者】
・就業者数は6772万人。前年同月に比べ17万人の増加。12か月連続の増加
・雇用者数は6085万人。前年同月に比べ33万人の増加。17か月連続の増加
・正規の職員・従業員数は3608万人。前年同月に 比べ1万人の減少。4か月ぶりの減少
非正規の職員・従業員数は2143万人。前年同月に比べ38万人の増加。2か月連続の増加
・主な産業別就業者を前年同月と比べると、 「医療,福祉」、「建設業」、 「卸売業,小売業」などが増加
【就業率】(就業者/15歳以上人口×100)
・就業率は61.4%。前年同月に比べ0.1ポイント の上昇
・15~64歳の就業率は79.1%。前年同月に比べ0.2ポイントの上昇
【完全失業者】
・完全失業者数は183万人。前年同月に比べ7万人の増加。3か月ぶりの増加
・求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が2万人の減少。 「自発的な離職(自己都合)」が前年同月と同数。「新たに求職」が2万人の増加
【完全失業率】(完全失業者/労働力人口×100)
・完全失業率(季節調整値)は2.7%前月に比べ0.2ポイントの上昇
【非労働力人口】
・非労働力人口は4065万人。前年同月に比べ 20万人の減少。17か月連続の減少
ホームページ
出典:総務省統計局
最近の雇用情勢(令和5年7月分) 愛知労働局 令和5年8月29日
愛知労働局は、最近の雇用情勢(令和5年月分)を公表した。
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.37倍(対前月比0.02ポイント増)
有効求人数(季節調整値)135,041人(対前月比1.5%減)
有効求職者数(季節調整値)98,784人(対前月比0.6%減)
・有効求人倍率は2か月連続で上昇
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値)2.40倍(対前月比0.23ポイント減)
新規求人数(季節調整値)45,214人(対前月比3.1%減)
新規求職者数(季節調整値)18,833人(対前月比3.0%増)
・新規求人倍率は3か月ぶりに低下
ホームページ
出典:愛知労働局
一般職業紹介状況(令和5年7月分) 厚生労働省 令和5年8月29日
厚生労働省では、令和5年7月分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
令和5年7月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月を0.01ポイント下回った。
新規求人倍率(季節調整値)は2.27倍となり、前月を0.05ポイント下回った。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.02倍となり、前月を0.01ポイント下回った。
7月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.0%増加となり、有効求職者(同)は0.9%増となった。
7月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると2.5%減少となった。
これを産業別にみると、情報通信業(5.2%増加)、宿泊業,飲食サービス業(2.1%増加)、学術研究,専門・技術サービス業(0.3%増加)で増加となり、製造業(11.4%減少)、建設業(8.0%減少)、生活関連サービス業,娯楽業(3.4%減少)などで減少となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
労働災害発生状況について(令和5年8月速報値) 厚生労働省 令和5年8月17日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年8月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数360人 (前年同期比 33人減少)
(2)業種別発生状況
製造業72人 (前年同期比 11人減少)
建設業104人 (前年同期比 35人減少)
林業16人 (前年同期比 0人増減なし)
陸上貨物運送事業52人 (前年同期比 12人増加)
第三次産業93人 (前年同期比 5人減少)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落94人 (前年同期比 18人減少)
交通事故(道路)70人 (前年同期比 16人増加)
はさまれ・巻き込まれ67人 (前年同期比 2人増加)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「転倒」及び「崩壊・倒壊」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和5年6月分結果確報 厚生労働省 令和5年8月25日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年6月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は461,811円(2.3%増)となった。うち一般労働者が625,995円(2.9%増)、パートタイム労働者が111,279円(1.7%増)となり、パートタイム労働者比率が32.01%(0.47ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は324,976円(1.7%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,265円(3.0%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は2.8%増となった。
うち一般労働者が3.0%増、パートタイム労働者が1.7%増となった。
・就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(前年同月と同水準)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
令和4年「雇用動向調査」の調査結果公表―入職率、離職率ともに上昇、入職超過率は拡大― 厚生労働省 令和5年8月22日
厚生労働省は、令和4年「雇用動向調査」の結果を取りまとめ、公表した。
(1)入職率、離職率及び入職超過率
入職率 15.2%(前年と比べて1.2ポイント上昇)
離職率 15.0%(前年と比べて1.1ポイント上昇)
入職超過率 0.2ポイント(入職超過)(前年と比べて0.1ポイント拡大)
(2)就業形態別入職率及び離職率
一般労働者 入職率11.8% 離職率11.9%
(前年と比べて入職率0.9ポイント上昇、離職率0.8ポイント上昇)
パートタイム労働者 入職率24.2% 離職率23.1%
(前年と比べて入職率2.2ポイント上昇、離職率1.8ポイント上昇)
(3)産業別入職率及び離職率
宿泊業,飲食サービス業 入職率34.6% 離職率26.8%で入職超過
(前年と比べて入職率10.8ポイント上昇、離職率1.2ポイント上昇)
生活関連サービス業,娯楽業 入職率23.2% 離職率18.7%で入職超過
(前年と比べて入職率5.4ポイント低下、離職率3.6ポイント低下)
ホームページ
出典:厚生労働省
仕事と介護・育児の両立支援セミナーの参加者募集―豊田商工会議所会場とオンラインのハイブリット開催― 愛知県 令和5年8月22日
愛知県では、仕事と介護・育児の両立支援セミナーの参加者を募集する。
貴重な人材が安心して長く働き続けるため、介護・育児との両立を支援することが求められている。
本セミナーでは、法改正のポイントはもちろん、男性育休や、仕事と介護の両立事例などを、介護支援プランの活用方法のほか、男性育休や育休復帰支援プラン・両立支援等助成金の紹介まで、幅広く解説する。
なお、特別企画として、”仕事と家庭の両立支援プランナー”による「無料個別相談」(豊田商工会議所会場での参加者限定(先着15社))も用意している。
【問合せ先】
愛知県西三河県民事務所 産業労働課 豊田加茂産業労働・山村振興グループ
電話:0565-32-7498(ダイヤルイン)
E-mail:nishimikawa@pref.aichi.lg.jp
ホームページ
出典:愛知県
人口推計(令和5年3月確定値、令和5年8月概算値) 総務省統計局 令和5年8月21日
総務省は、人口推計(令和5年3月確定値、令和5年8月概算値)を公表した。
【2023年(令和5年)8月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2454万人(前年同月比54万人減少)
【2023年(令和5年)3月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2456万7千人(前年同月比 53万5千人減少)
・15歳未満人口は1436万7千人(前年同月比 29万9千人減少)
・15~64歳人口は 7401万5千人(前年同月比 18万3千人減少)
・65歳以上人口は3618万5千人(前年同月比 5万3千人減少)
<日本人人口> 1億2163万1千人(前年同月比 81万3千人 減少)
ホームページ
出典:総務省統計局
あいちの人口 愛知県人口動向調査結果 月報(2023年7月1日現在) 愛知県 令和5年8月9日
愛知県は、愛知県人口動向調査結果 月報(2023年7月1日現在)を公表した。
7月1日現在の愛知県の人口は、7,481,863人(男 3,725,578人、女 3,756,285人)となり、前月に比べ854人減少(男782人減少、女 72人減少)し、前年同月に比べ21,843人の減少(男 12,442人減少、女 9,401人減少)となった。
社会増減(転入と転出の差に、その他の増減を加えたもの)
6月1か月間の転入数は 28,477人(男 15,834人、女 12,643人)、転出数は27,605人(男 15,639人、女11,966人)、その他の増(職権記載、転出取消等)は 480人、その他の減(職権消除等)は 563人で、789人の増加 (男109人増加、女 680人増加)となった.
ホームページ
出典:愛知県
最近の雇用情勢(令和5年6月分) 愛知労働局 令和5年8月1日
愛知労働局は、最近の雇用情勢(令和5年6月分)を公表した。
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.35倍(対前月比0.03ポイント増)
有効求人数(季節調整値)132,994人(対前月比3.8%減)
有効求職者数(季節調整値)98,216人(対前月比0.9%減)
・有効求人倍率は6か月ぶりに上昇
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値)2.63倍(対前月比0.04ポイント減)
新規求人数(季節調整値)46,662人(対前月比0.5%減)
新規求職者数(季節調整値)17,762人(対前月比2.1%減)
・新規求人倍率は2か月連続で上昇
ホームページ
出典:愛知労働局
一般職業紹介状況(令和5年6月分) 厚生労働省 令和5年8月1日
厚生労働省では、令和5年6月分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況を取りまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
令和5年6月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.30倍となり、前月を0.01ポイント下回った。
新規求人倍率(季節調整値)は2.32倍となり、前月を0.04ポイント下回った。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.03倍となり、前月と同水準となった。
6月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.0%減少となり、有効求職者(同)は0.6%増加となった。
6月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると2.1%増となった。
これを産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業(1.3%増加)、医療,福祉(0.9%増加)、学術研究,専門・技術サービス業(0.8%増加)で増加となり、製造業(11.0%減少)、建設業(7.2%減少)、教育,学習支援業(2.6%減少)で減少となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
労働力調査(基本集計) 2023年6月分公表 総務省統計局 令和5年8月1日
【就業者】
・就業者数は6785万人。前年同月に比べ26万人の増加。11か月連続の増加
・雇用者数は6109万人。前年同月に比べ61万人の増加。16か月連続の増加
・正規の職員・従業員数は3638万人。前年同月に比べ36万人の増加。3か月連続の増加。
非正規の職員・従業員数は2133万人。前年同月に比べ28万人の増加。3か月ぶりの増加
・主な産業別就業者を前年同月と比べると、「医療,福祉」、「宿泊業,飲食サービス業」、「建設業」などが増加
【就業率】(就業者/15歳以上人口×100)
・就業率は61.5%。前年同月に比べ0.2ポイントの上昇
・15~64歳の就業率は79.2%。前年同月に比べ0.5ポイントの上昇
【完全失業者】
・完全失業者数は179万人。前年同月に比べ7万人の減少。2か月連続の減少
・求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が2万人の減少。「自発的な離職(自己都合)」が1万人の減少。「新たに求職」が1万人の減少
【完全失業率】(完全失業者/労働力人口×100)
・完全失業率(季節調整値)は2.5%。前月に比べ0.1ポイントの低下
【非労働力人口】
・非労働力人口は4056万人。前年同月に比べ15万人の減少。16か月連続の減少
ホームページ
出典:総務省統計局
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年5月分)― 愛知県 令和5年7月31日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年5月分)―を公表した。
2023年5月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は286,469円となり、前年同月に比べ3.9%の増加(17か月連続)。
所定外労働時間は11.2時間となり、前年同月に比べ3.7%の増加(3か月ぶり)。
常用雇用指数は98.0(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ0.9%の減少(19か月連続)。
ホームページ
出典:愛知県
令和5年度地域別最低賃金改定の目安について 厚生労働省 令和5年7月28日
第 67 回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられた。
【答申のポイント】(ランクごとの目安)
各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク 41 円、Bランク 40 円、Cランク39 円。
都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで 28 道府県、Cランクで 13 県となっている。
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は 1,002 円となる。この場合、全国加重平均の上昇額は 41 円(昨年度は 31 円)となり、昭和 53 年度に
目安制度が始まって以降で最高額となる。また、引上げ率に換算すると 4.3%(昨年
度は 3.3%)となる。
ホームページ
出典:厚生労働省
人口推計(令和5年2月確定値、令和5年7月概算値) 総務省統計局 令和5年7月20日
総務省は、人口推計(令和5年2月確定値、令和5年7月概算値)を公表した。
【2023年(令和5年)7月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2456万人(前年同月比 56万人減少)
【2022年(令和5年)2月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2463万1千人(前年同月比 56万3千人減少)
・15歳未満人口は1439万5千人(前年同月比 29万4千人減少)
・15~64歳人口は 7405万6千人(前年同月比 20万8千人減少)
・65歳以上人口は3618万人(前年同月比 6万減少)
<日本人人口> 1億2172万1千人(前年同月比 80万8千人 減少)
ホームページ
出典:総務省統計局
毎月勤労統計調査 令和5年5月分結果確報 厚生労働省 令和5年7月25日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年5月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は284,998円(2.9%増)となった。うち一般労働者が370,009円(3.5%増)、パートタイム労働者が102,233円(3.5%増)となり、パートタイム労働者比率が31.81%(0.62ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は323,051円(2.0%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,268円(2.4%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は2.5%増となった。
うち一般労働者が2.7%増、パートタイム労働者が2.8%増となった。
・就業形態計の所定外労働時間は9.7時間(前年同月と同水準)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
労働災害発生状況について(令和5年7月速報値) 厚生労働省 令和5年7月18日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年7月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数302人 (前年同期比 20人減少)
(2)業種別発生状況
製造業59人 (前年同期比 14人減少)
建設業88人 (前年同期比 20人減少)
林業13人 (前年同期比 1人)
陸上貨物運送事業46人 (前年同期比 13人増加)
第三次産業77人 (前年同期比 6人減少)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落76人 (前年同期比 24人減少)
はさまれ・巻き込まれ64人 (前年同期比 9人増加)
交通事故(道路)62人 (前年同期比 21人増加)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「崩壊・倒壊」の順
ホームページ
出典:愛知県
中高年齢者再就職セミナー(第1回~第5回)の参加者募集 愛知県 令和5年7月14日
少子高齢化により人口が減少する中で、社会経済を維持していくためには、働く意欲のある方が年齢に関わりなく活躍できる生涯現役社会を目指すことが重要。
そこで愛知県では、今年度、「中高年齢者再就職セミナー」を全10回開催し、中高年齢者の早期再就職を支援する。本セミナーでは、講義形式で再就職に必要なノウハウを学ぶとともに、ロールプレイングを通して面接対策ができる。
【応募方法】
電話、FAX、メールいずれの申込方法の場合も、氏名、年齢、住所、連絡先を県委託事業者に伝える。なお、申込受付後に県事業委託先から申込宛てに申込完了メールを送信する。
【問合せ先】
・本事業の全体に関すること
愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話:052-954-6367(受付時間:平日(祝日を除く)午前8時45分から午後5時30分まで)
・セミナーの内容・申込みに関すること
中高年事業団やまて企業組合 名古屋支店(県委託事業者)
電話:052-585-0065(受付時間:平日(祝日を除く)午前8時45分から午後4時45分まで)
ホームページ
出典:愛知県
男性育児休業取得促進セミナー・ワークショップ(第1回~第3回)の参加者募集 愛知県 令和5年7月13日
男性の育児休業の取得を後押しする改正育児・介護休業法が2023年4月に全面施行され、企業には女性だけでなく男性も育児休業を取得しやすい職場環境の整備など、働き方の見直しが求められている。
そこで、愛知県では、法改正のポイントや企業に求められる取組について解説する講座とグループワークを組み合わせた普及啓発セミナー・ワークショップをオンライン併用で開催する。
【申込方法】
本事業事務局(県業務委託先)の申込専用Webフォームから申込みか、ちらしの申込欄に必要事項を記入の上、FAX(052-231-2029)にて申込み。
【問合せ先】
本事業事務局(県業務委託先:スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社)
メール:aichi_ikumen2023@starcat.co.jp
ホームページ
出典:愛知県
令和5年6月のテレワーク実施率調査結果 東京都 令和5年7月11日
東京都は、令和5年6月の都内企業のテレワーク実施状況について、調査を行い結果を公表した。
調査結果のポイント
都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は44.0%。5月の前回調査(44.0%)と同率。
テレワークを実施した社員の割合は35.8%と、前回(38.2%)に比べて、2.4ポイント減少。
テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が45.2%と、前回(42.4%)に比べて、2.8ポイント増加。
ホームページ
出典:愛知県
テレワーク・スクール(第1回・第2回)の参加者の募集開始 愛知県 令和5年7月11日
愛知県では、「あいちテレワークサポートセンター」を2021年4月に設置し、県内中小企業のテレワーク導入・定着に向けて、2023年度までの3年間で集中的な支援を行っている。
その一環として、中小企業の経営者や実務担当者を対象に、選ばれる企業になるためのDX時代の働き方や、電子インボイスを活用したテレワークでもスムーズな経理業務について学べる「テレワーク・スクール(第1回・第2回)」をオンラインと併用で開催する。
【申込方法】
セミナー受付専用サイトから申込み。
受付専用サイト:https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/seminar/
※申込後、県業務委託先からメールで受付完了を通知。申込多数の場合は、1社当たりの参加人数を制限することがある。
【問合せ先】
あいちテレワークサポートセンター(県業務委託先:株式会社パソナ)
電話:052-581-0510(受付時間:午前9時から午後5時まで、土日祝日・年末年始を除く)
メール:aichi-telework@pasona.co.jp
ホームページ
出典:愛知県
あいちの人口 愛知県人口動向調査結果 月報(2023年6月1日現在) 愛知県 令和5年7月10日
愛知県は、愛知県人口動向調査結果 月報(2023年6月1日現在)を公表した。
5月1日現在の愛知県の人口は、7,482,717人(男 3,726,360人、女 3,756,357人)となり、前月に比べ760人増加(男 573人増加、女 187人増加)し、前年同月に比べ20,016人の減少(男 11,309人減少、女 8,707人減少)となった。
社会増減(転入と転出の差に、その他の増減を加えたもの)
5月1か月間の転入数は 31,616人(男 17,958人、女 13,658人)、転出数は28,390人(男 15,904人、女12,486人)、その他の増(職権記載、転出取消等)は 459人、その他の減(職権消除等)は 779人で、2,906人の増加 (男 1,815人増加、女 1,091人増加)となった。
ホームページ
出典:愛知県
精神障害者雇用のための支援つき面接会の参加企業及び参加企業者を募集 愛知県 令和5年7月6日
愛知県では、精神障害のある方々の就職活動支援として、企業と求職者のマッチングの機会を促進するため、障害者を継続してサポートしている支援者が同席できる「精神障害者雇用のための支援つき面接会」を開催する。
今回は、企業・求職者への面接会開催前の「事前サポート」として、面接会参加企業には、面接対策セミナーを、求職者には、企業説明会や疑似面接を、支援者にはスキル向上セミナーを行う。
【申込方法】
・企業
8月18日(金曜日)までに申込み・問合せ先のWebページから申し込み。
参加決定後、個別に日程調整のうえ、求人票提出についての資料配布と、打合せを行う。打合せ終了後、9月20日(水曜日)までにハローワークに求人票を提出。
・求職者
参加企業の求人票をまとめた冊子を、10月4日(水曜日)から、申込み・問合せ先のWebページに公開。
参加希望者は、11月7日(火曜日)までに、同Webページから参加申込み。
【申込み・問合せ先】
あいち障害者雇用サポートデスク(県業務委託先:Man to Man Animo株式会社)
電話:052-583-1010
FAX:052-583-1011
ホームページ
出典:愛知県
「先端技術セミナー ゼロから学ぶ生成AI」の参加者を募集 愛知県 令和5年7月5日
昨今、ChatGPT等の生成AIが注目され、企業における業務への活用が期待される一方で、利用においては生成AIへの過度な依存、著作権侵害、回答の正確性や情報漏えいといった課題が懸念されている。
こうした状況を踏まえ、愛知県では、生成AIの概要、企業での活用事例及びリスク対策等について、企業支援の専門家が分かりやすく解説する「先端技術セミナー ゼロから学ぶ生成AI」を開催する。
また、愛知県では、生成AI等の「AI技術の活用」を活動テーマとしてワーキンググループ活動を実施するDXチャレンジ促進事業を実施する。
【申込方法】
・申込みWebサイトから申込み。
・申込完了後、申込者へ受付完了メールを送付。
・7月24日(月曜日)までに、申込者へWeb会議用URLをメールにて送付。
・当申込WebサイトからDXチャレンジ促進事業の事業説明会も申し込むことが可能。
【問合わせ先】
<本事業に関すること>
愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室 デジタル技術活用促進グループ
電話:052-954-7495 FAX:052-954-6943
E-mail:jisedai@pref.aichi.lg.jp
<申込み・セミナー内容に関すること>(県事業委託先)
有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所
住所:愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋37階
電話:052-565-5955
ホームページ
出典:愛知県
働き方改革の講師派遣を希望する企業等を募集~愛知県働き方改革支援事業「働き方改革サポートセミナー」~ 愛知県 令和5年7月4日
愛知県では、中小企業等における「働き方改革」の取組を着実に進めていくため、働き方改革に造詣が深い講師の派遣を希望する企業等を募集する。
専門の講師が申込団体・企業のニーズに合わせた講義(「働き方改革サポートセミナー」)を行う。
【申込方法】
県業務委託先(特定非営利活動法人ブルーバード)の申込フォームにて申込か、ちらし裏面の参加申込書に必要事項を記入の上、FAX(0565-50-2099)にて申込み。申込後、県業務委託先から受付完了をメールで通知。
【申込み・問合せ先】
・講師派遣の申込み・内容に関すること
働き方改革支援事業事務局(県業務委託先:特定非営利活動法人ブルーバード)
電話: 0565-77-6910(月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前9時から午後5時まで)
FAX:0565-50-2099、メール:info@bluebird.or.jp
・事業全般に関すること
愛知県労働局労働福祉課労使関係グループ
電話:052-954-6361(月曜日から金曜日まで(祝日を除く)午前8時45分から午後5時30分まで)
メール:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
ホームページ
出典:愛知県
労働力調査(基本集計) 2023年度5月分 総務省統計局 令和5年6月30日
総務省統計局は、労働力調査(基本集計)2023年5月分を公表した。
就業者数は6745万人。前年同月に比べ15万人の増加。10か月連続の増加
完全失業者数は188万人。前年同月に比べ3万人の減少。3か月ぶりの減少
完全失業率(季節調整値)は2.6%。前月と同率
ホームページ
出典:総務省統計局
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年4月分)― 愛知県 令和5年6月30日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年4月分)―を公表した。
2023年4月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は290,487円となり、前年同月に比べ2.1%の増加(16か月連続)。
所定外労働時間は12.4時間となり、前年同月と同水準。
常用雇用指数は97.8(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ1.4%の減少(18か月連続)。
ホームページ
出典:愛知県
一般職業紹介状況(令和5年5月分) 厚生労働省 令和5年6月30日
厚生労働省では、令和5年5月分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況を取りまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
令和5年5月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.31倍となり、前月を0.01ポイント下回った。
新規求人倍率(季節調整値)は2.36倍となり、前月を0.13ポイント上回った。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.03倍となり、前月と同水準となった。
5月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.7%減少となり、有効求職者(同)は0.1%増加となった。
5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると3.8%増となった。
これを産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業(13.5%増加)、教育,学習支援業(12.0%増加)、サービス業(他に分類されないもの)(5.7%増加)などで増加となり、製造業(5.4%減少)、建設業(0.8%減少)で減少となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
有給休暇の取得促進に取り組む中小企業等を奨励する「愛知県休み方改革マイスター企業認定制度」の申請受付を開始 愛知県 令和5年6月26日
愛知県では、ワーク・ライフ・バランスの充実と生産性向上による地域経済の活性化を目指し、経済界・労働界・教育界とともに、愛知県「休み方改革」プロジェクトに取り組んでいる。
このプロジェクトの一環として、年次有給休暇の取得及び多様な特別休暇の導入を積極的に推進している中小企業等を奨励する「愛知県休み方改革マイスター企業認定制度」を創設した。
この度、ハローワークの求人票への認定企業の表示や、建設工事の入札参加資格審査における優遇、制度融資の利用など、企業活動を後押しする様々な優遇措置を受けることができる「愛知県休み方改革マイスター企業」の認定申請の受付を7月3日(月曜日)から開始する。
【申請方法】
愛知県休み方改革マイスター企業認定制度ポータルサイト「あいちYOU休(ゆうきゅう)ナビ」にて申請
【問合せ先】
愛知県労働局労働福祉課 労使関係グループ
電話:052-954-6361
メール: rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
ホームページ
出典:愛知県
毎月勤労統計調査 令和5年4月分結果確報 厚生労働省 令和5年6月23日
厚生労働省は、毎月勤労統計調査(令和5年4月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は284,595円(前年同月比 0.8%増加)となった。うち一般労働者が369,615円(同1.3%増加)、パートタイム労働者が103,278円(同 2.0%増加)となり、パートタイム労働者比率が31.67%(同 0.49ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は325,506円(同 1.4%増加)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,261円(同 2.3%増加)となった。
・共通事業所による現金給与総額は同 1.9%増加となった。
うち一般労働者が2.0%増加、パートタイム労働者が同 1.8%増加となった。
・就業形態計の所定外労働時間は10.5時間(同 1.9%減少)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
令和5年5月のテレワーク実施率調査結果 東京都 令和5年6月22日
東京都は、令和5年5月の都内企業のテレワーク実施状況について、調査を行い結果を公表した。
調査結果のポイント
都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は44.0%。4月の前回調査(46.7%)に比べて2.7ポイント減少。
テレワークを実施した社員の割合は38.2%と、前回(42.0%)に比べて、3.8ポイント減少。
テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が42.4%と、前回(41.5%)に比べて、0.9ポイント増加。
ホームページ
出典:東京都
高年齢者就職相談・面接会(第1回~第3回)の参加企業を募集 愛知県 令和5年6月21日
愛知県では、高年齢者の就業促進に取り組む豊橋市、豊田市、小牧市と連携し、長年培った経験や能力を活かすことを望む高年齢者と、高年齢者の就業機会の選択肢を整える企業とのマッチングの機会を提供するため、高年齢者を対象とした就職相談・面接会を開催する。
今回は、全6回開催のうち、2023年8月から11月までの間に開催する、第1回から第3回までの面接会について、参加企業を募集する。
【申込方法】
「高年齢者就職相談会企業参加申込書」をダウンロードし、中高年事業団やまて企業組合(県委託事業者)へFAX又はメールより提出
FAX:052-585-0900
メール:nagoya@yamate-kigyo.jp
【問合せ先】
・本事業の全般に関すること
愛知県労働局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ 電話 052-954-6367
・高年齢者就職相談会の内容に関すること
中高年事業団やまて企業組合(県委託事業者) 電話 052-585-0065
ホームページ
出典:愛知県
職場のメンタルヘルス対策セミナーの参加者を募集 愛知県 令和5年6月21日
愛知県では、メンタルヘルス対策の重要性の啓発し、企業における取組を促進させるため、中小企業の経営者や人事労務担当者の方を主な対象とする「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催する。
今回のセミナーでは、「効果的な社内体制づくりのポイント」と「ラインケアの基礎知識と実践のポイント」という2つのテーマで、各テーマ2回ずつ(計4回)開催する。
【申込方法】
あいち電子申請・届出システムから申込みか、受講申込書に必要事項を記入のうえ、各締切日(開催の1週間前)までに申込み先へ、FAX又は郵送で申し込み
【問合せ先】
愛知県労働局労働福祉課 調査・啓発グループ
電話052-954-6359 メール rodofukushi@pref.aichi.lg.jp
ホームページ
出典:愛知県
「愛知自動車サプライヤー BUSINESS CREATION」事業創出セミナーの参加者を募集 愛知県 令和5年6月20日
愛知県では、サプライヤーを対象に、新規事業の創出に向けた具体的な行動を促すためのプログラム「愛知自動車サプライヤーBUSINESS CREATION」を実施する。
当プログラムでは、サプライヤーの新規事業創出に向けた検討フェーズに応じたハンズオン支援として、他社との協業を前提とした新事業創出を目指す「オープンイノベーション推進プログラム」、自社の強みを活かしながら自社単独で新事業開発の深化を目指す「新事業展開プログラム」の2つのコースを用意する。
このプログラムの開始に先立ち、新事業開発の基本的な知識を習得するため、「事業創出セミナー」を開催する。その後、2つのコースにより事業計画の策定までを一気通貫で支援する。
【申込方法】
株式会社eiicon(業務委託先)の応募用Webページ内の応募フォームから申込み
【問合せ先】
・プログラムの申込・参加に関すること(業務委託先)
株式会社eiicon
電話 070-1578-5513 メール aichi-carsupply@eiicon.net
・上記以外のことに関すること
愛知県経済産業局産業部産業振興課自動車グループ
電話 070-1578-5513 メール sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp
ホームページ
出典:愛知県
労働災害発生状況について(令和5年6月速報値) 厚生労働省 令和5年6月19日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年6月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数244人 (前年同期比 30人減少)
(2)業種別発生状況
製造業51人 (前年同期比 11人減少)
建設業71人 (前年同期比 25人減少)
林業12人 (前年同期比 0人)
陸上貨物運送事業37人 (前年同期比 8人増加)
第三次産業57人 (前年同期比 10人減少)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落60人 (前年同期比 28人減少)
はさまれ・巻き込まれ54人 (前年同期比 9人増加)
交通事故(道路)48人 (前年同期比 12人増加)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「崩壊・倒壊」、「転倒」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
【あいち就職支援プロジェクト】「採用戦略支援塾」及び「あいち合同企業説明会」の参加企業の募集を開始 愛知県 令和5年6月14日
愛知県では、就職活動に臨む求職者の視野を広げ、人手不足業界への就職につなげることにより、求職者と企業の双方を支援し、中小企業の人材確保を図るため、今年度新たに「あいち就職支援プロジェクト」を実施する。
このプロジェクトでは、人手不足が顕著な業種の中小企業に対し、採用活動を支援するための「採用戦略支援塾」を実施する。また、採用戦略支援塾の参加企業及びあらゆる業種の中小企業に対し、求職者とのマッチングを図る「あいち合同企業説明会」を実施する。
【申込方法】
事業特設Webサイトの申込フォームから申込み
事業特設サイト:https://www.zinzai-kikaku.jp/aichi-jobfair23/aichi-company/
【問合せ先】
・あいち就職支援プロジェクト全般に関すること
愛知県労働局就業促進課 若年者雇用対策グループ 電話052-954-6366
・各イベントの内容及び申込に関すること
株式会社人財企画 企画事業推進部 電話052-228-0084
ホームページ
出典:愛知県
「知的財産セミナー」の参加者募集 愛知県 令和5年6月13日
愛知県では、経営戦略に知的財産を組み込み活用する「知的経営」を中小企業等に広く普及・啓発するため「知的財産セミナー」を実施する。
このセミナーでは、商標の出願や活用などの基礎的な内容の講演を、経験豊かな講師が講演する。
申込方法:専用フォームから申込みか、ちらし裏面の参加必要申込書に必要事項を記載の上、FAXで申込み。
申込期限:7月18日(火曜) ※定員に達し次第、受付終了
問合せ先:愛知県経済産業局産業部産業科学技術課
研究開発支援グループ
電話:052-954-6370
FAX:052-954-6977
ホームページ
出典:愛知県
あいちの人口 愛知県人口動向調査結果 月報(2023年5月1日現在) 愛知県 令和5年6月9日
愛知県は、愛知県人口動向調査結果 月報(2023年5月1日現在)を公表した。
5月1日現在の愛知県の人口は、7,481,957人(男 3,725,787人、女 3,756,170人)となり、前月に比べ6,327人増加(男 4,023人増加、女 2,304人増加)し、前年同月に比べ15,071人の減少(男 8,438人減少、女 6,633人減少)となった。
社会増減(転入と転出の差に、その他の増減を加えたもの)
4月1か月間の転入数は 43,708人(男 24,920人、女 18,788人)、転出数は 34,836人(男 19,379人、女 15,457人)、その他の増(職権記載、転出取消等)は 524人、その他の減(職権消除等)は 718人で、8,678人の増加 (男 5,389人増加、女 3,289人増加)となった。
ホームページ
出典:愛知県
令和5年度「輝くテレワーク賞」の募集を開始~募集期間は6月6日~7月31日、テレワーク推進企業などを厚生労働大臣が表彰~ 厚生労働省 令和5年6月6日
厚生労働省では、令和5年度の「輝くテレワーク賞」の募集を開始する。
「輝くテレワーク賞」とは、テレワークの活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、他社の模範となる取組を行っている企業や団体を厚生労働大臣が表彰するもの。
テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、子育てや介護と仕事の両立など、ワーク・ライフ・バランスの向上に役立つほか、業務効率化による生産性の向上や人材の確保につながるなど、労使双方にメリットがある働き方。
募集期間:令和5年6月6日(火)~7月31日(月)(応募締切:7月31日(月)必着)
応募方法:専用ホームページにおいて募集要項を確認のうえ、必要事項を入力し応募。
「輝くテレワーク賞」特設サイト:https://kagayakutelework.jp/award/
お問い合わせ先:「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰」事務局
〒 164-0001 東京都中野区中野4-11-10アーバンネット中野ビル1F
株式会社東京リーガルマインド内
電話:0120-260-090(受付時間:9時~17時/土・日曜、祝日を除く)
URL:https//kagayakutelework.jp
E-mail:telework_sodan@lec.co.jp
ホームページ
出典:厚生労働省
労働協約の地域的拡張適用について 茨城県 令和5年6月1日
茨城県は、労働組合法第18条に基づき、労働協約の地域的拡張適用について、茨城県知事に申立てがあり、令和5年6月1日付けで茨城県知事が労働協約の拡張適用を決定した。
このことから、令和5年6月1日から令和7年5月31日までの間、以下の内容の労働協約が茨城県内全域に拡張適用される。
適用される労働者:「大型家電量販店」に雇用される「無期雇用フルタイム労働者」
適用される労働協約の内容
適用される労働者のうち、1日の所定労働時間が7時間45分を超える労働者の、各年度に付与される所定休日数の最低日数を111日以上とすること。
適用される労働者のうち、1日の所定労働時間が7時間以上7時間45分以下の労働者の、各年度に付与される所定休日数の最低日数を107日以上とすること。等
ホームページ
出典:茨城県
令和4年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表 厚生労働省 令和5年5月29日
―暑さ指数(WBGT)の把握、労働衛生教育の実施し、発症時・緊急時の措置を徹底―
厚生労働省では、令和4年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめ、公表した。
令和4年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、827人(前年比266人・47%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生している。
また、熱中症による死亡者数は30人(前年比10人・50%増)であり、建設業(14人)や警備業(6人)で多く発生している。死亡災害には、多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、熱中症予防のための労働衛生教育を行っていなかった。また、「休ませて様子を見ていたところ容態が急変した」、「倒れているところを発見された」など、熱中症発症時・緊急時の措置が適切になされていなかった。
ホームページ
出典:厚生労働省
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調結果査(2023年3月分)― 愛知県 令和5年5月31日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果(2023年3月分)―を公表した。
2023年3月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は、285,071円となり、前年同月に比べ1.5%の増加(15か月連続)
所定外労働時間は、12.1時間となり、前年同月に比べ3.2%の減少(2か月ぶり)
常用雇用指数は、96.6(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ1.4%の減少(17か月連続)
ホームページ
出典:愛知県
最近の雇用情勢(令和5年4月分) 愛知労働局 令和5年5月30日
愛知労働局は、最近の雇用情勢(令和5年4月分)を公表した。
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.32倍(対前月比0.02ポイント減)
有効求人数(季節調整値)128,267人(対前月比2.5%減)
有効求職者数(季節調整値)97,246人(対前月比0.7%減)
・有効求人倍率は4か月連続で低下
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値)2.18倍(対前月比0.08ポイント減)
新規求人数(季節調整値)42,232人(対前月比0.0%増)
新規求職者数(季節調整値)19,382人(対前月比3.9%増)
・新規求人倍率は3か月連続で低下
ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001472022.pdf
一般職業紹介状況(令和5年4月分) 厚生労働省 令和5年5月30日
厚生労働省では、令和5年4月分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
・令和5年4月の有効求人倍率は1.32倍で、前月と同水準。
・令和5年4月の新規求人倍率は2.23倍で、前月に比べて0.06ポイント低下。
これを産業別でみると、宿泊業,飲食サービス業(8.2%増)、情報通信業(7.5%増)、学術研究,専門・技術サービス業(3.3%増)などで増加となり、建設業(9.6%減)、製造業(9.3%減)、生活関連サービス業,娯楽業(1.3%減)などで減少となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
2023年度愛知ブランド企業の募集について ~集まれ!キラリと光る愛知のモノづくり企業~ 愛知県 令和5年5月29日
愛知県では、県内製造業の実力を広くアピールするため、オンリーワンやトップシェアなど、世界に誇る独自の技術や製品を持つ優れたモノづくり企業を「愛知ブランド企業」として認定している(2003年度から認定を開始し、現在404社を認定)。
この度、新たに「愛知ブランド企業」として認定を希望する企業の募集を開始した。
申込方法:「あいち電子申請・届出システム」から申請
申込URL【https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=74783】
問合せ先: 愛知県経済産業局産業部産業振興課
基盤産業グループ
電話:052-954-6345
メール:a-brand@pref.aichi.lg.jp
ホームページ
出典:愛知県
令和5年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)公表 厚生労働省 令和5年5月26日
厚生労働省と文部科学省は、令和5年3月大学等卒業者の就職状況を共同で調査し、令和5年4月1日現在の状況を取りまとめ、公表した。
【就職率の概要】
大学(学部)は97.3%(前年同期差1.5ポイント増)
短期大学は98.1%(同0.3ポイントポイント増)
大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では97.5%(同1.4ポイント増)
大学等に専修学校(専門課程)を含めると97.3%(同1.3ポイント増)
ホームページ
出典:厚生労働省
愛知県「休み方改革」イニシアチブ賛同企業・団体及び「あいちスキ旅キャンペーン」参画事業者の募集を開始 愛知県 令和5年5月25日
愛知県では、ワーク・ライフ・バランスの充実と生産性向上による地域経済の活性化を目指し、経済界、労働界、教育界とともに、愛知県「休み方改革」プロジェクトに取り組んでいる。
この度、プロジェクトに共に取り組む、愛知県「休み方改革」イニシアチブ賛同企業・団体の募集を開始する。
また、このプロジェクトの一つである、平日や閑散期への観光需要のシフトを狙った、「あいちスキ旅キャンペーン」参画事業者も同時に募集する。
受付方法:愛知県「休み方改革」プロジェクト特設サイトにて受付
問合せ先:愛知県観光コンベンション局観光振興課企画グループ
電話:052-954-6353
メール:kanko@pref.aichi.lg.jp
ホームページ
出典:愛知県
毎月勤労統計調査 令和5年3月分結果確報 厚生労働省 令和5年5月23日
厚生労働省は、5月23日付で毎月勤労統計調査(令和5年3月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は292,546円(前年同月比 1.3%増加)となった。うち一般労働者が383,016円(同2.1%増加)、パートタイム労働者が102,388円(同 3.4%増加)となり、パートタイム労働者比率が32.20%(同 0.88ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は322,113円(同 1.1%増加)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,254円(同 1.2%増加)となった。
・共通事業所による現金給与総額は同 2.4%増加となった。
うち一般労働者が2.4%増、パートタイム労働者が同 3.0%増加となった。
・就業形態計の所定外労働時間は10.5時間(同 1.0%増加)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
人口推計(令和4年12月確定値、令和5年5月概算値) 総務省 令和5年5月22日
総務省は、人口推計(令和4年12月確定値、令和5年5月概算値)を公表した。
【2023年(令和5年)5月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2450万人(前年同月比 57万人減少)
【2022年(令和4年)12月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2486万1千人(前年同月比 51万9千人減少)
・15歳未満人口は1444万9千人(前年同月比 29万3千人減少)
・15~64歳人口は 7420万2千人(前年同月比 20万8千人減少)
・65歳以上人口は3620万9千人(前年同月比 1万8千人減少)
<日本人人口> 1億2190万1千人(前年同月比 77万3千人 減少)
ホームページ
出典:総務省
「介護に関する入門的研修」の参加者募集―あいち介護サポーターバンク運営事業― 愛知県 令和5年5月19日
愛知県では、介護分野への多様な人材の参入を促進するため、介護事業所において洗濯、配膳やレクリエーションの手伝い等を行う「あいち介護サポーター」を人材バンクに登録し、各事業所からの依頼に基づきマッチングを行う「あいち介護サポーターバンク運営事業」を2016年度から実施している。
このたび、「あいち介護サポーター」として登録するための、「介護に関する入門的研修」の募集を開始した。研修は、介護未経験でも受講しやすく、かつ基本的な実技等も含めた充実した内容となっている。
申込期限:各講座の受講日7日前まで(必着)
申込方法・問合せ先:
(1)Web申込みの場合
Webサイト[https://aichi-kaigo.dg-1.jp/]から応募。
(2)郵送又はFAXの場合
受講申込書(募集チラシ裏面)をダウンロードし、以下の申込先まで送付。
募集チラシ[https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/461750.pdf]
申込先・問合せ先:〒450-6046 名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ46階
株式会社パソナ あいち介護サポーターバンク運営事務局(県委託先)
電話 0800-200-4415(フリーダイヤル)/052-564-5763(IP番号の場合)(平日午前9時から午後5時45分まで)
FAX 0800-200-9915(フリーダイヤル)/052-564-5764(コンビニ、IP電話の場合)(24時間対応)
ホームページ
出典:愛知県
労働災害発生状況について(令和5年5月速報値) 厚生労働省 令和5年5月18日
厚生労働省は、労働災害発生状況(令和5年5月速報値)を公表した。
死亡災害の発生状況
(1)全体
死亡者数 188 人 (前年同期比 39人減少)
(2)業種別発生状況
製造業 37 人 (前年同期比 15人減少)
建設業 55 人 (前年同期比 19人減少)
林業 9 人 (前年同期比 0人)
陸上貨物運送事業 35 人 (前年同期比 11人増加)
第三次産業 40 人 (前年同期比 19人減少)
(3)事故の型別発生状況
墜落・転落 46 人 (前年同期比 26人減少)
はさまれ・巻き込まれ 44 人 (前年同期比 9人増加)
交通事故(道路) 34 人 (前年同期比 3人増加)
※以下、「激突され」、「飛来・落下」、「崩壊・倒壊」および「転倒」の順
ホームページ
出典:厚生労働省
第12回「21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児)」の結果を公表 厚生労働省 令和5年5月17日
厚生労働省では、同じ集団を対象に毎年実施している「21 世紀出生児縦断調査(平成 22 年 出生児)」の第 12 回(令和4年)の結果を取りまとめ、公表した。 21 世紀出生児縦断調査は、21 世紀の初年である平成 13 年に出生した子を継続的に観察している調査と 平成 22 年に出生した子の比較対照等を行うことにより、少子化対策などの施策のための基礎資料を得ることを目的としている。
【調査結果のポイント】
1 母の就業状況の変化
・母が有職の割合は第 12 回調査(小学6年生)で 81.0%となり、平成 13 年出生児(第 12 回)の 73.7%に比べて 7.3 ポイント高い
・出産1年前の就業状況が「勤め(常勤)」の母のうち、第1回調査から第 12 回調査まで継続して「勤め(常勤)」の母の割合は、平成 22 年出生児では 34.5%で、平成 13 年出生児の 24.9%に比べて9.6 ポイント高い
2 子どもの生活の状況
(1)学校生活のようす
学校生活のようすをみると、平成 13 年出生児と同様、「友だちに会うことが楽しい」が約9割、「行事(遠足、運動会など)が楽しい」が約8割となっている
(2)この1年間の学校行事以外の体験
この1年間に学校行事以外の体験を1回以上した割合は、おおむね前回(第 11 回)調査に比べて上昇している
(3)子どもの手伝いの状況
・子どもが手伝いする割合は、男児・女児ともに「部屋やお風呂などの掃除をする」「洗たく物を干したり、たたむ」の順に高い
・母が「有職」の場合、「洗たく物を干したり、たたむ」「お米をといだり、料理を作るのを手伝う」等の割合が、「無職」の場合よりも高い
・父の家事の状況が「よくする」「ときどきする」の方が、「ほとんどしない・まったくしない」場合よりも高くなっている手伝いが多い
ホームページ
出典:厚生労働省
令和5年4月のテレワーク実施率調査結果 東京都 令和5年5月15日
東京都は、令和5年4月の都内企業のテレワーク実施状況について、調査を行い結果を公表した。
調査結果のポイント
都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は46.7%。3月の前回調査(51.6%)に比べて4.9ポイント減少。
テレワークを実施した社員の割合は42.0%と、前回(40.0%)に比べて、2.0ポイント増加。
テレワークの実施回数は、週3日以上の実施が41.5%と、前回(43.8%)に比べて、2.3ポイント減少。
ホームページ
出典:東京都
我が国のこどもの数―「こどもの日」にちなんで―(「人口推計」から) 総務省 令和5年5月4日
総務省統計局では、5月5日の「こどもの日」にちなんで、2023年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口)を推計した。2023年4月1日現在におけるこどもの数(15歳未満人口。以下同じ。)は、前年に比べ30万人少ない1435万人で、1982年から42年連続の減少となり、過去最少となった。
男女別では、男子が735万人、女子が700万人となっており、男子が女子より35万人多く、女子100人に対する男子の数(人口性比)は105.0となっている。
ホームページ
出典:総務省
最近の雇用情勢(令和5年3月分及び令和4年度分) 愛知労働局 令和5年4月28日
愛知労働局は、令和5年3月分及び令和4年度分の最近の雇用情勢を公表した。
「雇用情勢は、持ち直しの動きが広がりつつあるが、一部に改善の動きが弱まっており、引き続き注意する必要がある」としている。
[令和5年3月分]
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(季節調整値)1.34倍(対前月比 0.06ポイント減)
有効求人数 (季節調整値) 131,617人(対前月比 3.1 %減)
有効求職者数(季節調整値) 97,885人(対前月比 0.6 %増)
・有効求人倍率は3か月連続で低下
〇新規求人・求職の状況
新規求人倍率(季節調整値) 2.26倍(対前月比 0.20ポイント減)
新規求人数 (季節調整値) 42,219人(対前月比 9.9 %減)
新規求職者数(季節調整値) 18,663人(対前月比 1.8 %減)
・新規求人倍率は2か月連続で低下
[令和4年度分]
〇有効求人・求職の状況
有効求人倍率(原数値・年度平均)1.39倍(対前年比 0.16ポイント増)
有効求人数 (原数値・年度平均)135,845人(対前年比 7.9 %増)
有効求職者数(原数値・年度平均)97,698人(対前年比 4.4 %減)
ホームページ
出典:愛知労働局
一般職業紹介状況(令和5年3月分及び令和4年度分) 厚生労働省 令和5年4月28日
厚生労働省は、令和5年3月分及び令和4年度分の公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
・令和5年3月の有効求人倍率は1.32倍で、前月に比べて0.02ポイント低下。
・令和5年3月の新規求人倍率は2.29倍で、前月に比べて0.03ポイント低下。
・令和4年度平均の有効求人倍率は1.31倍で、前年度に比べて0.15ポイント上昇。
・都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.89倍、最低は神奈川県の1.09倍、受理地別では、最高は福井県の1.78倍、最低は神奈川県の0.90倍となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果―(2023年2月分) 愛知県 令和5年4月28日
愛知県は、あいちの勤労―毎月勤労統計調査地方調査結果―(2023年2月分)を公表した。
2023年2月分の調査産業計、事業所規模5人以上でみると
きまって支給する給与は281,718円となり、前年同月に比べ1.6%の増加(14か月連続)
所定外労働時間は11.6時間となり、前年同月に比べ1.8%の増加(3か月ぶり)
常用雇用指数は97.0(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ1.3%の減少(16か月連続)
ホームページ
出典:愛知県
労働力調査令和5年3月分公表 総務省 令和5年4月28日
総務省は、令和5年4月28日付で労働力調査令和5年3月分結果を公表した。
就業者数は6699万人。前年同月に比べて15万人の増加。8か月連続の増加
就業率は60.8%。前年同月に比べ0.3ポイントの上昇
完全失業者数は193万人。前年同月に比べ13万人の増加。21か月ぶりの増加
完全失業率は(季節調整値)は2.8%。前月に比べ0.2ポイントの上昇
ホームページ
出典:総務省
令和5年3月新規高等学校卒業者の職業紹介状況 愛知労働局 令和5年4月27日
愛知労働局は、令和5年3月新規高等学校卒業者の職業紹介状況を発表した。
新規高等学校卒業者の就職決定率は99.8%となり、前年と同一水準を確保した。
新規高等学校卒業者(令和4年9月16日選考開始)
・求人数 34,719人(対前年比 13.9%増加)
・就職希望者数 9,076人(対前年比 6.7%減少)
・求人倍率 3.83倍(対前年差 0.7ポイント上昇)
・就職決定者数 9,057人(対前年比 6.7%減少)
・就職決定率 99.8%(対前年差 同一)
・就職未決定者数 19人(対前年差 4人減少)
新規中学校卒業者(令和5年1月25日選考開始)
・求人数 386人(対前年比 7.0%減少)
・就職希望者数 128人(対前年比 10.3%増加)
・求人倍率 3.02倍(対前年差 0.56ポイント低下)
・就職決定者数 128人(対前年比 10.3%増加)
・就職決定率 100.0%(対前年差 同一)
・就職未決定者数 0人(対前年差 同一)
ホームページ
出典:厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果確報 厚生労働省 令和5年4月21日
厚生労働省は4月21日付で毎月勤労統計調査(令和5年2月分結果確報)をとりまとめ公表した。
・現金給与総額は271,143円(0.8%増)となった。
うち一般労働者が352,823円(1.2%増)、パートタイム労働者が99,137円(4.0%増)となり、パートタイム労働者比率が32.22%(0.87ポイント上昇)。
なお、一般労働者の所定内給与は319,508円(1.2%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,267円(1.1%増)。
・共通事業所による現金給与総額は1.9%増となった。
うち一般労働者が1.7%増、パートタイム労働者が3.9%増。
・就業形態計の所定外労働時間は10.0時間(2.1%増)となった。
(前年同月と比較して)
ホームページ
出典:厚生労働省
人口推計―令和4年11月確定値、令和5年4月概算値― 総務省 令和5年4月20日
【令和5年4月1日現在(概算値)】
<総人口> 1億2447万人で、前年同月に比べ減少 ▲60万人(▲0.48%)
【令和4年11月1日現在(確定値)】
<総人口> 1億2491万3千人で、前年同月に比べ減少 ▲53万1千人 (▲0.42%)
・15歳未満人口は1447万4千人で、前年同月に比べ減少 ▲28万8千人 (▲1.95%)
・15~64歳人口は 7421万4千人で、前年同月に比べ減少 ▲24万4千人 (▲0.33%)
・65歳以上人口は3622万5千人で、前年同月に比べ増加 1千人( 0.00%)
<日本人人口> 1億2196万9千人で、前年同月に比べ減少 ▲75万9千人 (▲0.62%)
ホームページ
出典:総務省
2023年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業を募集 愛知県 令和5年4月17日
愛知県では、仕事と生活の調和を図ることができる職場環境づくりに積極的に取り組む企業を「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」として登録する制度を2007年度から運用している。
また、登録企業の中から、他の模範となる優れた取組を実施している企業を、毎年度、知事が表彰している。
この度、2023年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰の候補企業の募集を開始した。
応募資格:愛知県ファミリー・フレンドリー企業として登録している企業等のうち、
県内に本社を置く企業等
募集期間:2023年6月23日(金)(必着)※持参の場合は午後5時30分まで
問合せ先:愛知県労働局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
電話 052-954-6360
ホームページ
出典:愛知県
令和5年度「全国安全週間」を7月に実施 厚生労働省 令和5年4月4日
令和5年度の「全国安全週間」スローガン
「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」
厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施する。
今年で96回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としている。
厚生労働省では、7月1日(土)から7日(金)までを「全国安全週間」、6月1日(木)から30日(金)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施する。
ホームページ
出典:厚生労働省
「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを更新 厚生労働省 令和5年4月11日
厚生労働省は、令和4年10月28日に策定した「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージについて、昨年度末に令和5年度政府予算案が国会で成立したことを踏まえて更新した。
本パッケージにより、意欲と能力に応じた「多様な働き方」を可能とし、「賃金上昇」の好循環を実現していくため、中長期も見据えた雇用政策に力点を移し、これまでの「賃上げ支援」に加えて、「人材の育成・活性化を通じた賃上げ促進」「賃金上昇を伴う円滑な労働移動の支援」「雇用セーフティネットの再整備」の一体的、継続的な取組を引き続き推進していく。この一体的、継続的な取組を通じて、経済変化に柔軟で、個人の多様な選択を支える「しなやかな労働市場」を実現し、人材の活性化と生産性の向上を通じた賃金上昇のサイクルを目指すとしている。
ホームページ
出典:厚生労働省
労働協約の地域的拡張適用について厚生労働大臣が決定した事案―青森県、岩手県及び秋田県の全域が適用対象地域に― 厚生労働省 令和5年4月11日
秋田県の全域が適用対象地域に― 厚生労働省 令和5年4月11日
厚生労働省は令和5年4月11日、ヤマダホールディングスユニオンとデンコードーユニオンが申し立てていた、北東北3県(青森県、岩手県、秋田県)の全域を適用地域として、大型家電量販店に雇用される無期雇用フルタイム労働者の各年度に付与される所定休日数を111日以上とする労働協約の拡張適用を決定した。
ホームページ
出典:厚生労働省
愛知県人口動向調査結果 月報(令和5年3月1日現在) 愛知県 令和5年4月10日
令和5年3月1日現在の愛知県の人口は、7,483,341人となり、前月に比べ3,509人減少し、前年同月に比べ14,534人の減少となった。
ホームページ
出典:愛知県
愛知県毎月勤労統計調査地方調査結果 2022年年末賞与の支給状況 愛知県 令和5年4月10日
愛知県は、毎月勤労統計調査の2022年11月分から2023年1月分までの「特別に支給された給与」のうち、賞与として支給された給与(年末賞与)の支給状況を公表した。
支給労働者1人平均支給額は、調査産業計で529,283円となり、前年に比べ6.7%増加した。
支給事業所数割合は、調査産業計で88.1%、支給労働者数割合は調査産業計で91.2%となった。
所定内給与に対する支給割合は、調査産業計で1.36か月分となった。
ホームページ
出典:愛知県
「2022年病院看護実態調査」結果 日本看護協会 令和5年3月31日
日本看護協会は令和5年3月31日、「2022年病院看護実態調査」結果を発表した。
2021年度の離職率は、正規雇用看護職員が11.6%、新卒採用者が10.3%、既卒採用者が16.8%と、いずれも昨年調査よりも増加した。特に、新卒採用者の離職率は、同様の方法で把握してきた2005年以降、初めて10%を超えた。
ホームページ
出典:日本看護協会
就職プロセス調査(2024年卒)「2023年3月18日時点 内定状況」 就職みらい研究所
就職みらい研究所学生調査モニターの大学生・大学院生を対象に「就職プロセス調査」を実施し、調査結果を取りまとめ、発表した。
3月18日時点の大学生(大学院生除く)の就職内定率※1は、38.9%(+9.9ポイント)※2と引き続き高い水準となった。内定率を文理別で見ると「理系」が47.3%、地域別で見ると「関東」が47.0%で、特に高い数値となっている。
※1 内々定を含む ※2 ( )内数値は前年同月差
ホームページ
出典:就職みらい研究所 令和5年3月29日
「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を継続設置 厚生労働省
厚生労働省は、トラック運転者の長時間労働改善に向けて、労務管理の改善や荷主と運送事業者の協力による作業環境改善等を図るために令和4年8月1日に設置した「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を、令和5年度も継続して設置する。
相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、運送事業者からの労務管理改善や作業環境改善に関する相談に対応する。また、利用者の希望に応じて、オンラインや現地訪問による支援を無料で実施する。
ウェブサイト
自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/consultation/
ホームページ
出典:厚生労働省 令和5年4月3日
令和3年度 労働者供給事業報告書の集計結果公表 厚生労働省
厚生労働省では、「労働者供給事業報告書」(令和3年度報告)を取りまとめ公表した.職業安定法施行規則 (昭和22年労働省令第12号) では労働者供給事業を行う労働組合等に対し、各年度毎の運営状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するよう定めている。
1 労働者供給事業を実施している組合等数 104組合(1組合増)
2 供給実績
(1)需要延人員 1,899,190 人( 4.2%増)
(2)供給延人員 1,813,354 人( 4.6%増)
(3)供給実人員 15,080 人( 6.8%減)
3 令和4年3月末日における供給対象組合員等総数
(1)常用供給数 8,598 人( 11.1%減)
(2)臨時的供給数 2,140 人( 13.3%減)
(3)合計 10,738 人( 11.6%減)
4 令和4年3月末日における組合員等総数 1,054,904 人( 1.0%減)
※( )内は前年度比
ホームページ
出典:厚生労働省 令和5年3月31日
「副業・兼業に取り組む企業の事例について」公表 厚生労働省
厚生労働省は、副業・兼業の解禁を考えている業種に向けて、「副業・兼業に取り組む企業の事例について」を公表した。
この事例集は、2022年8月から10月にかけて、副業・兼業に取り組む企業11社にヒアリングを行い、その結果をまとめたもの。事例集には、副業・兼業を段階的に解禁したいと考えている、副業・兼業の解禁に不安を持っている、副業・兼業のことがよく分からないという方に向けて、先進的な取り組み事例に加えて「非雇用に限り副業を解禁している事例」や「副業・兼業を許可制としている事例」なども掲載している。
ホームページ
出典:厚生労働省 令和5年3月30日
失業給付要件見直しへ 自己都合でも迅速化
政府は、自己都合で離職した場合、会社都合で離職した人に比べて失業支給に時間がかかっている現状を是正する考えを示した。
失業給付は、ハローワークで求職申し込み後、解雇など会社の都合で退職した人には申し込みから1カ月程度で支給されるが、自己都合の場合は給付制限期間があるため、3カ月程度かかる。政府は現状を是正し、離職者の生活を支え、円滑な労働移動につなげる狙い。
出典:共同通信社/WEB労政時報
介護保険料 2023年度過去最高 厚生労働省
厚生労働省は27日、40~64歳の人が負担する介護保険料の推計が、2023年度は前年度から111円増加し、平均で1人当たり月6216円になると発表した。高齢化の進行により、介護サービスの利用者が増加しており、過去最高の更新が続いている。制度を開始した00年度は月2075円で、3倍近く膨らんだ。
40~64歳の保険料は毎年度改定する。65歳以上は市区町村ごとに3年に1度見直す。
出典:共同通信社/WEB労政時報
毎月勤労統計調査 令和4年12月分結果確報 厚生労働省
【前年同月比較】
●現金給与総額は567,916円(4.1%増)
うち一般労働者が782,495円(4.5%増)、パートタイム労働者が114,899円(2.5%増)となり、パートタイム労働者比率が32.23%(0.29ポイント上昇)
●一般労働者の所定内給与は320,857円(1.7%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,259円(3.3%増)
ホームページ
出典:厚生労働省
非正規女性 年収100万未満が4割強 総務省
非正規女性 年収100万未満が4割強 総務省
総務省の「労働力調査」の2022年平均結果によると、女性の非正規の職員・従業員に占める年間収入100万円未満の割合は41.2%だった。次いで高い100万~199万円は38.2%で、全体の8割が年収200万円未満となっている。
非正規の職員・従業員数は同26万人増の2101万人となり、3年ぶりにプラスに転じた。男性は正規が14万人減と落ち込み、非正規は16万人増と伸びている。女性は正規が16万人増、非正規が10万人増となり、ともに前年結果を上回っている。
出典:労働新聞 令和5年2月27日
マスクの個人判断化 従業員への要請は許容 厚生労働省
マスクの個人判断化 従業員への要請は許容 厚生労働省
厚生労働省は、マスク着用に関する事務連絡を都道府県などに向け発出した。3月13日からは個人の判断に委ねるのを基本とする。原則は個人判断だが、医療機関を受診する際や、重症化リスクが高い人が多い高齢者施設などへの訪問時、通勤ラッシュ時間帯の電車やバスなどの公共交通機関については、着用が効果的なため、推奨を続ける。
また、企業が感染対策や事業上の理由などにより、従業員に着用を求めることは許容されるとした。
出典:労働新聞 令和5年2月27日
令和4年コロナ労災請求 10万件超 厚生労働省
昨年1年間の新型コロナウイルスの労災請求件数が、一昨年に比べ、5倍以上増加し10万件を超えた。
昨年の新型コロナの労災請求件数は11万8152件で、一昨年の2万835件から大幅に増加した。支給件数は9万9756件で、こちらも一昨年の1万8516件から5倍以上増えている。
出典:労働新聞 令和5年2月13日
氷河期世代募集の暫定措置延長 厚生労働省
厚生労働省は、労働者の募集・採用における年齢制限の禁止の例外として、氷河期世代の無業者・不安定就労者に限定した募集・採用を認めている暫定措置について、令和7年3月末まで延長する方針。
労働施策総合推進法施行規則を改正し、今年3月末までとなっている期限を2年間延長する。
暫定措置の対象となる「就職氷河期世代」に該当するのは、昭和43年4月2日~63年4月1日生まれの人。
出典:労働新聞 令和5年2月13日
外国人雇用の事業者 過去最多 厚生労働省
外国人雇用の事業者 過去最多 厚生労働省
厚生労働省がまとめた外国人雇用に関する2022年10月末時点の届出状況を集計し、外国人を雇用している事業所数・雇用している外国人数が過去最多を記録したことが分かった。
外国人を雇用する事業所数は29万8790事業所(前年比1万3710事業所増)
外国人労働者数は、182万2725人(前年比9万5504人(5.5%)増)
国籍別:ベトナムが全体の25.4%を占め、中国21.2%、フィリピン11.3%と続く。
在留資格別:永住者など「身分に基づくもの」が32.7%で最も多く、「専門的・技術的分野」が26.3%、「技能実習」が18.8%となった。
出典:労働新聞 令和5年2月6日
障害者雇用の助成金減額へ 厚生労働省
厚生労働省は2日、民間企業に法律で義務付けている障害者の雇用割合(法定雇用率)を達成した上で、さらに多く雇う企業に対する助成金「障害者雇用調整金・報奨金」について、2024年度から減額を検討し、労働政策審議会の分科会に案を示した。雇用率に達しなかった企業が支払う納付金を原資としており、多くの障害者が働くようになり、助成金財政が厳しくなっていた。
出典:共同通信社/WEB労政時報
令和5年度雇用保険料率 愛知労働局
愛知労働局は令和5年4月から令和6年3月31日までの雇用保険料率を公表した。
失業等給付等の保険料率は、事業主負担、労働者負担ともに6/1,000に変更となり、双方の負担金額が増加する。
●一般の事業における
労働者負担は6/1,000(令和4年10月~は、5/1,000)
事業主負担は9.5/1,000(令和4年10月~は、8.5/1,000)
ホームページ
出典:愛知労働局
2023年3月卒 就職内定状況(2022年12月現在)公表 愛知県労働局
愛知県は、2022年度(2023年 3月)に県内の大学等を卒業する予定者について、2022 年 12月末現在の就職内定状況を取りまとめ公表した。
大学・短期大学を合わせた全体の就職内定率は 85.6%(前年同月差2.2ポイント)
大学のみ就職内定率 85.9%(前年同月差2.3ポイント)
短大のみ就職内定率 80.9%(前年同月差0.5ポイント)
ホームページ
出典:愛知県労働局就業促進課
2022年 年末一時金要求・妥結状況調査結果 愛知県労働局
愛知県労働局は、県内企業の年末一時金要求・妥結状況を県内労働情勢の一つとして調査し、その結果を取りまとめ公表した。
平均妥結額 :868,129円 【前年比】33,614円増 4.0%増 ※
平均妥結月数: 2.67か月 【前年比】0.11か月増 ※
※前年と回答企業が一部異なるため、単純比較はできない。
(県内308社が回答:平均年齢39.1歳 基準内賃金324,972円)
○2022年の年末一時金の平均妥結額は868,129円、平均妥結月数は2.67か月で、前年より額で33,614円の増、月数で0.11か月の増となった
○回答企業の約7割を占める製造業の平均妥結額は909,749円で、前年比44,091円の増(前年比5.1%増)となった
ホームページ
出典:愛知県労働局労働福祉課
一般職業紹介状況(令和4年12月分および令和4年分)公表
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和4年12月分および令和4年分)を公表した。
【結果概要】
○令和4年12月の有効求人倍率は1.35倍で、前月と同水準。
○令和4年12月の新規求人倍率は2.39倍で、前月に比べて0.03ポイント低下。
○令和4年平均の有効求人倍率は1.28倍で、前年に比べて0.15ポイント上昇。
【産業別】生活関連サービス業,娯楽業(18.5%増)、サービス業(他に分類されないもの)(7.9%増)、宿泊業,飲食サービス業(6.9%増)などで増加、建設業(6.2%減)、製造業(0.1%減)で減少
【都道府県別有効求人倍率】
就業地別、最高は福井県の1.94倍、最低は神奈川県と沖縄県の1.08倍、
受理地別、最高は福井県の1.82倍、最低は神奈川県の0.91倍
令和4年平均の有効求人倍率は1.28倍となり、前年の1.13倍を0.15ポイント増
令和4年平均の有効求人は前年に比べ12.7%増となり、有効求職者は0.7%減
ホームページ
出典:厚生労働省
年末一時金84.3万円 厚生労働省
厚生労働省がまとめた令和4年民間主要企業年末一時金妥結状況によると、集計367社の妥結額(加重平均)は84万2978円だった。前年結果と比べて7.77%増と伸びたが、コロナ禍前の水準(86万8604円)までは回復していない。
産業別では、前年比プラスが建設(3.36%増)や自動車(11.66%増)など15産業、マイナスが食料品・たばこ(0.03%減)や化学(2.70%減)など6産業となっている。
出典:労働新聞 令和5年1月30日
令和4年毎月勤労統計調査特別調査 結果公表 厚生労働省
厚生労働省は、令和4年「毎月勤労統計調査特別調査」の結果を取りまとめ公表した。
この調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労
働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として毎年実施している。
●小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態
【賃金】
・きまって支給する現金給与額(令和4年7月) 203,079 円(前年比 1.6%増)
・1時間当たりきまって支給する現金給与額(令和4年7月) 1,531 円(前年比 0.1%増)
・1年間(R3.8.1~R4.7.31)に賞与など特別に支払われた現金給与額 258,268 円(前年比 2.0%増) 【雇用】
・女性労働者の割合(令和4年7月末日現在) 57.3%(前年より 0.1 ポイント減少)
・常用労働者の産業別構成割合(令和4年7月末日現在)
「卸売業,小売業」が 25.6%と最も高く、次いで「建設業」11.3%、「医療,福祉」
9.8%、「宿泊業,飲食サービス業」9.6%、「生活関連サービス業,娯楽業」8.5%、
「製造業」7.8%の順。
ホームページ
出典:厚生労働省
令和6年3月新規高卒者就職選考期日公表 厚生労働省
全国高等学校長協会、主要経済団体、文部科学省及び厚生労働省において、令和6年3月に高校を卒業する生徒等の採用選考期日等について取りまとめ公表した。
令和6年3月新規高等学校卒業者の採用選考期日等
ハローワークによる求人申込書の受付開始 ・・・・・・・・ 6月1日
※高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を
確認したのち、学校に求人が提出されることとなります。
企業による学校への求人申込及び学校訪問開始 ・・・・・・・・ 7月1日
学校から企業への生徒の応募書類提出開始 ・・・・・・・・ 9月5日
(沖縄県は8月30日)
企業による選考開始及び採用内定開始 ・・・・・・・・ 9月16日
ホームページ
出典:厚生労働省
「小学校休業等対応助成金」3月末で終了 別制度へ 厚生労働省
厚生労働省は23日、新型コロナウイルス感染拡大で小学校などを休んだ子どもを世話するため、仕事を休まざるを得なかった保護者への助成制度「小学校休業等対応助成金」を3月末で終え、令和5年4月以降は、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設けることを決めた。
4月以降、育児や介護の休業取得促進に取り組む企業を支援する「両立支援等助成金」の制度を活用。支給額は、1人当たり10万円、1事業主につき10人分までとの上限を設ける。フリーランスで働く人向けに用意した支援は3月末で全て終了する。
ホームページ
出典:共同通信社・厚生労働省
「デジタル給与」実態調査 結果発表 エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン株式会社が運営する総合求人サイト『エン転職』上で、ユーザーを対象に「デジタル給与」についてアンケートを実施し 結果を発表した。
■結果概要
「デジタル給与」について・・・半数以上が「知らない」と回答
「知っている」48%(内容をよく知っている:6%、概要は知っている:42%)
「知らない」52%
「デジタル給与」を利用したいか・・・全体の2割は「利用したい」と回答
・20代は26%が「利用したい」と回答。年代が若いほど利用したい率が高い
利用したい19%(とても利用したい4%、利用したい15%)
利用したくない57%(あまり利用したくない34%、利用したくない23%)
わからない・その他25%
ホームページ
出典:エン・ジャパン株式会社
「令和5年3月大学等卒業予定者就職内定状況」公表 厚生労働省
厚生労働省と文部科学省は、令和5年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和4年12 月1日現在の状況を取りまとめ公表した。
■就職率の概要
大学(学部)は84.4%(前年同期差+1.4 ポイント)
短期大学は69.4%(前年同期差+6.6ポイント)
大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では83.6%(前年同期差+2.2ポイント)
大学等に専修学校(専門課程)を含めると82.1%(前年同期差+1.9ポイント)
ホームページ
出典:厚生労働省
非正規公務員ボーナス拡充へ 総務省
総務省は、20年4月時点で約62万人いる自治体で働く単年度契約の非正規職員(会計年度任用職員)のボーナスを拡充する方針を固めた。公務員のボーナスは期末手当と勤勉手当で構成。会計年度任用職員には期末手当しか支給できないが、正規職員や国の非正規職員と同じく両方を支給できるようにする。格差是正が狙い。地方自治法改正案を通常国会に提出、早ければ2024年度から適用する見込み。
出典:WEB労政時報/共同通信社
令和5年度年金額改定 厚生労働省
厚生労働省は、総務省から1月 20 日に「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことを踏まえ、令和5年度の年金額を法律の規定に基づき、新規裁定者(67 歳以下の方)は前年度から 2.2%引き上げ、既裁定者(68 歳以上の方)は前年度から 1.9%の引き上げとなることを公表した。
ホームページ
出典:厚生労働省
介護保険料率過去最高 全国健康保険協会
全国健康保険協会(協会けんぽ)は政府予算案を踏まえた令和5年度の収支見込をまとめ、介護保険料率が今年度から0.18ポイント増加し、1.82%になると発表した。制度開始以来過去最高の数値となる。介護保険制度は平成12年度に始まった。開始当初の自己負担を除いた保険給付は年間3.2兆円だったが、以降は右肩上がりの増加を続け、令和元年度に10兆円を超えていた。
出典:労働新聞 令和5年1月23日
「令和4年障害者雇用状況」公表 厚生労働省
厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、令和4年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ公表した。
■民間企業に雇用されている障害者数613,958.0人(前年より16,172.0人増加(対前年比2.7%増)19年連続で過去最高となった。
雇用者のうち、身体障害者は357,767.5人(対前年比0.4%減)、知的障害者は146,426.0人(対前年比4.1%増)、精神障害者は109,764.5人(対前年比11.9%増)と、知的障害者、精神障害者が前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。
■実雇用率 11年連続で過去最高の2.25%(前年は2.20%)、法定雇用率達成企業の割合は48.3%(同47.0%)であった。
ホームページ
出典:厚生労働省
障害者雇用率引き上げ 厚生労働省
厚生労働省は、民間企業に法律で義務付けている障害者の雇用割合(雇用率)を段階的に引上げることを決め、労働政策審議会で合意した。
雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては現行の2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。
国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とし、段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様とする。
ホームページ
出典:厚生労働省
22年年末賞与9%増 経団連
日本経済団体連合会(経団連)は「2022年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(加重平均)」を発表した。支給額の総平均は89万4179円で、前年(82万955円)から8.92%増加した。製造業・非製造業別では、製造業が91.5万円(7.29%増)、非製造業が83.2万円(16.86%増)だった。
ホームページ
出典:日本経済団体連合会
モデル就業規則改訂 新たに3規定追加 厚生労働省
厚生労働省はモデル就業規則を改訂し、新たに勤務間インターバル制度、出生時育児休業と不妊治療休暇の3つの規定を追加した。
インターバル制度は、休息時間が翌日の始業時刻にかかったケースについて、重複部分を働いたとみなす例と、始業時刻を繰り下げる例を提示。
出生児育休は、就業規則本体とは別に育児・介護休業に関する規則を設ける例を挙げた。不妊治療休暇は請求により、休暇と休業を取得できる例を提示した。
ホームページ
出典:労働新聞 令和5年1月16日
23年4月以降の雇用保険料0.2%引上げへ 厚生労働省
労働政策審議会の部会は、2023年4月から失業等給付分の雇用保険料率を0.2%引き上げ、法律上の原則どおり0.8%にすることを了承した。引上げ後の雇用保険料率は1.55%となる。
雇用保険財政はコロナ禍前までゆとりがあったため、料率は法律で定める原則よりも引き下げていた。4月以降は、失業等給付分を原則どおり0.8%とする。労使で折半する育児休業給付分の0.4%と、事業主が負担する雇用保険2事業分の0.35%は据え置く。
出典:労働新聞 令和5年1月16日
新型コロナ休業支援金・給付金 受付終了 厚生労働省
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給している「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を、2022年度末をもって終了する予定とした。申請期限は令和5年3月31日まで。
ホームページ
出典:厚生労働省
障害者雇用促進トップセミナーの参加者を募集 愛知県労働局
愛知県では、愛知労働局等関係機関との共催により、県内の企業において障害者の雇用と職場定着が一層進められるよう、事業主や人事担当者等を対象とした「障害者雇用促進トップセミナー」の参加者を募集している。
本セミナーでは、愛知労働局による障害者雇用状況に関する説明のほか、障害者雇用を積極的に進める企業と支援機関が「経営戦略としての障害者雇用」をテーマに、パネルディスカッションを行う。
詳細は愛知県労働局就業促進課HP。
ホームページ
出典:愛知県労働局就業促進課
「業務改善助成金(通常コース)」拡充 厚生労働省
厚生労働省は、中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する「業務改善助成金(通常コース)」について、令和4年12月12日から
・事業場規模30人未満事業者の助成上限額引き上げ
・特例事業者の助成対象経費拡充
・令和5年3月31日まで申請期限延長
等の拡充を行った。
ホームページ
出典:厚生労働省
「新卒採用活動支援セミナー」の動画をWeb上で配信中 愛知県
愛知県は、新型コロナウイルス感染症の影響により、採用活動やインターンシップにおけるオンライン化への対応に課題を抱える中小企業を支援している。
中小企業の人事担当者等を対象に、Web面接やインターンシップ等のオンラインによる実施や内定者フォロー等のノウハウを習得するためのセミナーを全6回開催し、そのセミナー内容を動画で随時配信中。
ホームページ
出典:愛知県労働局就業促進課
令和5年3月新規高等学校卒業予定者の求人・求職・就職内定状況公表 愛知労働局
愛知労働局職業安定部職業安定課は、令和4年11月末現在の令和5年3月新規高等学校卒業予定者の求人・求職・就職内定状況を公表した。
【結果概要】
●求人数34,460人 (対前年比14.3%)
●就職希望者数9,137人 (対前年比▲ 7.0%)
●就職内定者数 8,615人 (対前年比▲ 6.8%)
●求人倍率3.77倍 ( 対前年差0.70ポイント)
●就職内定率94.3% ( 対前年差0.2ポイント)
ホームページ
出典:愛知労働局職業安定部職業安定課
2022年労働組合基礎調査結果公表 愛知県労働局
愛知県は、県内の全ての労働組合を対象とした労働組合基礎調査を実施し、2022 年調査の結果を取りまとめ公表した。
【結果概要】
● 労働組合数: 2,388組合 【前年比】32組合 減(1.3% 減)
●労働組合員数: 79万1,787人【前年比】3,354人 減(0.4% 減)
【産業別の労働組合員数】
「製造業」 40 万 2,426 人(全労働組合員数の50.8%)と最多
次いで「卸売業,小売業」 8 万 928 人(全労働組合員数の10.2%)
「運輸業,郵便業」が 6 万 3,626 人(全労働組合員数の8.0%)
労働組合員数が最も増加したのは「卸売業,小売業」(1,839 人増)
●推定組織率: 20.9% 【前年差】0.3ポイント低下
ホームページ
出典:愛知県労働局
労働力調査(令和4年11月分)公表 総務省統計局
総務省は2022年11月分の労働力調査(基本集計)結果を公表した。
(1) 就業者数
就業者数は6724万人。前年同月に比べ28万人の増加。4か月連続の増加
(2) 完全失業者数
完全失業者数は165万人。前年同月に比べ18万人の減少。17か月連続の減少
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は2.5%。前月に比べ0.1ポイントの低下
ホームページ
出典:総務省統計局
一般職業紹介状況(令和4年11月分)公表 厚生労働省
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として公表した。
【令和4年11月分】
有効求人倍率(季節調整値)1.35倍となり、前月と同水準
新規求人倍率(季節調整値)2.42倍となり、前月を0.09ポイント上回る
新規求人(原数値)は前年同月と比較すると8.7%増
【産業別】
宿泊業,飲食サービス業(21.2%増)、サービス業(他に分類されないもの)(13.2%増)、
卸売業,小売業(13.0%増)などで増加、教育,学習支援業(9.4%減)で減少
【都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)】
就業地別では、最高は福井県の2.02倍、最低は神奈川県の1.09倍
ホームページ
出典:厚生労働省
令和4年「高齢者雇用状況等報告」集計結果公表 愛知労働局
愛知労働局は、令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の状況をとりまとめ公表した。
(集計対象)
愛知県内の常時雇用する労働者が21人以上の企業14,088社
中小企業(21~300人規模):12,985社
大企業 (301人以上規模):1,103社
【結果概要】
① 高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は14,088社(100.0%)[変動なし]
・高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、全企業において76.0%[0.9ポイント減少]
② 65歳定年企業の状況
65歳定年企業は2,522社(17.9%)[0.8ポイント増加]
・中小企業では18.4%[0.7ポイント増加]
・大企業では12.1%[1.4ポイント増加] ③70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は4,059 社(28.8%)[2.6ポイント増加]
・中小企業では29.5%[2.5ポイント増加]
・大企業では20.6%[2.7ポイント増加]
ホームページ
出典:愛知労働局職業安定部
雇用保険料0.2%引き上げ 厚生労働省
厚生労働省は14日、労使が払う雇用保険料率を、2023年4月から0・2%引き上げて1・55%にする方針を固めた。そのうち労働者の保険料率は現在の0・5%から0・6%となる。
例えば、月収30万円の人の場合、保険料は月1500円から1800円に増える。
事業主は0・85%から0・95%に上がる。
新型コロナウイルス禍に伴い雇用調整助成金の利用が増え、雇用保険財政を圧迫している。増収で財政を安定させることを目指す。
出典:共同通信社/WEB労政時報
2023年3月卒業予定者 就職内定率(11月末現在)81.8% 愛知県労働局
愛知県は、2022年度(2023年 3月)に県内の大学等を卒業する予定者について、2022年11月末現在の就職内定状況を取りまとめ公表した。
大学・短期大学を合わせた全体の就職内定率は 81.8%(前年同月 78.7%:3.1 ポイント上昇)と
なった。
大学:82.4%(前年同月79.3%:3.1ポイント上昇)
短大:73.1%(前年同月70.8%:2.3ポイント上昇)
ホームページ
出典:愛知県労働局就業促進課
毎月勤労統計調査 令和4年10月結果速報 厚生労働省
厚生労働省は、毎月勤労統計調査令和4年 10 月分結果速報をとりまとめ、公表した。 【結果概要】(前年同月と比較)
●現金給与総額は275,888円(1.8%増)
うち一般労働者が357,332円(1.9%増)、パートタイム労働者が99,556円(1.5%増)
パートタイム労働者比率が31.64%(0.05ポイント上昇)
●一般労働者の所定内給与は321,146円(1.5%増)、
パートタイム労働者の時間当たり給与は1,245円(1.3%増)
●就業形態計の所定外労働時間は10.4時間(5.9%増)
ホームページ
出典:厚生労働省
賃上げ5%要求 2023年度春闘 日本労働組合総連合会
日本労働組合総連合会(連合)は中央委員会を開き、2023年春闘で5%程度の賃上げを求める闘争方針を正式に決定した。歴史的な物価上昇を踏まえ、過去7年にわたって4%程度としてきた要求水準の引き上げに踏み切った。労働者の生活維持に必要な賃金を目指す。
10月に発表した23年春闘の基本構想によると、基本給を一律に引き上げるベースアップ(ベア)を月給の3%程度とし、定期昇給分と合わせて5%程度の賃上げを要求。明確な水準としては5~6%とした1995年以来の規模となる。
ホームページ
出典:共同通信社 / 日本労働組合総連合会
就活26年卒の弾力化検討 25年卒は現行維持 WEB労政時報/共同通信社
政府は30日、就職活動日程に関する関係省庁連絡会議を開き、2026年春に卒業する学生の就活ルールに関し、専門性の高い一部人材の採用日程の弾力化を含め速やかに検討するとした。
25年卒の学生については、広報活動を卒業する前年の3月以降、採用選考活動を6月以降、正式内定を10月以降とする現行日程を維持すると決めた。
政府が経団連に代わりルール設定するのは今年で5年目。経済界には来年3月末をめどに25年卒のルール順守などを要請する。
出典:WEB労政時報 / 共同通信社
デジタルリテラシーへの理解促進セミナー 中部経済産業局
中部経済産業局は「DXに挑む!はじめの一歩 ~デジタルリテラシーを身につけよう~」
セミナーを12月15日(木)に開催する。
中部経済産業局は、愛知労働局及び公益財団法人産業雇用安定センターと連携し、これからDXに取り組もうとしている企業経営者向けに、デジタルリテラシーについての理解促進を図り、実践に役立つセミナーを開催する。
ホームページ
出典:中部経済産業局
製造業・女性の採用比率向上 関西経済連合会
関西経済連合会の調査で、直近3年間の女性採用比率が全産業平均で前年度比0.4ポイント低下したのに対し、製造業では同1.7ポイント増加したことが分かった。製造業の採用比率は26.7%で、全産業平均の33.6%を下回っているものの、採用拡大の動きがみてとれる。
出典:労働新聞 令和4年11月28日
保険証としてマイナカード利用促進提言 経団連
経団連は、感染症の流行状況の迅速・的確な把握と医療サービスの効率的な提供に向け、医療DXの推進を訴えた。マイナンバーカードの健康保険証としての利用を進め、個人がマイナポータルを通じて健康・医療情報を閲覧・取得できるようにすべきなどと政策提言をまとめた。
医療DXの観点から、速やかなワクチン接種に向け、マイナンバーカードを通じて接種記録を含む健康・医療情報を国が一元的に管理し、個人の状況に応じて受診勧奨を行えるようにすることが重要と訴えた。
出典:労働新聞 令和4年11月28日
iDeCo加入可能年齢引上げ検討 厚生労働省
厚生労働省は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢の引上げの検討を始めた。社会保障審議会企業年金・個人年金部会で引上げに向けた資料を提示したもので、年内に議論をまとめるとしている。iDeCoには、2022年9月末現在264万2812人が加入している。
現行制度では、65歳まで加入が可能となっているが、高年齢者雇用安定法による就業確保措置の
努力義務が70歳まで伸びた点に留意しながら、引上げを検討していく。
出典:労働新聞 令和4年11月28日
12月「職場のハラスメント撲滅月間」厚生労働省
厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施している。
また、ハラスメント防止対策の取組の参考となるパンフレットや研修動画などを提供している。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)
ホームページ
出典:厚生労働省
3年以内離職率 大卒者で3割超 厚労省集計
平成31年3月に大学を卒業した大卒者の就職後3年以内の離職率が31.5%に上ることが、厚生労働省の集計で分かった。前年度と比較して0.3ポイント上昇した。同年の新規高卒者の離職率は35.9%で、同1.0ポイント低下している。
大卒・高卒ともに事業所規模が小さいほど離職率が高く、業種別では大卒・高卒ともに宿泊業・飲
食サービス業が最も高い。
出典:労働新聞 令和4年11月21日
22年度版 愛知のモデル賃金 愛知県経営者協会
愛知県経営者協会は、2022 年度 愛知のモデル賃金等調査結果について発表した。
【結果概要】
2022 年度 モデル賃金【総合職・現業職・一般職】
・22歳20.9万円、35歳32.4万円、50歳46.1万円、60歳47.5万円
・ 調査対象の全 30 年齢ポイントのうち、15 の年齢ポイント(前年 20 の年齢ポイント)におい
て前年を上回り、全年齢ポイント平均で対前年金額 0.2%増(前年 0.4%増)となった。
ホームページ
出典:愛知県経営者協会
2024年卒インターンシップ・就職活動準備に関する調査 (株)リクルート
株式会社リクルートの研究機関・就職みらい研究所は、「2024年卒 インターンシップ・就職活動準備に関する調査」の調査結果をまとめ発表した。
【結果概要】
・学生が参加したインターンシップ・1day仕事体験の期間別参加状況
1日以下」のプログラムは85.9%、平均参加件数5.15件
5日以上のプログラムは13.7%、平均参加件数1.16件
・満足度
期間がより長い方が「満足している」と回答した割合が高い
ホームページ
出典:(株)リクルート・就職みらい研究所
愛知県特定最低賃金(2業種)改正 令和4年12月16日発効 愛知労働局
特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されている。愛知県では、12月16日から2業種の特定最低賃金額が改定される。
発効日 令和4年12月16日
特定最低賃金名:鉄鋼業 最低賃金額(1時間):1,018円
特定最低賃金名:輸送用機械器具製造業 最低賃金額(1時間):997円
問い合わせ先:事業所を管轄する労働基準監督署
ホームページ
出典:愛知労働局
動画版「令和4年版 労働経済の分析」を公開 厚生労働省
厚生労働省は、今年9月に公表した「令和4年版 労働経済の分析」(労働経済白書)の動画版を作成し、公開した。労働経済白書は、雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書。
動画版は、4つの章で構成し、2021年の労働経済の推移と特徴や、労働者の主体的なキャリア形成に向けた課題などを、スライドと音声で分かりやすく説明している。動画版「令和4年版 労働経済の分析」は、厚生労働省のウェブサイトや厚生労働省YouTubeチャンネルで視聴可能。
ホームページ
出典:厚生労働省
新型コロナ・季節性インフルエンザ同時流行に備え検査証明配慮を 厚生労働省
厚生労働省は新型コロナに加え、インフルエンザについても従業員から検査結果などの提出を求めないよう要請する事務連絡を発出した。今冬の同時流行に備えた対応で、発熱外来などのひっ迫回避がねらい。
具体的には、従業員が新型コロナ・インフルエンザに感染し、療養を始める際に、検査結果の提出を求めないようにすべきとした。職場復帰する場合も、陰性証明や治癒証明の提出を不要にするよう要請している。
出典:労働新聞 令和4年11月14日
令和4年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に関わる求人・求職・就職内定状況」 厚生労働省
厚生労働省は、令和5年3月に高校や中学を卒業する生徒について、令和4年9月末現在のハローワーク求人における求人・求職・就職内定状況を取りまとめ公表した。対象は、学校やハローワークからの職業紹介を希望した生徒。
●結果概要
【高校新卒者】
○ 就職内定率 62.4%で、前年同期比0.4ポイントの増
○ 就職内定者数 約8万1千人で、同6.1%の減
○ 求人数 約42万5千人で、同15.4%の増
○ 求職者数 約12万9千人で、同6.7%の減
○ 求人倍率 3.29倍で、同0.63ポイントの上昇
【中学新卒者】
○ 求人数 759人で、前年同期比7.4%の減
○ 求職者数 686人で、同6.7%の減
○ 求人倍率 1.11倍で、同0.01ポイントの低下
ホームページ
出典:厚生労働省
育休明け子育て時短勤務に現金給付制度創設検討
政府は、育児休業明けで子育てのため勤務時間を短くして働く人向けに、新たな現金給付制度を創設する方向で検討している。時短勤務には、育児のため通常の勤務時間で働くことが難しい人が仕事を続け、徐々に本格的な復帰を目指してもらう目的がある。ただ慣れない両立に不安を抱え、賃金減少も重なるため働く意欲が低下し、離職につながりやすい。
給付は雇用保険加入者が対象で、時短勤務で賃金が減る中、子育てと仕事の両立を支援する狙い。政府は、就労の継続や通常勤務復帰によるキャリア形成を後押しする新たな方策が必要と判断した。
出典:共同通信社/WEB労政時報
学び直し企業に最大1億円 助成制度創設 厚生労働省
厚生労働省は、政府が掲げる「人への投資」の一環として成長分野など新たな事業展開に向けて従業員の「リスキリング(学び直し)」を実施した企業に、年最大1億円を支給する助成制度を設ける。新規事業を始め、その分野の知識や技術を従業員に習得してもらうための訓練を実施した企業が対象。従業員1人当たり最大時給960円(助成率は最大75%)を支給し、年間で1億円を上限に助成する。来年6月までに企業・産業間での労働移動円滑化に向けた指針を取りまとめる方針。
出典:共同通信社/WEB労政時報
毎月勤労統計調査 令和4年9月分結果速報等公表 厚生労働省
厚生労働省は、毎月勤労統計調査令和4年9月分結果速報等をとりまとめ公表した。
【調査結果のポイント】(前年同月比)
●現金給与総額(就業形態計) 275,787 円(2.1%増)
一般労働者の現金給与総額 357,039 円(2.4%増)
パートタイム労働者の現金給与総額 99,939 円(3.4%増)
●パートタイム労働者比率 31.64%(0.33 ポイント上昇)
ホームページ
出典:厚生労働省
2022春季生活闘争年末一時金(第1回)・企業内最低賃金協定(最終)回答集計結果 連合
連合は、2022春季生活闘争年末一時金(第1回)・企業内最低賃金協定(最終)の回答集計を発表した。 【結果概要】
●年末一時金:組合員一人あたり加重平均
月数:2.39月(昨年同時期 2.31月)
額:726,893円(昨年同時期 674,221 円)
いずれも昨年同時期実績と比較して上回った。
●企業内最低賃金協定
闘争前に協約があり、基幹的労働者の定義を定めている場合:166,004 円/時間額1,029円
闘争前に協約があり、基幹的労働者の定義を定めていない場合:月額166,515円/時間額976円
ホームページ
出典:日本労働組合総連合会
2022年度愛知のモデル賃金等調査結果 愛知県経営者協会
愛知県経営者協会は「2022年度愛知のモデル賃金等調査結果」について調査結果のポイントを発表した。
【結果概要】
●2022年度モデル賃金
・調査対象全30年齢ポイントのうち、半数の15の年齢ポイントにおいて前年度を上回る。
(前年度調査:20の年齢ポイント)
●2022年度管理職の実在者賃金
部長相当職平均562,107円、課長相当職平均450,361円
●2022年度モデル退職金
・大卒総合職 60 歳・勤続 38 年のポイントでは、前回調査に比べ 0.8 パーセント増加した。
・高卒現業職を見ると 40 歳以上で減少している。
ホームページ
出典:愛知県経営者協会
2022年(1-9月)上場企業「早期・希望退職」実施状況 東京商工リサーチ
東京商工リサーチは、2022年(1-9月)上場企業「早期・希望退職」実施状況を発表した。
2022年1-9月に早期・希望退職者の募集が判明した上場企業は、33社(募集人数5,000人)にとどまることがわかった。アパレル・繊維製品と機械が各4社で最多。次いで、電気機器、医薬品、情報通信が各3社、外食・小売などコロナ禍の直撃を受けた業種は募集無し。
コロナ禍の2020年以降、1-9月累計では社数、募集人数ともに最少を記録した。
募集人数は、通年ではコロナ前の2019年(通年35社、1万1,351人)を下回る可能性も出てきた。
ホームページ
出典:東京商工リサーチ
女性の活躍に関する意識調査 2022 ソニー生命
ソニー生命は、女性の活躍に関する意識と実態を明らかにするため「女性の活躍に関する意識調査」を行い、結果を発表した。
【結果概要】
●女性が考える家事・地域社会貢献での時給換算額は年々上昇傾向。
「育児・世話(未就学児)」 1,847 円
「育児・世話(小学生以上の子ども)1,542 円
「PTA 活動」1,441 円。
●7割弱の有職女性が、社会で働くには不利な点が多いと思っている。
年代別では、50代が最も高い。
●「女性が家庭と仕事を両立させるために必要だと思うこと」
1位「休暇が取得しやすい職場環境」、2位「男性の家事・育児参加」、3位「職場の理解・協力」
●職場にあったら良い働き方や制度
「時短勤務」が最も高く、「在宅勤務」、「週休3日」、「社内保育園」と続く。
ホームページ
出典:ソニー生命
11月は「過労死等防止啓発月間」 厚生労働省
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行う。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施している。月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行う。
ホームページ
出典:厚生労働省
大企業健保の負担増検討 厚生労働省
65~74歳(前期高齢者)の医療費を巡り、給与水準の高い大企業の社員らが加入する健康保険組合の負担を増やす方向で厚生労働省が検討していることが分かった。健保組合によっては保険料引き上げにつながる一方、給与水準の低い健保組合や、中小企業の社員らが入る協会けんぽは負担が軽くなる。支払い能力に応じた支え合いの仕組みを強め、健保の財政的な格差を是正する狙い。
ホームページ
出典:WEB労政時報/共同通信社
無料「専門労務相談」開催 愛知県労働局
愛知県では、県内の中小・小規模事業主、労働者等の方を対象として、社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士による「専門労働相談」を実施している。
コロナ禍における労務管理や就業規則の見直し、職場のトラブル、メンタルヘルスなど、様々な労働問題について専門の相談員が相談を受け、解決に向けて助言をする。
相談料は無料。
開催日時等詳細は、愛知県のHP
https://www.pref.aichi.jp/press-release/srs20221003.html
ホームページ
出典:愛知県
健康保険証 令和6年秋に廃止 デジタル庁
河野太郎デジタル大臣は、政府がマイナンバーカードと健康保険証の一体化に向け、健康保険証を令和6年の秋で廃止する方針を決めたことを明らかにした。
政府が実施した調査によると、マイナンバーカードの取得率は64.3%で、1~2月の前回調査に比べ5.4ポイント増加した。そのうち健康保険証としての利用申込みをした割合は43.6%となっている。
カードの取得率は業種によって差がみられる。最も高いのは国家公務員の84.2%、最も低いのは自動車整備業の53.2%だった。取得促進の取組みを実施している企業・団体の割合は16.7%に留まった。
出典:労働新聞 令和4年10月24日
「令和4年度 シニア人材活用セミナー」開催 愛知労働局
愛知労働局は、令和3年4月1日施行された改正高年齢者雇用安定法をはじめ、高年齢者の雇用に関するさまざまな情報をセミナーで紹介している。12月2日(金)に「令和4年度 シニア人材活用セミナー ~生涯現役社会における高齢者雇用を考える~」を開催する。
現地とオンラインのハイブリッド方式で開催し、参加費は無料。
詳細は愛知労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_taisaku/_79409/_kourei_seminar2022.html
ホームページ
出典:愛知労働局
WEBサイト「マイジョブ・カード」公開 厚生労働省
厚生労働省は、ジョブ・カードのデジタル化に向けて、新たなウェブサイト「マイジョブ・カード」を公開した。ジョブ・カードは、個人のキャリアプランや職務経歴を記録し、求職活動や能力開発に役立てるもので、これまでは紙または電子媒体で作成・保存することができた。今回公開したウェブサイトでは、オンライン上でジョブ・カードを作成・管理ができるようになる。また、マイナポータルからシングルサインオンできるほか、ハローワークインターネットサービスやjob tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))と連携し、登録情報の活用や、職業情報やキャリア形成に役立つ情報取得ができるようになる。
ホームページ
出典:厚生労働省
デジタル賃金2023年4月解禁 厚生労働省
スマートフォンの決済アプリなどを使い、賃金をデジタルマネーで支払う制度の解禁に向け、厚生労働省は10月26日の審議会で、関連する省令の改正案を了承した。導入には労働者の同意が条件で、企業は労使協定を結ぶ必要がある。
改正省令は2023年4月に施行される見通し。厚労省によるアプリ事業者の審査にも時間がかかるため、実際に運用が始まるのは施行から数カ月後となる見込み。
出典:WEB労政時報/共同通信社
奨学金代理返還 報酬に該当せず 厚生労働省
厚生労働省は、企業の奨学金返還支援(代理返還)について、原則として社会保険の「報酬等」に含めない考えを明らかにした。給与規程に基づき、給与に代えて直接返還する場合は給与の代替措置に過ぎないため、被保険者に直接返還金を支給しないケースであっても、報酬等に当たるとしている。
代理返還は2021年4月から始まったもので、(独)日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金の貸与を受けていた従業員が対象。
出典:労働新聞 令和4年10月10日
賃金デジタル支払い 2023年4月スタート 厚生労働省
厚生労働省は、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進むなか、一定の要件を満たした場合、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令案を明らかにした。
使用者が労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たして厚労大臣の指定を受けた移動業者の口座への資金移動によって賃金を支払えるようになる。公布は2022年11月、施行は2023年4月1日の予定。
出典:労働新聞 令和4年10月10日
10月は「年次有給休暇取得促進期間」 厚生労働省
厚生労働省は、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っている。
少子化社会対策大綱などで、令和7年までに年休の取得率を70%とすることが目標に掲げられているが、令和2年に年休の取得率は56.6%と過去最高となったものの、政府が目標とする70%には届いていない状況。
ホームページ
出典:厚生労働省
第46回技能五輪国際大会(京都大会)開催 ウェブサイトで視聴可能 厚生労働省/中央職業能力開発協会
厚生労働省と中央職業能力開発協会は、「第46回技能五輪国際大会(京都大会)」を令和4年10月15日(土)から18日(火)まで、京都市勧業館みやこめっせで開催する。
技能五輪国際大会は、幅広い職種の青年技能者を対象とした唯一の世界レベルの技能競技大会で、職業訓練の振興と技能水準の向上、技能者の国際交流、親善を図ることを目的に、2年に一度開催している。
第46 回技能五輪国際大会(京都大会)の様子は、専用ウェブサイト上(https://worldskills.jp/)でライブ配信するほか、競技期間中は会場で見学可能。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28004.html
中央職業能力開発協会:https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/kokusai/index.html
出典:厚生労働省・中央職業能力開発協会
愛知県最低賃金「986円」に引上げ 愛知労働局
令和4年10月1日から愛知県最低賃金が時間額986円に改正された。
令和4年9月30日までの愛知県最低賃金955円から31円引上げられ、986円に改定された。愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用される。
ホームページ
出典:愛知労働局
「令和4年 民間主要企業夏季一時金妥協状況」公表 厚生労働省「令和4年 民間主要企業夏季一時金妥協状況」公表 厚生労働省
厚生労働省は、労使交渉の実情を把握するため「民間主要企業の夏季一時金妥結状況」を集計し、令和4年の集計結果を公表した。
【集計対象】
資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業381社。
【集計結果概要】
平均妥結額は832,340円、昨年比較58,708円(7.59%増)
産業別妥結額 化学の1,008,350円が最高額。以下、鉄鋼992,406円、建設978,922円、自動車965,650円と続く。
ホームページ
出典:厚生労働省
「高卒採用自由化へ」提言 1人1社制見直しを 経済産業省
経済産業省の産業構造審議会教育イノベーション小委員会は、高卒者の1人1社制の見直しを文部科学省などに提言する中間案を取りまとめた。
全国的な慣行である「1人1社制」は、学生にとって実質的に1社しか応募できず、就職率が高く、就職後のミスマッチなど定着が不安定と指摘した。高卒者が求職する際の選択肢を多様化することが必要とし、現行の学校推薦に加え、求人サイトなどを通して学生自らが就職活動し、複数社に応募できる仕組みの普及を訴えた。
出典:労働新聞 令和4年9月26日
「2022年度中高年齢者再就職支援セミナー」参加者募集 愛知労働局
愛知労働局就業促進課は、中高年齢者の早期再就職を支援するため「中高年齢者再就職支援セミナー」を開催している。セミナーでは、講義形式で再就職に必要なノウハウや、面接対策などを学ぶことができる。第6回(会場:ウインクあいち)、7回(開催地:小牧市)、8回(開催地:豊田市)の参加者を募集している。受講料は無料。
詳細は、愛知労働局就業促進課のホームページ
6回(https://www.pref.aichi.jp/press-release/chukonen-2022-2.html)
7・8回(https://www.pref.aichi.jp/press-release/chukonen-2022-3.html)
ホームページ
出典:愛知労働局 就業促進課
企業の福利厚生 電子支払いを実証 内閣官房
内閣官房は、企業の福利厚生を電子通貨で支払う実証計画を新たに認定した。参加した労働者のアンケートにより、デジタル払いのメリット・デメリットを検証していく。
実証計画では、まず協力企業がテレワークの実施回数などの健康推進活動の実績に応じて労働者にポイントを付与する。付与されたポイントは前払式支払手段である電子通貨に交換できる。交換した電子通貨は商品購入などの場面で利用可能となっている。
出典:労働新聞 令和4年9月19日
「令和4年版 厚生労働白書」公表 厚生労働省
厚生労働省は、「令和4年版厚生労働白書」を公表した。
その年ごとのテーマを設定している【第1部】では「社会保障を支える人材の確保」と題し、現役世代が急減していく人口構造を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の対応の方向性をテーマとしている。
【第2部】では、テーマ「現下の政策課題への対応」と題し、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめている。
ホームページ
出典:厚生労働省
令和4年3月新卒者内定取消し等状況公表 厚生労働省
厚生労働省は、令和4年3月に大学や高等学校などを卒業して就職を予定していた人のうち、内定取消しとなったり、入職(入社)時期が延期(繰下げ)となった人の状況(令和4年8月末現在)を取りまとめ公表した。
内定取消しを行った事業所は27事業所、内定取消しとなった新卒者は50人だった。
ホームページ
出典:厚生労働省
男性育休白書2022 発表 積水ハウス
積水ハウス株式会社は、2019年から企業で働く男性の育休取得実態を探る「男性育休白書」を発行しており、2022年の4回目は、全国の小学生以下の子どもを持つ20代〜50代の男女9,400人を対象とした調査に加え、マネジメント層400人を対象とした調査を実施し、結果を発表した。
【結果概要】
積水ハウスは「男性の家事・育児力」の指標として ①配偶者評価 ②育休取得日数 ③家事・育児時間 ④家事・育児参加による幸福感の4つの独自の指標を設け、ポイント算出により都道府県ランキングを作成。
<男性の家事・育児力全国ランキング2022>
1位:高知県 2位:沖縄県 3位:鳥取県
<男性の育休取得や家事・育児の実態>
男性の育休取得率は17.2% 前年から5ポイント上昇
女性の家事・育児時間が減少 夫のリモートワークが家事・育児の分担を促進
育休制度の認知も高まる一方、本人・上司・同僚それぞれ不安を感じている
ホームページ
出典:積水ハウス
企業が求める人物像「高いコミュニケーション能力」 帝国データバンク
帝国データバンクは、企業が求める人材像についてアンケートを行い、結果を発表した。
【結果概要】
採用活動において、どのような人材像を求めているかを尋ねたところ、「コミュニケーション能力が高い」(42.3%)と「意欲的である」(42.2%)が4割超となった。
一方で、中途入社者に対しては、即戦力として業務に従事できる能力や、誠実で信頼できる人柄が求められていることが明らかとなった。
また、主に採用するのは新規卒業者か中途入社者かの問いには、大企業で新卒採用メインの割合が高く、企業規模が小さくになるにしたがい中途採用メインの割合が増えている。
ホームページ
出典:帝国データバンク
賃金デジタル支払い 23年にも解禁 上限100万 厚生労働省
厚生労働省は、スマートフォンの決済アプリなどを使い賃金を「デジタルマネー」で支払う制度の解禁に向け、2022年度内の省令改正を目指す方針を明らかにした。審議会で、安全性を懸念する労働組合側から、資金保全の仕組みに関して一定の理解を得られたと判断した。23年中にも解禁する可能性がある。
スマートフォンアプリなどで扱うことができるデジタルマネーを用いた賃金支払いについては、政府方針により当初2021年度中の解禁に向けて検討が進められていたが一時中断となり、2022年3月から議論が再開された。
審議会で示された骨子案では、安全性を担保するため、口座残高の上限を100万円以下に設定し、超えた場合はすぐに銀行口座に移すことが可能といった要件を満たす決済アプリ業者を、厚労相が指定するとした。また、万一業者が破綻した場合は、口座残高全額を速やかに労働者に保証することとしている。賃金のデジタル払い解禁には、賃金の確実な支払方法について規定する厚生労働省令(労働基準法施行規則)の改正が必要となり、厚労省では今後早期の改正に向けて議論を進める構えとみられる。
ホームページ
出典:共同通信社/WEB労政時報
ビジネスパーソンと企業の転職意識ギャップ調査 第2回「男性育休」 パーソルキャリア株式会社
パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda」は、第2回は「男性育休」に関するビジネスパーソンと企業とのギャップを調査し結果を公表した。
【調査結果概要】
●個人、企業ともに「今の会社で育休取得しやすい」と回答した人は57.5%とギャップなし
一方で、個人の取得意向は90.0%と「取得しやすさ」と大きな差が出る結果に
●「男性育休」取得時の不安にギャップあり
個人は「収入の減少」(49.5%)、企業は「業務の引継ぎ」(43.5%)を最も不安に感じている
● 個人、企業ともに「育休の分割取得」に期待が高い
● 企業の育休取得実績率が転職時の応募動機に影響すると回答した個人、企業はともに7割以上。転職先を選ぶ際に重視するワークライフバランスの制度として「育休」が上位。
ホームページ
出典:パーソルキャリア株式会社
「2022年度 新入社員意識調査」 一般社団法人日本能率協会
一般社団法人日本能率協会(JMA、会長:中村正己)は、仕事や働くことに対しどのような意識を持っているか調査を行い、「2022年度 新入社員意識調査」結果を公表した。
【結果概要】
・理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人(71.7%)」が1位で2012 年以降の
調査で過去最高。
・仕事の不安は、人間関係「上司・同僚などの職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が 1 位、2位は「仕事に対する現在の自分の能力・スキル(53.4%)」
・抵抗がある業務は、1位「指示が曖昧なまま作業を進めること(抵抗がある+どちらかは抵抗がある)82.7%」、2位は「知らない人・取引先に電話をかける(抵抗がある+どちらかは抵抗がある)69.3%」
・仕事よりもプライベートを優先したい人は8割
ホームページ
出典:2022年度「新入社員意識調査」(一般社団法人日本能率協会)
一般職業紹介状況(令和4年7月分)公表 厚生労働省
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、「一般職業紹介状況令和4年7月分」を公表した。
【結果概要】
有効求人倍率(季節調整値)1.29倍(前月を0.02ポイント上回る)
新規求人倍率(季節調整値)2.40倍(前月を0.16ポイント上回る)
正社員有効求人倍率(季節調整値)1.01倍となり、(前月を0.02ポイント上回る)
7月の有効求人(季節調整値)前月比0.8%増・有効求職者(季節調整値)前月比1.2%減
7月の新規求人(原数値)前年同月比12.8%増
<産業別>宿泊業,飲食サービス業(47.7%増)、サービス業(他に分類されないもの)(16.7%増)、運輸業,郵便業(14.7%増)、製造業(14.5%増)
<都道府県別有効求人倍率(季節調整値)>
就業地別:最高は福井県の2.10倍、最低は沖縄県の1.01倍
受理地別:最高は福井県の1.93倍、最低は神奈川県と沖縄県の0.91倍
ホームページ
出典:厚生労働省
2021年度国民生活基礎調査結果公表 厚生労働省
厚生労働省は、「2021(令和3年)年国民生活基礎調査」の結果を取りまとめ公表した。
【調査結果のポイント】
●世帯の状況
・単独世帯は 1529 万2千世帯(2019年・1490 万7千世帯)、全世帯の 29.5%<2019年・28.8%)と世帯数、割合とも過去最高
・高齢者世帯は 1506 万2千世帯 (2019年・1487 万8千世帯)、全世帯の 29.0%(2019年・28.7%)と世帯数、割合とも過去最高
・児童のいる世帯における母の「仕事あり」の割合は 75.9%(2019年・72.4%)と過去最高
●所得等の状況
・1世帯当たり平均所得金額は564万3千円 (2019年・552万3千円)と増加
・生活意識が「苦しい」とした世帯は 53.1% (2019年・54.4%)と低下
ホームページ
出典:厚生労働省
離職率低下 介護労働実態調査 介護労働安定センター
介護労働安定センターは、令和3年度介護労働実態調査をまとめ発表した。
訪問介護員と介護職員の2職種における離職率は前年比0.6ポイント減の14.3%だった。平成19年をピークに低下傾向にあり、同年の約3分の2まで低下。離職率は低下しているものの、人材の不足感を訴える事業所は63.0%に上り、前年の60.8%より多い。
早期離職防止や定着促進に最も効果のあった方策は「本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる」で、22.9%だった。次いで多かったのは「残業を少なくする、有給休暇を取りやすくする等の労働条件の改善に取り組んでいる」で18.1%となっている。
出典:労働新聞社 令和4年9月5日
令和4年10月1日施行 育児休業給付制度の改正について 厚生労働省
厚生労働省は、令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について、被保険者と労働者にむけて改めて周知した。
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができる。また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができる。※令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象
【育児休業給付について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
1歳に達する日後の期間について、保育所等における保育の実施が当面行われないなどの事情がある場合、1歳6か月または2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の対象となります。
【事業主用リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf
ホームページ
出典:厚生労働省
「2023年卒の就職活動の費用に関する調査結果」発表 リクルート
株式会社リクルートの研究機関・就職みらい研究所は、就職みらい研究所学生調査モニターの大学生・大学院生を対象に「2023年卒の就職活動の費用に関する調査」を実施し、調査結果を発表した。
【調査結果概要】
学生が就職活動に使用した金額について
2023年卒学生が6月時点で就職活動に使用した金額は、平均7万5,245円と、コロナ禍前(2020年卒)から約4割減少。2022年卒と比べると、約3,000円増加したが、コロナ禍前よりも就職活動費用が少ない傾向が続いている。要因は、22年卒で進んだオンライン活用の一定の普及と、最終面接を中心とした対面機会の活用が考えられる。
ホームページ
出典:株式会社リクルート
愛知県内企業における2022年夏季一時金要求・妥結状況調査結果公表 愛知県
愛知県は、県内企業の夏季一時金要求・妥結状況を県内労働情勢の一つとして調査し、その結果を取りまとめ公表した。
【調査結果概要】
平均妥結額 :939,121円 【前年比】111,751円増 13.5%増 ※
平均妥結月数: 2.90か月 【前年比】0.36か月増 ※
※前年と回答企業が一部異なるため、単純比較はできない。
(県内323社が回答:平均年齢39.1歳 基準内賃金324,057円)
●2022年の夏季一時金の平均妥結額は939,121円、平均妥結月数は2.90か月と、いずれも4年ぶりの増加となり、平均妥結額は、加重平均により集計を始めた1990年以降の最高額となった。
●企業規模別(299人以下、300~999人、1,000人以上)では、すべての企業規模において前年を上回った。
ホームページ
出典:愛知県
新型コロナの労災認定 7月末時点で昨年度超過 厚生労働省
今年度の新型コロナウイルスの労災認定件数は7月末時点で2万2032件と、昨年度1年間の数字をすでに上回っていることが分かった。請求も2万8601件で、昨年度を超過している。
新型コロナは、業務による感染が明らかな場合に加え、感染経路が不明であっても、感染リスクの高い業務に従事し、業務による感染の蓋然性が高い場合は労災と認めている。さらに医療従事者については、業務外での感染が明らかなケースを除き、原則労災認定している。
累計の認定件数は4万6069件となった。内訳は医療従事者が3万1891件、医療従事者以外が1万4130件、海外出張者が48件だった。
労働新聞社 令和4年9月5日
在籍型出向に助成金 労働者の能力向上促進 令和5年度 厚生労働省
厚生労働省は令和5年度、在籍型出向を活用した労働者の能力向上を促進するため、産業雇用安定助成金に新コースとして「スキルアップ支援コース」(仮称)を追加する方針。政府が重点課題に掲げる「人への投資」の施策の一環で、労働者のスキルアップのために在籍型出向を行う出向元に対し、出向労働者の賃金の一部を助成する。
在籍型出向は、自社にはない実践の場での経験から新たなスキルを習得することが期待できるため、賃金の一部を助成することで在籍型出向を推進し、企業活動の活性化を促すのが狙い。
労働新聞社 令和4年9月5日
改正育児介護休業法Q&A集 改定 厚生労働省
厚生労働省は、今年4月から順次施行している改正育児休業法のQ&A集を改定し、出生時育休期間中の就業に関する留意点を拡充した。
Q&A集では、管理監督者や、通常の労働者と異なる労働時間制度の適用者に対する出生時育児介護休業期間中の就業に関する項目を追加した。
【令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A】厚生労働省
ホームページ
労働新聞社 令和4年8月29日
障害者年金受け取りやすく 改正検討 厚生労働省
厚生労働省は、一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから、金額が多い「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めた。2025年に国会提出を目指す年金制度の改正法案に盛り込みたい考えで、今後具体策を審議会で議論する。実現すれば、障害年金の制度上、約40年ぶりの大きな変更となる。障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が重要で、初診日のわずかな違いで年金の有無や支給額が大きく左右される構造的な問題に対し、障害者からは改正を求める声が以前から上がっていた。
ホームページ
出典:WEB労政時報/共同通信社
地域別最低賃金の改定額 全都道府県の答申出そろう 地方最低賃金審査会
厚生労働省の中央最低賃金審議会は、8月初旬に令和4年度の地域別最低賃金額改定の「目安」について答申した。国が示した引き上げ額の目安を参考に、都道府県ごとに地域審議会が協議を進め、最低賃金の引上げ額を決定し答申した。改定額は10月以降、順次適用されていく。
●【国の目安額】各都道府県の引上げ額の目安
(※都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示)
Aランク(愛知・東京・大阪など6都府県)31円
Bランク(三重・静岡・京都など11府県)31円
Cランク(岐阜・福岡など14道県)30円
Dランク(青森・沖縄など16県)30円
●地方最低賃金審議会の答申
・47都道府県で、30~33円の引上げ(引上げ額30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
・改定額の全国加重平均額は961円
・全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・愛知県986円(改定前955円・今回引上げ額31円)、岐阜県910円(改定前880円・今回引上げ額30円)、三重県933円(改定前902円・今回引上げ額31円)
ホームページ
出典:厚生労働省
薬剤師も給与引き上げ措置支援対象に追加要望 一般社団法人日本病院会
一般社団法人日本病院会は、令和4年10月からの診療報酬改定で看護職員を対象に給与引上げのための仕組みが創設される見込みであることを受け、給与引上げの対象に、「病院に勤務する薬剤師」を追加するよう要望書を厚生労働省に提出した。
厚生労働省は、10月の診療報酬改定を通じ、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、収入を3%程度(月額平均1万2000円相当)引き上げる処遇改善の仕組みを創設する方針。日本病院会は、対象職種が特定の職種に限定されているため、多職種の連携によるチーム医療においては不公平感が生じる恐れがあるとし、チーム医療の円滑な推進の観点から、病院の勤務薬剤師を対象に含めるよう訴えた。
出典:労働新聞 令和4年8月8日
雇用保険 基本手当日額変更 厚生労働省
厚生労働省は、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更した。
雇用保険の「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。今回の変更は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴う措置。
●基本手当日額の最高額引上げ
年齢別の最高額
(1)60 歳以上65 歳未満 7,096 円 → 7,177 円(+81 円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,265 円 → 8,355 円(+90 円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,510 円 → 7,595 円(+85 円)
(4)30 歳未満 6,760 円 → 6,835 円(+75円)
●基本手当日額の最低額引上げ
2,061 円 → 2,125 円(+64円)
ホームページ
出典:厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和4年6月分結果速報公表 厚生労働省
厚生労働省は、毎月勤労統計調査令和4年6月分結果速報をとりまとめ公表した。
【結果概要】(前年同月比較)
●現金給与総額は452,695円(2.2%増)
うち一般労働者が608,617円(2.5%増)・パートタイム労働者が108,730円(2.7%増)
なお、一般労働者の所定内給与は319,841円(1.5%増)・パートタイム労働者の時間当たり給与は
1,228円(1.1%増)
●パートタイム労働者比率31.31%(0.39ポイント上昇)
ホームページ
出典:厚生労働省
男性育休取得率9年連続上昇 厚生労働省
厚生労働省は「令和3年度雇用均等基本調査」の結果を取りまとめ公表した。
調査結果によると、育児休業取得者(令和元年10月1日から令和2年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性、男性の場合は配偶者が出産した男性のうち、令和3年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。))の割合は、女性85.1%(令和2年度81.6%)、男性13.97%(令和2年度12.65%)で、男女ともに前年度より上昇し、男性においては9年連続上昇した。
ホームページ
出典:厚生労働省
ワーケーション導入ガイド作成 (一社)日本経済団体連合会
(一社)日本経済団体連合会は、企業におけるワーケーションの導入手順と規程整備上の留意点を示した「導入ガイド」を作成した。ワーケーションは場所にとらわれない働き方の1つで、テレワークを行いながら普段の職場や自宅と異なる地域での滞在を楽しむ働き方。休暇中の訪問先で業務を行うワーケーションであっても、在宅勤務時と同様に労働時間を適正に把握する義務があると指摘したうえで、労働者による始業・終業時刻の報告方法を社内規程に明記する必要があるとした。また、労働災害の観点から、業務時間と余暇時間の明確化も重要としている。
出典:労働新聞 令和4年8月1日
第10回「働く人の意識調査」結果公表 日本生産性本部
(公財)日本生産性本部は、新型コロナウイルス感染症が組織で働く人の意識に及ぼす影響の継続調査(第 10 回「働く人の意識調査」)結果を取りまとめ公表した。
【結果概要】
・新型コロナウイルスの影響で、勤め先の業績(売上高や利益)に不安を感じているかどうかの問いに、「かなり不安を感じる」は 10.2%、「どちらかと言えば不安を感じる」38.5%の合計は 48.7%と、前回調査より減少した。
・今後の自身の雇用について、「不安を感じない」(「全く不安を感じない」13.5%、「どちらかと言えば不安を感じない」38.4%の合計)と回答した人が51.9%。
・テレワークの実施率は 16.2%と2020年5月の調査開始以降、過去最低。
・従業員規模別のテレワーク実施率は、従業員数101~ 1,000人の企業は前回調査の25.3%から17.6%に、1,001人以上の企業は前回の33.7%から27.9%へと減少。また、100人以下の企業は前回の11.1%から10.4%と微減した。今回、いずれの従業員規模でも過去最低の実施率。
ホームページ
出典:(公財)日本生産性本部
男女賃金差の公表義務化 女性活躍推進法の改正省令を施行 厚生労働省
厚生労働省は7月8日、労働者301人以上の企業に対して男女の賃金の差異の公表を義務付ける女性活躍推進法の改正省令を施行した。情報の公表は、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者の3区分で実施する。派遣労働者は派遣先の非正規雇用労働者には含まない。
男女の賃金差異の公表義務化は、今年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザインおよび実行計画」で示されたもの。
出典:労働新聞 令和4年7月25日
令和3年労働安全衛生調査(実態調査)の結果を公表 厚生労働省
厚生労働省は「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を取りまとめ公表した。
労働安全衛生調査は、周期的にテーマを変えて調査を行っている。令和3年は事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について調査を行った。
【調査結果概要】
■メンタルヘルス対策への取組状況<事業所調査>
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合
労働者数 50 人以上の事業所で 94.4%(令和2年調査 92.8%)、
労働者数 30~49 人の事業所で 70.7%(同 69.1%)、
労働者数 10~29 人の事業所で 49.6%(同 53.5%)
■仕事や職業生活に関する強いストレス<個人調査>
現在の仕事や職業生活に強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%(令和2年調査 54.2%)。その内容は「仕事の量」が 43.2%(同 42.5%)と最も多い。
ホームページ
出典:厚生労働省
「いじめ・嫌がらせ」相談件数増加 民事上の個別労働紛争 厚生労働省
厚生労働省は、「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表した。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件やトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法がある。
総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談は124万2579件で前年度比3.7%減。このうち民事上の個別労働紛争の相談件数は28万4139件で前年度比1.9%増。民事上の個別労働紛争における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で「いじめ・嫌がらせ」の件数が最多。民事上の個別労働紛争の「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は8万6034件で前年度比8.6%増、10年連続最多。
ホームページ
出典:厚生労働省
改正公益通報者保護法(令和4年6月施行法)に準拠した「公益通報ハンドブック」公表 消費者庁
消費者庁は「公益通報ハンドブック 改正法(令和4年6月施行)準拠版」を公表した。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものである。今回公表されたハンドブックは、労働者および事業者に向けて最新の「公益通報者保護法」の内容についてまとめてある。
ホームページ
出典:消費者庁
雇用保険受給期間の特例を新設 2022年7月1日から 厚生労働省
厚生労働省は2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間雇用保険の基本手当の受給期間に算入しない特例を新設した。受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっている。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動 に当たって基本手当を受給することが可能になる。特例申請については要件があり、すべてを満たす必要がある。
詳細は厚生労働省HPを参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000954820.pdf
ホームページ
出典:厚生労働省
受入企業に奨励金 紹介予定派遣で就労支援 厚生労働省
厚生労働省は、コロナ禍で離職を余儀なくされた非正規雇用労働者や異職種・異業種への転職を希望する人などの就労を支援するため、紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業を開始した。事業の委託先である派遣事業者がカウンセリングや研修を実施した後、紹介予定派遣を活用して正社員就職を後押しする。同事業を通じて派遣労働者を受け入れ、一定の要件を満たした派遣先には、奨励金の支給や、派遣料金・紹介手数料の負担軽減措置などを行う。
出典:労働新聞 令和4年7月18日
新型コロナ 自宅療養証明書不要 傷病手当金Q&A改訂 厚生労働省
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」を改訂し、全国健康保険協会や健康保険組合連合会などに事務連絡として発出した。
健康保険法では、傷病手当金の支給申請書には医師等の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならないこととされているが、「宿泊・自宅療養証明書」については添付を求められていない。
「宿泊・自宅療養証明書」については、医療従事者や保健所等の負担を考慮して内容を簡素化する等の対応を行っている中で、保険者において一律に当該証明書を求めることは適切ではないとした。なお、保険者の判断により、何らかの証明書を求める場合には、例えば、My HER-SYSの電子証明書の活用を認める等の対応が考えられるとした。
出典:労働新聞 令和4年7月25日
令和3年度「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果公表 愛知労働局 6月24日
愛知労働局は、令和3年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の状況をとりまとめ公表した。(集計対象:愛知県内の常時雇用労働者21人以上の企業13,894社)
【集計結果】
■65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況
① 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は13,894社(100.0%)
② 65歳定年企業は2,381社(17.1%)
■66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
① 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は3,646社(26.2%)
② 66歳以上まで働ける制度のある企業は5,744社(41.3%)
③ 70歳以上まで働ける制度のある企業は5,455社(39.3%)
④ 定年制の廃止企業は537社(3.9%)
ホームページ
出典:愛知労働局
精神障害の労災認定3年連続過去最多 労災補償状況公表 厚生労働省 6月24日
厚生労働省は「過労死等の労災補償状況」を取りまとめ公表した。仕事が原因でうつ病などの精神障害を患い、令和3年度に労災認定されたのは前年度比21件増の629件だった。3年連続で過去最多を更新した。精神障害による労災申請も前年度比295件増と2346件で過去最多だった。
原因別でみると「パワーハラスメント」が125件で最も多く、業種別では「社会保険・社会福祉・介護事業」が82件で最多。医療業、道路貨物運送業、飲食店と続いた。
愛知県の令和3年度精神障害による労災申請は157件、うち労災認定されたのは34件だった。
ホームページ
出典:厚生労働省
国民年金の保険料免除 令和3年度過去最多 厚生労働省 6月23日
厚生労働省は、令和3年度国民年金加入・保険料納付状況を公表した。保険料の納付を全額免除・猶予されている人は令和2年度から3万人増の612万人で過去最多を更新した。新型コロナウイルス禍による経済状況の悪化が長期化していることが影響したとみられる。
「現年度納付率」は、73.9%で前年度から2.4ポイント増で、10年連続で上昇している。
都道府県別に納付率を見ると、最も高いのは島根の85・5%、最も低いのは沖縄の66・8%。愛知県は75.5%で47都道府県中28位。
ホームページ
出典:厚生労働省
男女間賃金差開示 7月施行 労政審省令改正案了承 厚生労働省 6月24日
厚生労働省は、労働政策審議会の分科会で従業員300人超の企業に対し「男女間の賃金差の開示」を義務付ける省令改正案を提示し、了承され、7月に施行予定。
現在、女性活躍推進法に基づく省令では、従業員300人超の企業に対し、「管理職に占める女性割合」や「平均勤続年数の男女差」など厚労省が挙げた十数項目のうち2項目以上を任意で選び公表するよう定めている。今回の省令改正では、公表が必須の項目として「男女の賃金差」を加える。従業員300人以下の企業は開示義務はないが、積極的な公表を促す。
ホームページ
出典:共同通信社
夫婦交替育休取得推進企業に奨励金 東京都
東京都は、(公財)東京しごと財団と連携して、育児中の従業員の就業継続や男性従業員の育児休業取得を応援する東京都内企業等に対して奨励金を支給している。
今回新たに、育児介護休業法改正で増加が見込まれる「夫婦交替等での育児休業取得」を支援するため、奨励金制度「パパと協力!ママコース」を設立した。新コースでは、女性従業員に半年以上1年未満の育児休業を取得させ、夫婦交替等での育休取得を推進し、一定条件を満たした都内中小企業を対象に100万円を助成する。
ホームページ
出典:東京都 TOKYOはたらくネット
採用選考に情報活用 インターンの取扱い改定 厚生労働省・経済産業省・文部科学省
厚生労働省、経済産業省、文部科学省は、インターンシップ実施上のルールなどを示した「インターンシップ推進に当たって
の基本的考え方」を改定した。一定の条件を満たしたインターンを通じて得た学生情報については、採用活動開始後に活用できるよう改めた。今回の改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生、主に今の大学2年生が令和5年度に参加するインターンシップから適用される。改定前は、基本的に、取得した学生情報を広報活動に使用してはならないとしていた。
出典:労働新聞 令和4年6月23日
最低賃金1,000円へ 「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太方針)を閣議決定
政府は6月7日、政策の指針となる「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太方針)を閣議決定した。新しい資本主義を実現するための重点項目として「人への投資」を掲げたうえで、多様な働き方の推進や賃上げ・最低賃金引上げに取り組むとした。最低賃金については、できる限り早期に全国加重平均1000円以上の達成をめざすと明記している。
出典:労働新聞 令和4年6月20日
健診の活用推進へ アクションプラン(案)示す 経済産業省
経済産業省は、健康・医療新産業協議会のなかで、未来の健康づくりに向けたアクションプラン(案)を示した。未来の健康づくりでは職場との連携が重要になるとして、法令上必要な健康診断のほか、企業が独自に検査項目を加える取組みを支援していくべきとした。現状では、健診が法令に基づく義務=コストとみられるのみで、結果が活かされていないと指摘。健診を人的資本への投資と考え、労働者の健康をサポートしていくことが、定着率や生産性の向上につながるとしている。また、健診後は結果を踏まえ、通院や体調に合わせて勤務時間が調整できる職場環境が望まれるとしている。
出典:労働新聞 令和4年6月20日
障害者のテレワーク雇用に向けた企業向けコンサルティング実施 厚生労働省 6月15日
厚生労働省は、障害者のテレワーク雇用に向けた企業向けコンサルティングを実施している。障害者をテレワークで雇用するにあたり生じる個別具体的な課題について、電話・メール・事業所訪問・オンラインで最大5回まで無料で相談できる。さらに、障害者をテレワークで雇用することを検討している企業、障害者をテレワークで雇用しているものの課題を抱えている企業等に対して、コンサルティングを実施する。
ホームページ
出典:厚生労働省
テレワークに関する労務管理とICTのワンストップ相談窓口設置 厚生労働省 6月10日
厚生労働省は、総務省と連携し、テレワークに関する労務管理とICT(情報通信技術)の双方について、ワンストップで相談できる窓口をテレワーク相談センターに設置した。テレワークを導入しようとする企業等に対し、「労務管理」から「ICT活用」まで、テレワークに関する相談、コンサルティングにワンストップで対応し、「良質なテレワーク」の導入・定着の支援を行う。
ホームページ
出典:厚生労働省
ウクライナ避難民受入れ企業に助成金 雇用保険法施行規則改正 厚生労働省 5月30日
厚生労働省は、日本に滞在しているウクライナ避難民の更なる雇用機会の増大・創出を図るため、改正雇用保険法施行規則を公布、施行した。
5月30日から、当分の間、就労を希望するウクライナ避難民の就労支援について、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を継続雇用または試行雇用する事業主に対し、特定求職者雇用開発助成金またはトライアル雇用助成金を支給する。
ホームページ
出典:厚生労働省
高齢者の労災増加 厚生労働省 令和4年5月30日
厚生労働省は、令和3年の労働災害発生状況を取りまとめ公表した。
死亡者数と休業4日以上の死傷者数がともに前年を上回り、死傷者数の4分の1を60歳以上が占め、高齢者が被災するケースが増えている。
令和3年1月から12月までの労災死亡者数は867人で、前年比65人(8.1%)増と4年ぶりに増加。新型コロナ関係を除く死傷者数を年齢別にみると、60歳以上が最多で、3万6370人に達する。前年比で2127人(6.2%)増、平成29年比では6000人以上増加した。
出典:厚生労働省
学び直しガイドライン(骨子案) 節目ごとにコンサル実施を 厚生労働省
厚生労働省は、社会人の自律的な学び・学び直しの促進に向けて、労使の取り組むべき事項を示したガイドライン(骨子案)を明らかにした。
取組み事項には、能力・スキルの明確化や学びの方向性・目標の擦り合わせと共有、学ぶ機会の確保などを挙げた。自身のキャリアを振り返るとともに、今後めざすキャリアのために何を学ぶべきかを本人に考えてもらうための取組み例として、キャリアコンサルティングの定期的な実施や、昇進時、出産・育児など家庭生活で変化が生じたとき、定年前といった節目ごとの実施を提示している。
出典:労働新聞 令和4年6月13日
企業のテレワーク導入率5割超 総務省 令和4年5月27日
総務省は令和3年「通信利用動向調査」結果を公表した。調査結果では、テレワークを導入する企業の割合が51.9%に上ることがわかった。同調査で導入率が5割を超えるのは初めてとなる。
導入しているテレワークの形態は「在宅勤務」が91.5%、「モバイルワーク」は30.5%、「サテライトオフィス」が15.2%。導入目的は「新型コロナ対応」が90.5%、「勤務者の移動時間短縮・混雑回避」が37.0%、「事業継続」が31.1%。
ホームページ
出典:総務省
令和3年労働組合活動等に関する実態調査結果公表 厚生労働省 令和4年6月8日
厚生労働省は、令和3年「労働組合活動等に関する実態調査」の結果をとりまとめ、公表した。
【結果概要】
●労使関係についての認識
労使関係が「安定的に維持されている・おおむね安定的に維持されている」と認識している労働組合は 92.9%
●労働組合員数の変化に関する状況
3年前(平成 30 年6月)と比べた組合員数の変化は、「増加した」31.4%、「変わらない」25.8%、「減少した」42.7%
●正社員以外の労働者に関する状況
(1)労働者の種類別に「組合加入資格がある」
「パートタイム労働者」37.3%、「有期契約労働者」41.5%、「嘱託労働者」39.6%、「派遣労働者」6.6%
(2)労働協約の規定の状況
「労働協約の規定がある」42.1%
労働協約の規定がある事項、
「正社員以外の労働者(派遣労働者を除く)の労働 条件」34.7%、「有期契約労働者の雇入れに関する事項」28.3%、「パートタイム労働者の雇入れに関する事項」28.0%
ホームページ
出典:厚生労働省
2023年春卒の大学生内定率73.1% 17年卒以降で過去最高 リクルート 令和4年6月7日
株式会社リクルートの就職みらい研究所は、「就職プロセス調査」の結果を発表した。
2023年春卒業予定の大学生の就職内定率(2022年6月1日時点)は、前年同時点と比べ4.6ポイント上昇の73.1%と、就職・採用活動の日程が現行スケジュールの6月選考解禁となった2017年卒以降で最も高くなった。文理別では、理系の内定率が82.5%(+4.2ポイント)と高い数値だった。
ホームページ
出典:就職みらい研究所(株式会社リクルート)
毎月勤労統計調査 令和4年4月分結果速報を公表 厚生労働省 令和4年6月7日
厚生労働省は、「毎月勤労統計調査」令和4年4月分結果速報をとりまとめ公表した。
【結果概要】前年同月比
●現金給与総額 283,475円(1.7%増)
・うち一般労働者365,411円(1.9%増)、パートタイム労働者100,852円(1.0%増)
・パートタイム労働者比率30.77%(0.06ポイント上昇)
・一般労働者の所定内給与320,694円(1.2%増)
・パートタイム労働者の時間当たり給与は 1,226円(1.2%増)
●共通事業所による現金給与総額1.5%増
・うち一般労働者が1.5%増、パートタイム労働者が0.6%増
●就業形態計の所定外労働時間 10.7時間(5.7%増)
ホームページ
出典:厚生労働省
小学校休業等対応助成金・支援金 9月末まで延長へ 厚生労働省 令和4年5月31日
厚生労働省は、令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について公表した。新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、令和4年6月末までの間に取得した休暇について支援を行っている。この措置を令和4年9月末まで延長する方針を決めた。
ホームページ
出典:厚生労働省
雇用調整助成金の特例措置 9月末まで延長へ 厚生労働省 令和4年5月31日
雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は令和4年9月末まで延長することを決めた。
雇用調整助成金は、企業が従業員の雇用を維持した場合に休業手当などの一部が助成される制度。
特例措置の期限は6月末までとなっていたが、厚生労働省は新型コロナの影響が続いていて原油高などで経済の回復の遅れも懸念されるとして、今の内容のまま令和4年9月末まで延長する方針を決めた。
ホームページ
出典:厚生労働省
育児休業給付手取り10割に 自民党が提言 自民党少子化対策調査会
自民党の少子化対策調査会は、育児休業期間中の収入の減少が育休取得・継続の妨げの一つの要因となっていると指摘し、育児休業取得前と後で経済状況が変わらないよう、男女ともに育児休業給付を実質手取り10割の水準になるよう検討するべきと提言した。
現行制度は、育休開始から6カ月間は休業前の賃金の67%、その後は50%としている。最初の6カ月間は手取りで休業前の8割ほどが確保できる一方、その後は6割程度の水準に落ち込む。
出典:労働新聞 令和4年6月6日
障害者雇用 調整金・報奨金の減額を提言 厚生労働省
厚生労働省は、労働政策審議会障害者雇用分科会(5月25日開催)の意見書案を明らかにした。
常用労働者100人超事業者を対象としている納付金制度における財政の安定化などに向け、一定要件に該当する際の調整金・報奨金の減額を提言している。調整金について、支給対象人数が10人を超える場合、その超過人数分の支給額を50%に削減する意向。
同日の分科会では、調整金の減額などに対して使用者委員から反対意見が出た。厚労省は今後改めて分科会を開き、意見書をまとめる方針。
出典:労働新聞 令和4年6月6日
6月は「外国人労働者問題啓発月間」 厚生労働省 令和4年5月31日
厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行う。
外国人労働者の就労形態は派遣・請負が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが見られる。厚生労働省は、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていく。
ホームページ
出典:厚生労働省
改正「公益通報者保護法」 2022年6月1日から施行 消費者庁
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするもの。
詳細は消費者庁HP。
<主な改正内容>
保護される通報者の範囲、保護される通報の対象の範囲、保護の内容。
事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け。(※中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務
ホームページ
出典:消費者庁
リスキル推進に報酬提示を 期待する役割想定し 経済産業省 令和4年5月30日
経済産業省は、人的資本経営の実現に向けた検討会の報告書を取りまとめ、経営環境の急速な変化に対応するための人材戦略の1つとして、リスキル・学び直しの推進を掲げた。
報告書では、人的資本経営を実現するための取組みとして、経営環境の急速な変化に対応できるよう、組織に不足しているスキルを把握し、社員にリスキルを促す重要性を指摘した。リスキルは、それぞれの社員が強い意欲を持って自律的に推進する必要があり、企業は積極的に支援すべきとしている。
職場内では確保できる学習時間が不十分であるケースを想定し、社外での学習機会を提供することも重要とした。具体的な施策として、長期間職場を離れて学習などに活用するための長期休暇(サバティカル休暇)制度の導入や、大学・大学院への留学などを挙げている。
出典:労働新聞 令和4年5月30日
労災の取扱い明確化 新型コロナ後遺症で通達 厚生労働省 令和4年5月30日
厚生労働省は新型コロナウイルスの罹患後症状(後遺症)の労災の取扱いに関する新たな通達を発出した。従来から罹患後症状についても労災補償の対象としてきたが、4月に罹患後症状に関する診療の手引きが取りまとめられたのを受け、取扱いの明確化を図った。手引きに記載のある症状などは労災保険の療養補償給付の対象になるとしている。
同手引きでは罹患後症状の代表的な例として、疲労感・倦怠感や咳、息切れ、記憶障害、集中力低下、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害などを挙げた。通達では手引きに記載のある症状のほか、新型コロナにより新たに発症した、精神障害を含む傷病や合併症も労災の対象になるとした。十分な治療をしても改善の見込みがなく、症状固定と判断される場合は障害補償給付に移行する。
職場復帰時には主治医の意見を参考に、労働時間の短縮や通院機会の確保など、職場での配慮が必要とした。
出典:労働新聞 令和4年5月30日
人材育成計画を半数が作成せず 高齢・障害・求職者雇用支援機構 令和4年5月30日
高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は企業が求める職業能力と人材に関する令和3年度の調査結果をまとめ公表した。人材育成計画について、47.2%の企業が「作成していない」と回答している。「作成している」は35.5%、「作成予定」は17.3%だった。
作成していない理由は32.6%が「担当する部課がない」とした。「作成方法が分からない」が17.8%、「人材がいない」が16.0%、「時間がない」が15.3%と続く。能力開発推進者は81.1%が「選任していない」とした。
出典:労働新聞 令和4年5月30日
企業規模要件撤廃も 勤労者皆保険で提言 全世代型社保会議 令和4年5月30日
政府の全世代型社会保障構築会議は5月17日、議論の中間整理をまとめた。
中間整理では、働き方の多様化が進むなか、働き方に対して「中立」な社会保障制度の構築を進める必要があると指摘。対策として、短時間労働者の保険加入に関する企業規模要件の段階的な引下げを内容とする令和2年年金制度改正法に基づき、被用者保険の適用拡大を着実に実施するとした。
女性就労の制約となっている恐れのある社会保障や税制についても、働き方に中立的な制度に変えていくことが重要とし、社会保険加入の収入目安である「106万円の壁」については、最低賃金を引き上げれば解消すると見込んでいる。
出典:労働新聞 令和4年5月30日
雇用調整の恐れ医療福祉が最多 コロナによる影響 厚生労働省 令和4年5月30日
厚生労働省は、都道府県労働局などに相談があった事案について集計し、今年5月における新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整の状況(13日時点)を取りまとめた。
雇用調整の恐れがある事業所数が最も多いのは医療、福祉で、27事業所に上った。以下、建設業が26事業所、飲食業が17事業所と続く。産業計は144事業所。解雇などの見込み労働者数は計590人。業種別では、製造業が最多の165人、次いで医療、福祉が121人だった。
出典:労働新聞 令和4年5月30日
社員の教育訓練 OJT頼み2割 日本商工会議所/東京商工会議所 令和4年5月23日
日本商工会議所と東京商工会議所は、会員企業3222社に従業員への研修・教育訓練に関する調査を行い、結果を発表した。
従業員に対して研修を実施していない、もしくはOJTのみ実施している企業は19.1%だった。
研修・訓練方法について、「OJT」が最も多く、75.6%だった。次いで、「外部主催の研修・セミナー受講」57.3%、「業務に関連する資格取得の奨励」51.0%、「社内での集合研修の実施」41.2%などとなっている。研修や教育訓練の実施に当たっての課題には、約半数の44.7%が「業務多忙など時間的余裕がない」を挙げた。
出典:労働新聞 令和4年5月23日
一般職業紹介状況(令和4年4月分)公表 厚生労働省 令和4年5月31日
厚生労働省は、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として令和4年4月分を公表した。
【結果概要】
【有効求人倍率(季節調整値)】1.23倍、前月を0.01ポイント上回る。
【新規求人倍率(季節調整値)】2.19倍、前月を0.03ポイント上回る。
【正社員有効求人倍率(季節調整値)】0.97倍、前月を0.03ポイント上回る。
【4月の有効求人(季節調整値)】前月に比べ0.9%増、有効求職者(同)は0.1%減。
【4月の新規求人(原数値)】前年同月と比較すると12.3%増。
【産業別】宿泊業,飲食サービス業(49.6%増)、製造業(21.9%増)、サービス業(他に分類されないもの)(15.3%増)、運輸業,郵便業(13.1%増)などで増加。
都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)
【就業地別】最高は福井県の1.99倍、最低は沖縄県の0.92倍
ホームページ
出典:厚生労働省
労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)4月分結果 総務省統計局 令和4年5月31日
総務省統計局は、労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)4月分をとりまとめ、結果を公表した。
【結果概要】
(1) 就業者数
就業者数は6727万人。前年同月に比べ24万人の増加。7か月ぶりの増加
(2) 完全失業者数
完全失業者数は188万人。前年同月に比べ23万人の減少。10か月連続の減少
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は2.5%。前月に比べ0.1ポイントの低下
ホームページ
出典:総務省統計局
女性管理職の意識調査結果発表 パーソルキャリア株式会社 令和4年5月23日
パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda(デューダ)」は、20代~50代の女性管理職を対象に意識調査を行い、結果を発表した。
【主な調査結果】
管理職のオファーを承諾する前、6割以上が「不安や悩みがあった」と回答した一方、実際に「管理職になってよかったと思う」と回答した人は約6割いることがわかった。
また、管理職になると決めたとき、あったらよりよかったものは「公平な評価制度」が最多であった。
ホームページ
出典:パーソルキャリア
男女賃金差、開示義務付け 300人超企業、非正規も 政府、今夏施行へ 共同通信社/WEB労政時報 令和4年5月20日
政府は20日、従業員300人超を雇用する企業に対し、男女の賃金差の開示を義務付ける方針を決めた。女性活躍推進法に基づく省令は現在、従業員300人超の企業に対し、管理職に占める女性割合や平均勤続年数の男女差など厚労省が挙げた十数項目のうち2項目以上を公表するよう義務付けているが、どれを公表するかは企業側に委ねられている。今回は男女の賃金差を必須の公表項目として加えるよう省令を見直す。
(共同通信社)https://nordot.app/900327623618478080?c=39546741839462401
(WEB労政時報)https://www.rosei.jp/readers/article/82999
出典:共同通信社/労政時報WEB
「人材版伊藤レポート2.0」公表 経済産業省 令和4年5月13日
経済産業省は、持続的な企業価値の向上に向けて、経営戦略と連動した人材戦略をどう実践するかという点について、2020年9月に公表した「人材版伊藤レポート」に「実践事例集」を追加する形でまとめた「人材版伊藤レポート2.0」とともに、併せて、「人的資本経営に関する調査 集計結果」を公表した。「人材版伊藤レポート2.0」では、「人的資本」の重要性を認識するとともに、人的資本経営という変革を、どう具体化し、実践に移していくかを主眼とし、それに有用となるアイディアを提示している。
ホームページ
出典:経済産業省
同一労働同一賃金 4割強で待遇差是正推進へ 労働新聞 令和4年5月23日
東京都が都内3000社に実施したパートタイマーに関する実態調査によると、正社員との不合理な待遇差をなくすための取組みを実施済み、もしくは実施を予定している企業の割合が4割強に上った。そのうち、職務評価などを通じて「根拠の明確化のみで対応する」とした割合は18%に留まり、77%がパートの待遇に対して何らかの改善に取り組んでいる。
改善内容別の取組み割合は、休暇制度の見直し45%、基本給の引上げ・変更36%、賞与の支給対象拡大30%などとなっている。
出典:労働新聞
精神障害者 週20時間未満を雇用率に算入 労働新聞 令和4年5月16日
厚生労働省は、週20時間未満で働く精神障害者などについて、企業の実雇用率の算定対象に加える方針である。4月27日に開いた労働政策審議会障害者雇用分科会に、追加対象となる労働者の範囲や算定方法などを提示している。週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を対象とし、1人につき0.5人とカウントする。障害特性で長時間の勤務が難しい障害者について、雇用機会の拡大を図る狙い。
出典:労働新聞
「賃金のデジタル支払い」 厚労省が制度の全体像整理 労働新聞 令和4年5月23日
厚生労働省はこのほど、制度化に向けた検討を進めている「賃金のデジタル支払い」(資金移動業者の口座への賃金支払い)について、労働政策審議会労働条件分科会に対して、検討中の制度の全体像を提示した。使用者から移動業者口座への賃金支払いは労働者の同意を必須とし、同意を得る際は、移動業者の破綻時の保証や不正引出し時の補償といった事項について説明しなければならないとしている。厚労省においては、説明事項を記載した同意書の様式例を作成する方向。様式例では、実質的にデジタル支払いを強制している場合は労働基準法違反になることも明記する。
出典:労働新聞
令和4年3月大学等卒業者の就職状況(4月1日現在)を公表 厚生労働省/文部科学省 令和4年5月20日
厚生労働省と文部科学省は、令和4年3月大学等卒業者の就職状況を共同で調査し、令和4年4月1日現在の状況を取りまとめ公表した。
【結果概要】
●大学の就職率は95.8%(前年同期比0.2ポイント低下)。
【国公立大学】96.1%(同0.2ポイント上昇)
【私立大学】95.6%(同0.5ポイント低下) ●男女別では、男子大学生の就職率は94.6%(前年同期比0.4ポイント低下)、女子は97.1%(同0.1ポイント低下)。
【国公立大学】男子:94.7%、女子:97.6%
【私立大学】男子:94.5%、女子:97.0%
●地域別では、中部地区の就職率が最も高く、97.0%(前年同期比1.3ポイント低下)
ホームページ
出典:厚生労働省/文部科学省
社会人の「学びに関する意識・実態把握調査」結果公表 株式会社リクルート 2022年5月17日
株式会社リクルートが提供する社会人・学生のための大学・大学院、通信制大学・大学院検索サイト『スタディサプリ社会人大学・大学院』は、社会人および企業の経営層・ミドルマネジメント層を対象にした「学びに関する意識・実態把握調査」の結果を公表した。
社会人全体の4割弱が社会人向け大学・大学院進学への興味関心を抱いており、年齢が低いほど学ぶ意欲が高い傾向で、男女とも20・30代で7割前後と特に意欲が高い。
実際に進学した人たちの65%は「視野が広がった」「専門性が深くなった」などポジティブな効果を感じている。その一方で、進学への支援制度が「ある」と回答した企業は 6%にとどまることがわかった。
ホームページ
出典:株式会社リクルート
2022年度新入社員の初任給調査結果を公表 一般財団法人労務行政研究所 2022年5月11日
一般財団法人 労務行政研究所は2022年4月の新卒入社者初任給を調査し、4月13日までにデータを得られた東証プライム上場企業 165 社について、速報集計の結果を公表した。
<調査結果>
(1)初任給の改定状況:
「全学歴引き上げた」企業は 41.8%(21年度比20ポイント以上上昇)
「全学歴据え置き」は 49.7%(同20 ポイント以上低下)
(2)初任給の水準:
大学卒(一律設定)21万6637 円、大学院卒修士23万4239 円、短大卒18万7044 円、高校卒(一律設定)17万5234 円
ホームページ
出典:一般財団法人労務行政研究所
働く10,000人の就業・成長定点調査2022 結果を公表 パーソル総合研究所 2022年5月10日
パーソル総合研究所は、あらゆる雇用形態・業職種を対象とした10,000人を対象に、働き方の実態や就業意識、成長の実感度・イメージについて経年調査をし、「働く10,000人の就業・成長定点調査2022」の結果を公開した。
本調査は、働くことを通じた成長、働き方の実態、働く人の価値観、働く人の状態の4つのカテゴリーについて調査を実施している。
ホームページ
出典:株式会社 パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」
2021年度下半期 中途採用動向調査結果を公表 株式会社リクルート 2022年4月27日
株式会社リクルートは、転職支援サービス『リクルートエージェント』利用企業11,749社を対象に、21年度下半期の中途採用充足状況および22年度通期の中途採用計画の状況、中途入社者の賃金・処遇の計画などについて調査を実施し、結果を公表した。
(結果概要)
【21年度下半期の中途採用充足状況】
80.8%が採用計画に対して未充足。中途採用が充足した企業は 20%を下回る。
【22 年度通期の中途採用計画(前年度比増減状況)
前年度比で中途採用計画を増やす企業は 25.1%、減らす企業は 4.0%
【22 年度 中途入社者の賃金・処遇の計画(前年度比増減状況)
全体の 15.0%が賃金・処遇を「増やす」と回答。一方で「減らす」という企業はほぼ皆無
ホームページ
出典:株式会社リクルート
スマホで簡単に年金額試算「公的年金シミュレーター」試験運用開始 厚生労働省 令和4年4月25日
厚生労働省は、スマートフォンやタブレットで、年金額を簡単に試算できるツール「公的年金シミュレーター」を開発し、4月25日から試験運用を開始した。
「公的年金シミュレーター」は、日本年金機構から届く「ねんきん定期便」に記載の二次元コードをスマートフォンなどで読み取り、生年月日を入力するだけで、働き方・暮らし方の変化に応じて将来受給できる年金額を手軽に試算することができる。
ホームページ
出典:厚生労働省
2022年度愛知ブランド企業の募集について 愛知県産業振興課 令和4年5月9日
愛知県では、県内製造業の実力を広くアピールするため、オンリーワンやシェアトップなど、世界に誇る独自の技術や製品を持つ優れたモノづくり企業を「愛知ブランド企業」として認定している。2003年度から認定を開始し、現在400社を認定。
この度、新たに「愛知ブランド企業」として認定を希望する企業を募集中。
申請期間:2022年5月11日(水曜日)から6月17日(金曜日)まで
認定期間:2023年4月1日から5年間(更新あり)
【申請詳細について】
愛知県ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/press-release/2022aichibrandboshuu.html
【愛知ブランド事業の詳細について】
愛知ブランドWebサイト
https://www.aichi-brand.jp
ホームページ
出典:愛知県産業振興課
「日本型」変革を提言 事務職の需要4割減に 労働新聞 令和4年5月16日
経済産業省は、雇用や人材育成の政策課題を検討する未来人材会議の中間案を取りまとめた。2050年には情報処理・通信技術者が現在より20%増加し、事務従事者は40%以上減少するなど、労働需要が大きく変動すると推計している。変動に対応するためには、旧来の日本型雇用システムから転換し、多様なキャリアを踏まえた税制などの見直しを行い、ジョブ型雇用のガイドラインを作成すべきと提言した。
出典:労働新聞 令和4年5月16日
令和4年度業務改善助成金のご案内 厚生労働省/愛知労働局労働基準部賃金課 令和4年5月12日
●「業務改善助成金(通常コース)」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業所を支援。
●「業務改善助成金(特例コース)」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%
以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成。
業務改善助成金(通常コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
業務改善助成金(特例コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
出典:厚生労働省/愛知労働局労働基準部賃金課
ホワイトカラー向け能力診断ツールを開発 中高年齢者が対象 労働新聞 令和4年5月16日
厚生労働省は、40~60歳代のミドルシニア層のホワイトカラー職種向けに職業能力を診断できる「ポータブルスキル見える化ツール」を開発し、職業情報提供サイト「job tag」内で公開した。「現状の把握」や「計画の立案」といった自身のスキルを15分程度で入力すると、本人の持ち味を生かせる職務や職位が示される仕組みで、労働者のキャリアの形成・転換に生かすことができる。キャリアコンサルタントなどの支援者が、企業内の労働者のキャリア自律と自己啓発を促すための相談や、求職者の職業相談の場面で活用することなどを想定している。
出典:労働新聞
副業時の健康確保へ メンタル対策を厚生労働省が通知 労働新聞 令和4年5月6日
厚生労働省は、平成29年3月に発出した通達「『過労死等ゼロ』緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」を改訂し、都道府県労働局に通知した。精神障害による労災支給決定が行われた副業・兼業労働者を使用していた各事業者への対応を新たに盛り込んだ。
出典:労働新聞
「コロナ禍でも労働生産性上昇」日本生産性本部が生産性レポート公表 日本生産性本部 令和4年4月25日
日本生産性本部は、「コロナ禍でも労働生産性が上昇した企業は何が違うのか~企業レベル生産性データベース(JPIC-DB)にもとづく生産性分析~」を公表した。レポートでは、「企業レベル生産性データベース」として提供している企業財務データをもとに、企業の労働生産性がどのように変化したのかについて概観している。
出典:生産性新聞・日本生産性本部
不妊治療 ハラスメントない職場を 厚労省が手引改訂 労働新聞 令和4年4月25日
厚生労働省は、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」を改訂した。不妊治療を受ける夫婦が増加傾向にある。マニュアルでは両立支援に向けた導入ステップを示しており、とくにハラスメントについては軽々しく扱うといった振る舞いは慎むよう周知が必要とした。制度導入に向けた手順やポイントを示した企業事例も9社から20社に充実している。
出典:労働新聞
10月以降開始した育休に適用 社保免除の要件改正 労働新聞 令和4年5月2日
厚生労働省は10月1日に施行となる育児休業中の社会保険料免除の要件改正に関するQ&Aをまとめ、地方厚生局などに通知した。現行制度では、開始日による不公平が生じていたが、改正法では現行の要件に加え同一の月内で14日以上取得したケースについても免除の対象とする。賞与に対する免除措置も見直しを図る。改正後の要件は10月1日以降に開始した育休に適用し、施行日をまたぐ育休には改正前の要件を適用するとしている。
出典:労働新聞
男性育休の有給化が加速 産後4週分義務化も 労働新聞 令和4年5月2日
今年10月の「産後パパ育休」のスタートを控え、さらに踏み込んで男性の育休取得を促す動きが相次いでいる。有給での付与を前提として4週分の取得義務化に踏み切ったケースや、子が1歳になるまでに8週分を柔軟に有給取得できるようにしたケースなどがみられる。取得期間の長さよりもまず取得率の向上が目標とされてきた従来の方向性が、同制度創設を機に変わってくるのか否か、今後の動向が注目される。
出典:労働新聞
2021 年「夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」の概要 (一社)日本経済団体連合会/(一社)東京経営者協会 2022年4月27日
非管理職・管理職別にみると、非管理職では、夏季 72 万 58 円(対 前年増減率△1.0%)、冬季 69 万 2,033 円(同+1.9%)、管理職では、夏季146 万1,602 円(同+0.2%)、冬季134 万 2,201 円(同+ 4.5%)となった。
前年は、コロナ禍等の影響により、夏季・冬季ともに対前年増減率はマイナスとなったが、非管理職の夏季を除いてプラスとなるなど、回復に転じた。
ホームページ
出典:(一社)日本経済団体連合会/(一社)東京経営者協会
入社前後のトラブルに関する調査2022結果公表 日本労働組合総連合会 2022年4月28日
日本労働組合総連合会は、新卒採用における入社前後のトラブルの実態を把握するために、2016年の調査に続き2回目となる「入社前後のトラブルに関する調査2022」をインターネットリサーチにより2022年2月28日~3月2日の3日間で実施、大学卒業後に新卒で正社員として就職した全国の入社2年目~5年目の男女1,000名の有効サンプルを集計し、公表した。
【調査結果】
◆内定者インターンシップやアルバイト 参加者の46.9%が「必ず参加することを求められた」または「参加を強く求められた」と回答
◆新卒入社した会社を「離職した」が 3 割を超す
◆労働条件通知書を「書面にて渡された」は 59.9%、前回調査より下降
◆新卒入社した会社を辞めた理由の 1 位は「仕事が自分に合わない」
労働条件通知書を書面で“渡されていない”人では「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が 1 位に
◆新卒入社した会社における「労働条件通知書の閲覧可否」「新入社員研修や上司・先輩からの指導・アドバイス状況」で労働組合の有無による違いが明らかになった。
ホームページ
出典:日本労働組合総連合会
2022年度第1回労働講座の受講者を募集 愛知県 2022年4月27日
愛知県では、労働問題を解決する上で必要な基礎的知識などを提供することにより、安定した労使関係を形成することを目的として、中小企業の事業主や人事労務担当者等を対象とする労働講座を開催している。
今年度の第1回労働講座では、職場のハラスメント防止対策をテーマとし、特定社会保険労務士の馬場 三紀子(ばば みきこ)氏が、具体的な事例を交えながら、ハラスメントのない職場づくりのポイント等について講演。また、愛知労働局の担当官が、改正労働施策総合推進法の概要やハラスメント防止対策について説明する。申込先着順、受講料は無料。
日時:2022年6月1日(水曜日)午後1時30分から午後4時まで
場所:愛知県女性総合センター(ウィルあいち) 1階セミナールーム1・2
ホームページ
出典:愛知県
第 9 回「働く人の意識調査」~新型コロナが働く人の意識に及ぼす影響を継続調査~結果を公表 公益財団法人日本生産性本部 2022年4月22日
公益財団法人日本生産性本部は「新型コロナウイルス感染症が組織で働く人の意識に及ぼす影響」の継続調査(第9回「働く人の意識調査」)結果を取りまとめ、公表した。
前回に続き働く人の景気見通しが一段と悲観的になり、新型コロナの新規感染者数の高止まりや円安・物価高が生活に影を落としていることが確認さた。テレワーク実施率は、過去最低を記録した前回から20.0%に微増。背景には、感染に対する中堅・大企業の慎重姿勢があるものと推察される。また、在宅勤務の満足度は84.4%と過去最高を記録し、約2年前(2020年5月調査)の57.0%から大幅な伸びとなった。さらに、今回の調査で新設した職場における生産性向上への取り組みに関しては、何らかの取り組みを経験した雇用者は4~5割に上り、テレワーカーと非テレワーカーの取り組み実施率に大きな差があることが明らかになった。
ホームページ
出典:公益財団法人日本生産性本部
毎月勤労統計調査 令和4年3月分結果速報 を公表 厚生労働省 令和4年5月9日
厚生労働省は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とし、特別調査はこれらを補完することを目的とした「毎月勤労統計調査」令和4年3月分結果速報をとりまとめ公表した。
(前年同月比較)
○現金給与総額は286,567円(1.2%増)。うち一般労働者が372,765円(1.5%増)、パートタイム 労働者が97,309円(0.2%減)となり、パートタイム労働者比率が31.29%(0.09ポイント上昇)となった。 なお、一般労働者の所定内給与は317,546円(0.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は 1,232円(1.8%増)となった。
○共通事業所による現金給与総額は1.5%増。うち一般労働者が1.5%増、パートタイム労働者が0.4%増となった。
○就業形態計の所定外労働時間は10.3時間(2.8%増)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
愛知県の勤労(2022年2月分)を公表 愛知県 2022年4月28日
毎月勤労統計調査地方調査は、統計法に基づく基幹統計として、愛知県内の雇用労働者の賃金、労働時間及び雇用 について毎月の変動を明らかにすることを目的とし、愛知県は2022年2月分を公表した。
結果の概要:2022年2月分の調査産業計、事業所規模5人以上
【きまって支給する給与】277,210円となり、前年同月に比べ0.4%の増加(2か月連続)
【所定外労働時間】11.4時間となり、前年同月に比べ0.8%の減少(2か月連続)
【常用雇用指数】98.3(2020年平均=100)となり、前年同月に比べ 0.9%の減少(4か月連続)
ホームページ
出典:愛知県県民文化局統計課 勤労統計グループ
一般職業紹介状況(令和4年3月分及び令和3年度分)について 厚生労働省職業安定局 令和4年4月26日
厚生労働省は、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、一般職業紹介状況3月分及び令和3年度分を公表した。
(季節調整値)
令和4年3月の有効求人倍率は1.22倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
令和4年3月の正社員有効求人倍率は0.94倍で、前月を0.01ポイント上昇。
令和4年3月の新規求人倍率は2.16倍で、前月に比べて0.05ポイント低下。
都道府県別の有効求人倍率(就業地別)最高は福井県の2.05倍、最低は沖縄県の0.85倍
令和3年度平均の有効求人倍率は1.16倍で、前年度に比べて0.06ポイント上昇。
令和3年度平均の有効求人は前年度に比べ9.5%増となり、有効求職者は3.9%増。
ホームページ
出典:厚生労働省職業安定局 雇用政策課
県内大学・短期大学生の 2022年3月卒業者の就職内定率(3月末現在)を公表 愛知県労働局就業促進課 2022年4月25日
愛知県では 1994 年度から県内の大学・短期大学における就職内定状況を調査公表している。
2021年度(2022年3月)に県内の大学等を卒業した学生の3月末現在の就職内定状況を公表した。 大学・短期大学を合わせた全体の就職内定率(※就職希望者に占める就職内定者の割合)は 96.5%(前年同月 96.2%:0.3 ポイント上昇) となった。
ホームページ
出典:愛知県労働局就業促進課 若年者雇用対策グループ
令和4年3月新規高等学校・中学校卒業者の職業紹介状況について 愛知労働局 令和4年4月25日
新規高等学校卒業者の就職決定者数は就職希望者の減少もあり、9,703 人と前年同月 比で 7.0%減少。求人数は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い 2 年連 続で低水準に止まったが、就職決定率は 99.8%と、前年同月に比べて 0.2 ポイントの 増加となった。 また、新規中学校卒業者の就職決定者数は 116 人となり、前年同月比で 14.1%減少したが、就職決定率は 100.0%と希望者全員の就職が叶った。
ホームページ
出典:愛知労働局職業安定部職業安定課
令和4年度「就職氷河期世代の就職サポート」 参加者・受入企業募集 愛知県 令和4年4月25日
愛知県では、2019年度に経済団体、労働団体及び業界団体等で構成する「あいち就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」を全国に先駆けて設置し、不安定な就業を余儀なくされている方や長期間無業の状態にある方等の就職・正社員化を支援しており、2021年度から「就職氷河期世代の就職サポート」を実施している。
「就職氷河期世代の就職サポート」では、正社員等の安定した就職を希望する就職氷河期世代の方々を対象に、応募書類の書き方やパソコン研修など、ビジネススキルを向上するための「就職スタートアップ研修」や、企業での「トライアル勤務」に参加いただき、受入企業への正社員就職を目指す。今年度の当事業への参加者及び「トライアル勤務」の受入企業を募集中。
ホームページ
出典:愛知県
毎月勤労統計調査 令和4年2月分結果確報 厚生労働省 令和4年4月22日
現金給与総額は268,898円(1.2%増)となった。うち一般労働者が348,256円(1.3%増)、パートタイム労働者が95,348円(1.5%増)となり、パートタイム労働者比率が31.35%(0.07ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は315,689円(0.8%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,253円(2.0%増)となった。
共通事業所による現金給与総額は0.9%増となった。うち一般労働者が1.1%増、パートタイム労働者が0.2%減となった。就業形態計の所定外労働時間は9.8時間(5.1%増)となった。
ホームページ
出典:厚生労働省 政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
中小企業応援障害者雇用奨励金 支給要件改正 愛知県 令和4年4月1日
愛知県では、2017年度に障害者雇用の経験のない中小企業(常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業)が、対象となる障害者を初めて雇用した場合(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む。)に奨励金を支給する「中小企業応援障害者雇用奨励金」制度を独自に創設し、障害者雇用の促進を図っている。
令和4年4月1日より支給要件を改正し、2022年4月1日以降の雇入れについては、採用時の年齢の上限を撤廃した。
ホームページ
愛知県
令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況(2月1日現在) 厚生労働省 令和4年3月18日
厚生労働省と文部科学省は、令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和4年2月1日現在の状況を取りまとめ公表した。
【調査結果の主な概要】
大学(学部)は89.7%(前年同期差+0.2ポイント)
短期大学は86.9%(同+4.2ポイント)
大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では89.7%(同+0.4ポイント)
大学等に専修学校(専門課程)を含めると88.8%(同+0.8ポイント)
ホームページ
厚生労働省
毎月勤労統計調査 令和4年2月分結果速報 厚生労働省 令和4年4月5日
前年同月と比較して、現金給与総額は269,142円(1.2%増)となった。うち、一般労働者が347,971円(1.2%増)、パートタイム労働者が95,196円(1.3%増)となり、パートタイム労働者比率が31.17%(0.11ポイント低下)となった。なお、一般労働者の所定内給与は315,404円(0.7%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,252円(1.9%増)となった。
共通事業所による現金給与総額は1.0%増となった。うち、一般労働者が1.1%増、パートタイム労働者が0.3%増となった。就業形態計の所定外労働時間は9.8時間(5.1%増)となった。
ホームページ
厚生労働省 政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
「一般職業紹介状況(令和4年2月分)」を公表 厚生労働省 令和4年3月29日
厚生労働省は、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ公表した。
●令和4年2月(季節調整値)
有効求人倍率 1.21倍(前月比0.01ポイント増)
新規求人倍率は2.21倍(前月比0.05ポイント増)
正社員有効求人倍率0.93倍(前月比0.02ポイント増)
有効求人 前月比0.2%減、有効求職者 前月比1.4%減
新規求人(原数値)は前年同月比9.5%増
〇産業別
宿泊業,飲食サービス業(28.4%増)、製造業(27.6%増)、情報通信業(18.1%増)
教育,学習支援業(0.6%減)
〇都道府県別有効求人倍率(季節調整値)
就業地別:最高:福井県2.07倍、最低:沖縄県0.86倍
受理地別:最高:福井県1.91倍、最低:沖縄県0.79倍
ホームページ
厚生労働省 職業安定局 雇用政策課
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施中 厚生労働省 令和4年3月31日
厚生労働省では、全国の学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施する。
なお、本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で8回目となる。
学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や大学等での出張相談などを実施する。
ホームページ
厚生労働省 労働基準局労働条件政策課労働条件確保改善対策室
令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が拡大 令和4年3月14日 厚生労働省
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を 改正する省令が令和4年3月10日に公布された。本改正により、令和4年4月1日から、労災保険の特別加入について、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も対象となった。
ホームページ
出典:厚生労働省
新たな認定制度「トライくるみん」を創設、不妊治療と仕事の両立企業に「プラス」新設 令和4年3月14日 厚生労働省
厚生労働省は、次世代育成支援対策推進法施行規則を改正し、認定基準を改正するとともに、新たな認定制度「トライくるみん」を創設し、令和4年4月1日から施行した。
「くるみん認定」および「プラチナくるみん認定」は、男性の育児休業等取得率の引き上げなど認定基準を改正。認定基準の引き上げを踏まえ、現行のくるみん認定と同基準の認定制度「トライくるみん」を新設。
さらに、不妊治療と仕事との両立に取り組む企業を認定する「プラス」制度を新設し、企業において子育てや不妊治療等を行う労働者が職業生活と家庭生活の両立を図ることができる職場環境の整備が推進されるよう、取り組み支援を図る。
ホームページ
出典:厚生労働省雇用環境・均等局 職業生活両立課